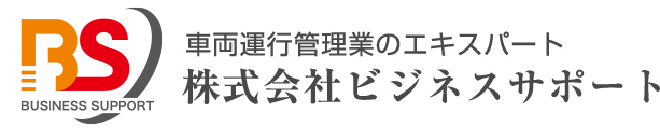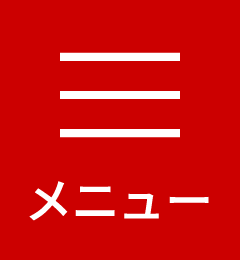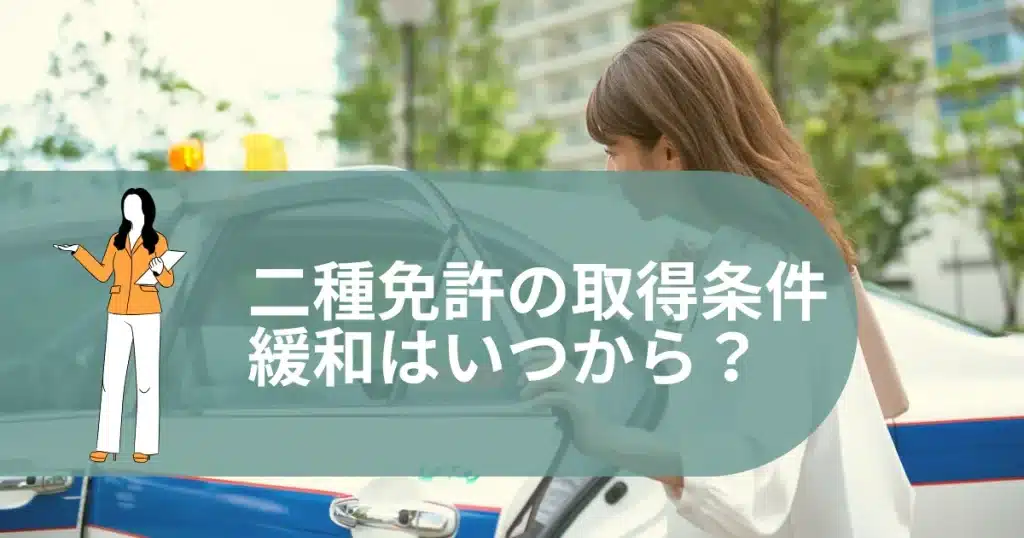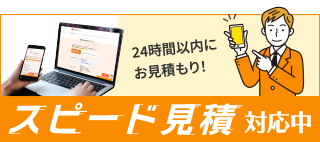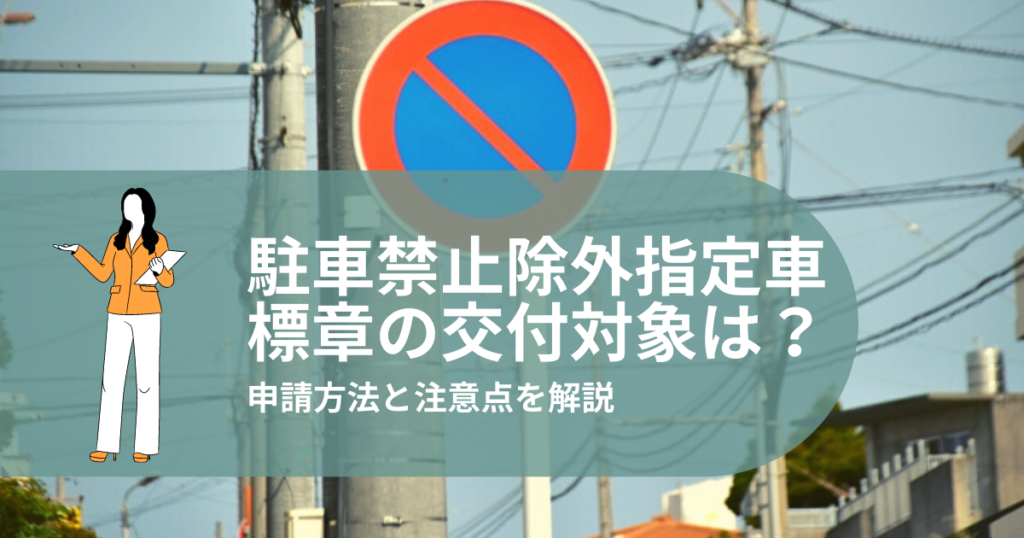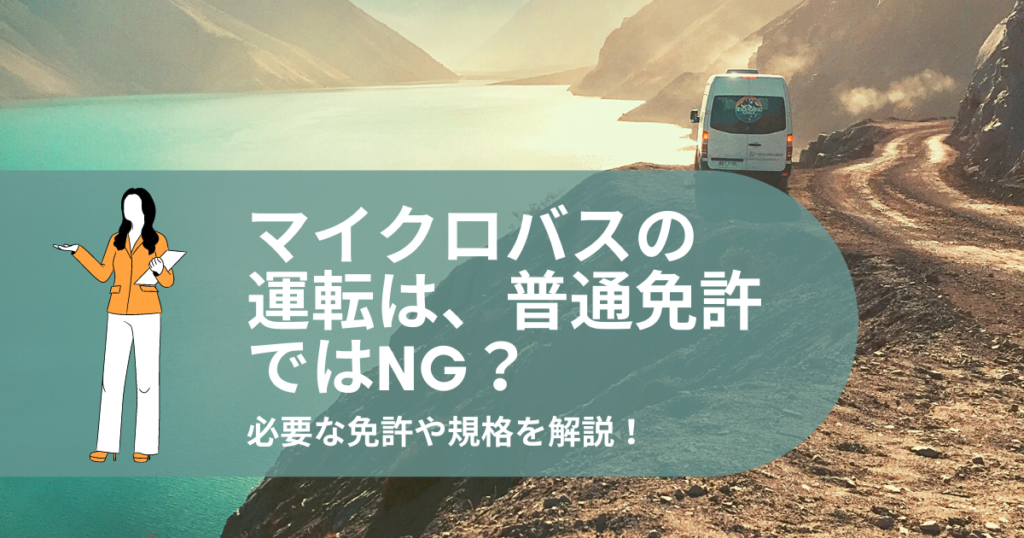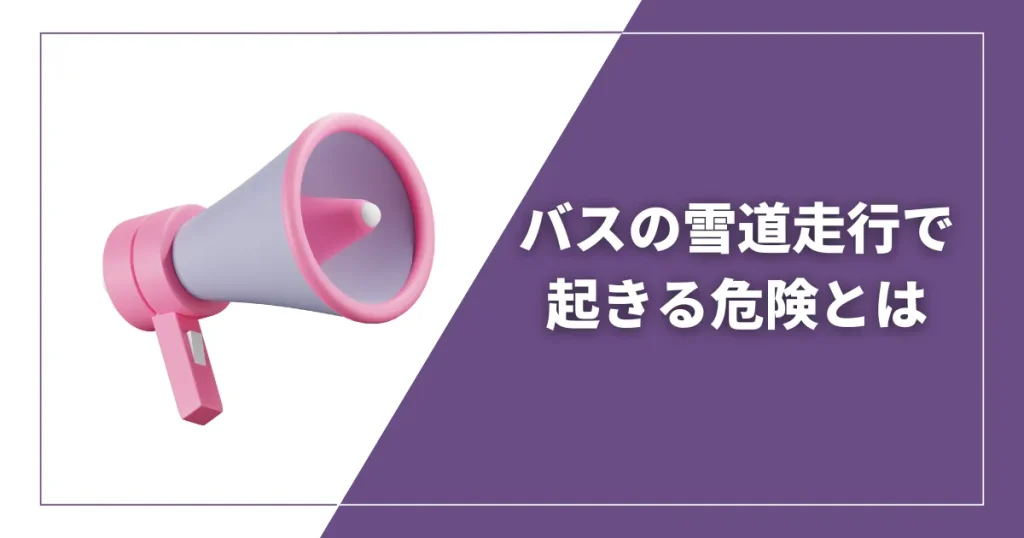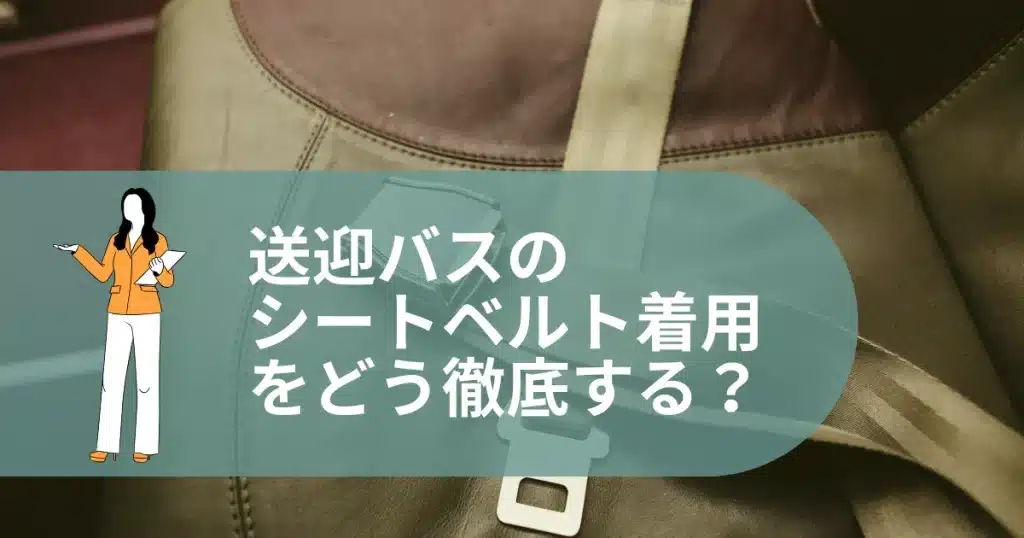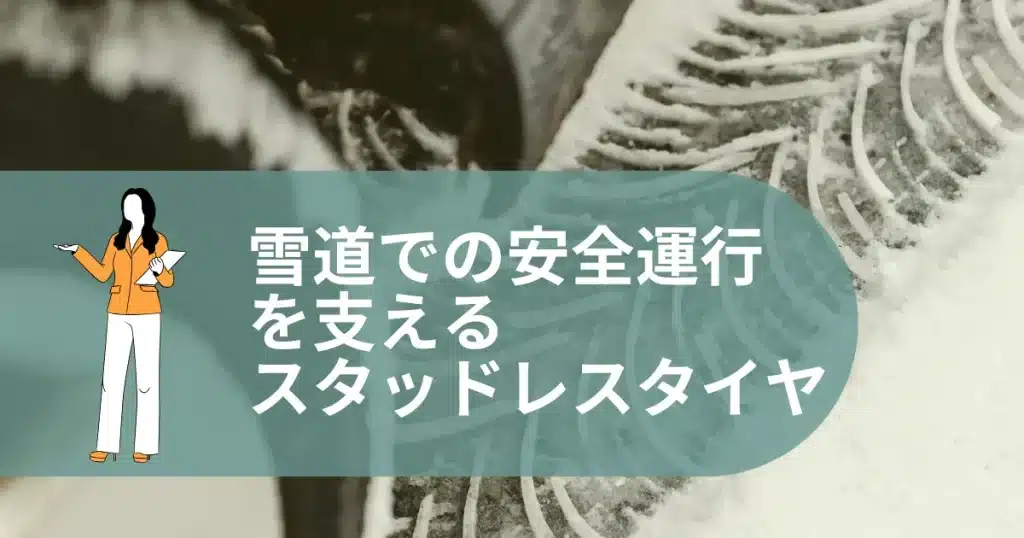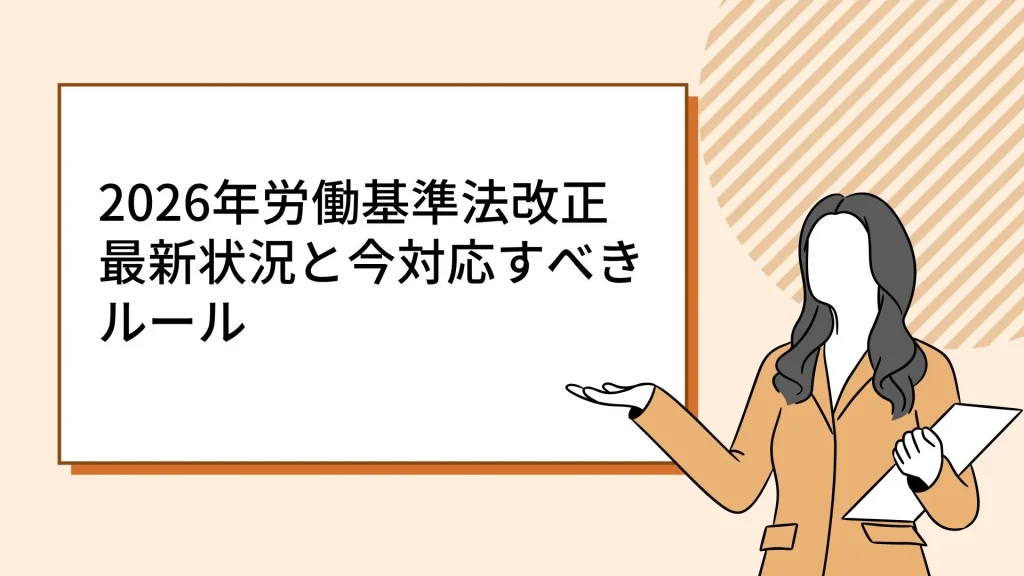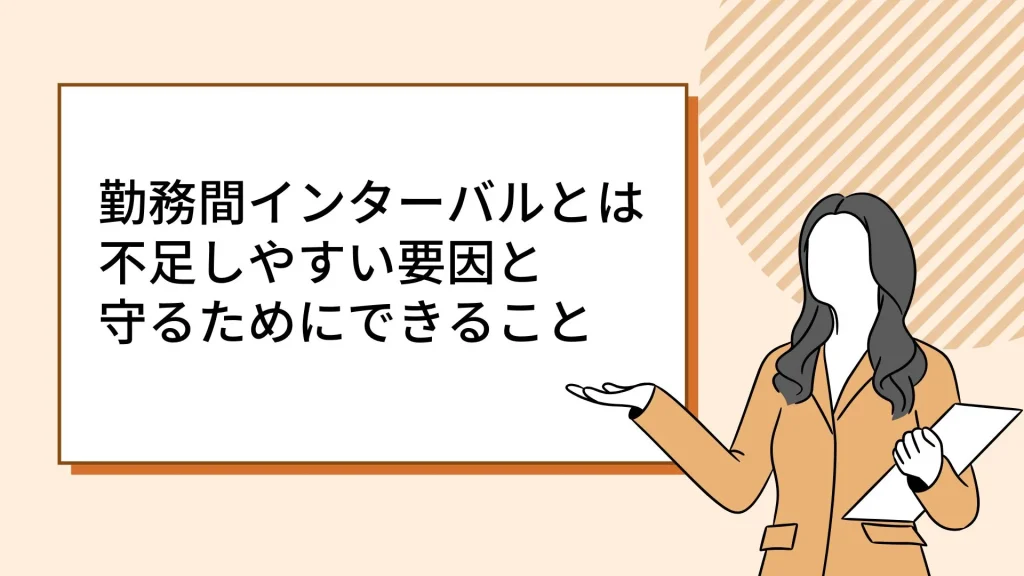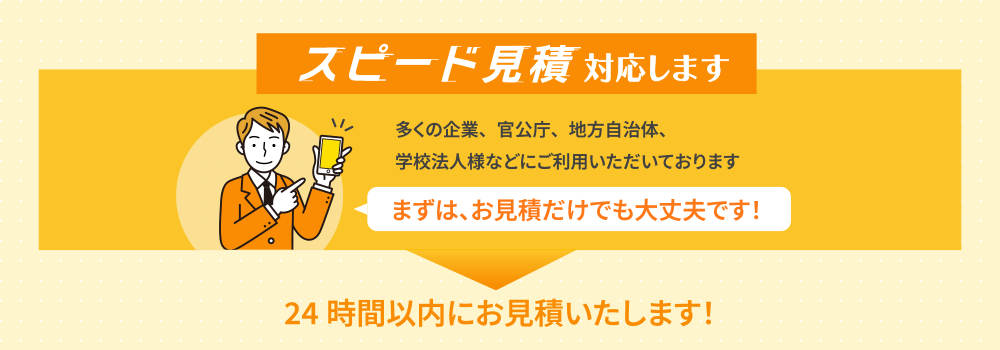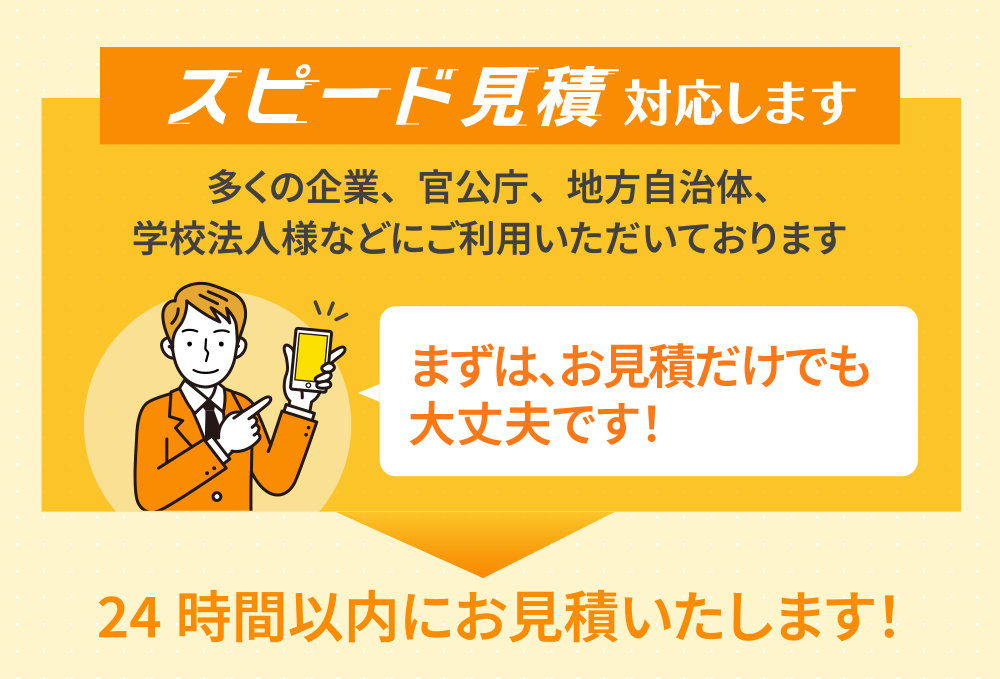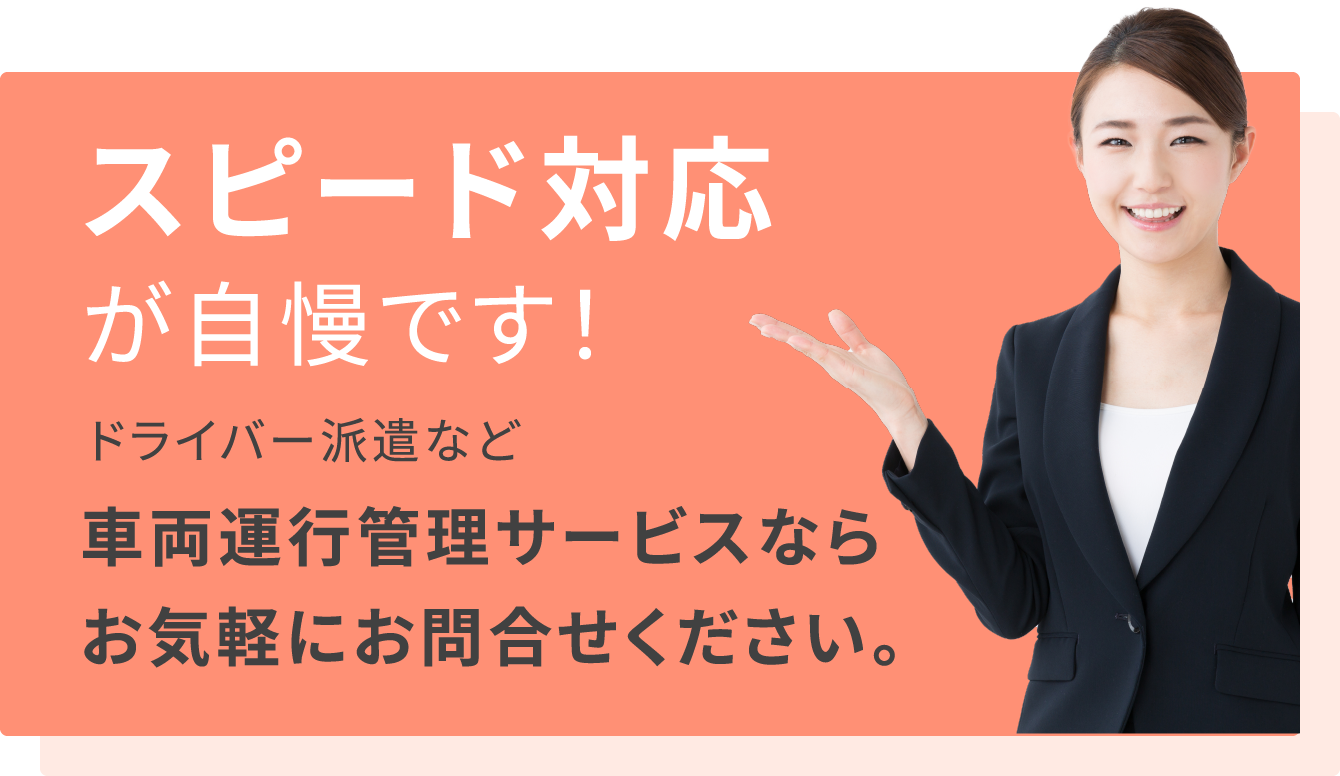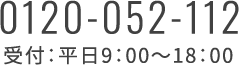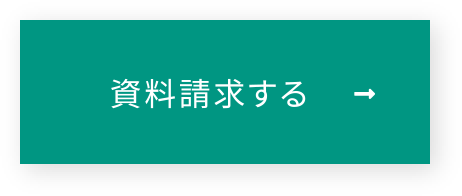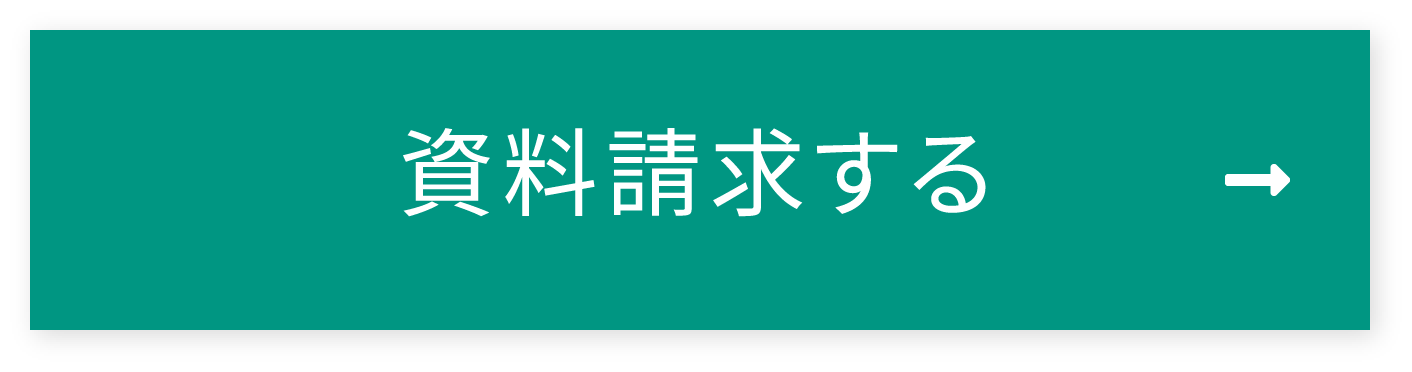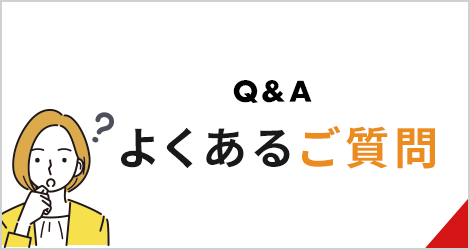2025.10.17
カテゴリ:法務/労務管理/規制
タグ:ノウハウ
二種免許の取得条件緩和はいつから?変更点と緩和される理由を解説「二種免許を取りたいけれど、年齢や経験が足りない」「せっかく業界に入っても、すぐにハンドルを握れない」。
こうした声は、これまで多くのタクシー・送迎業界の現場から聞かれてきました。従来、二種免許は21歳以上・運転経験3年以上が必要で、若年層にとっては高い壁となっていたのです。
しかし、二種免許の取得条件は段階を踏んで緩和されています。新たに導入された制度により、19歳・運転経験1年以上でも受験が可能となり、早期に現場で活躍できる道が開かれました。
この記事では、二種免許の取得条件がどのように緩和されたのかをわかりやすく解説。さらに、特例制度や教習時間の短縮など、改正で変わった具体的なポイントについても整理します。「これから二種免許を取りたい」「改正内容を正しく理解したい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
二種免許の取得条件緩和はいつから?
二種免許は、これまでに複数回取得条件が緩和されています。2022年の5月には受験資格が、2025年9月には教習内容が緩和されました。
従来の二種免許には「取得に年齢や経験の壁がある」「すぐに現場に出られないため採用しづらい」といった課題がありました。条件の緩和は、こうした課題に対応するためのものです。
この条件緩和により、より早い段階で二種免許を取得し、タクシーや送迎バスの運転に携われるようになります。特にドライバー不足が深刻な地域では、若年層の早期戦力化が期待されているのです。一方で、安全性への配慮から、特例制度の整備や教習内容の見直しも同時に進められています。
二種免許取得緩和後の変更点
二種免許取得緩和後の変更点は次の通りです。それぞれ、詳しく解説します。
- 受験資格特例制度の導入
- 教習時間・教習制度の見直し
受験資格特例制度の導入
受験資格特例制度は、2022年の法改正によって導入された制度で、年齢要件や運転経験年数のハードルが下げられました。
- 従来:21歳以上かつ運転経験3年以上
- 特例制度後:19歳以上かつ運転経験1年以上+特例教習修了
従来は高校卒業直後に業界入りしても、数年間は直接業務に関われない「空白期間」が発生していました。しかし、受験資格特例制度の導入により、若年層がより早く実務に就けるようになります。
ただし、安全性を確保するため、特例教習の受講と修了が必須です。公安委員会指定の教習所での履修が必要となり、すべての教習所が対応しているわけではありません。制度を活用する際は、対応教習所を確認してください。
教習時間・教習制度の見直し
2025年9月には、教習制度そのものも見直されました。主な変更は次の通りです。
- 学科教習:19時限 → 17時限
- 技能教習:21時限 → 12時限
- 総教習時間:40時限 → 29時限
- 最短教習期間:6日 → 3日程度
一種免許と二種免許の教習内容に重複が多かったことから、効率化し教習時間を短縮しました。ナビや運行支援システムの普及を前提に、一部の経路設定などは省略されます。
そのため、費用と時間の両面で二種免許の取得ハードルが下がるでしょう。ただし、教育内容の簡略化が安全性に与える影響については、今後の運用状況を注視する必要があります。
二種免許の取得条件が緩和される理由
二種免許の取得条件が緩和されるのには、次のような理由があります。それぞれ、詳しく解説します。
- 運転手不足の深刻化
- 業界の高齢化・若年層減少
- 制度設計上のミスマッチと空白期間
- サービス提供の維持・交通空白地の拡大防止
- 教習制度の重複・効率改善によるハードル引き下げ
運転手不足の深刻化
公共交通・旅客輸送業界では、慢性的な人手不足が続いています。
例えば、タクシー業界ではコロナ禍以降に運転手が2割以上減少しました。また、地方の路線バスは運休・廃止が相次いでいます。
高齢化により引退者は増加する一方、新規参入者が少ないのが現状です。こうした状況に対応するためには、制度面から若年層の参入を促進することが欠かせません。
特に地方では高齢者の移動手段が制限され、生活インフラとしての交通機能が維持できなくなる懸念もあります。運転手の確保は、単なる雇用の問題ではなく、地域社会全体の存続にも関わる重要課題といえるでしょう。
二種免許の取得緩和策はこの問題に対する根本的なアプローチとして位置づけられています。
業界の高齢化・若年層減少
旅客輸送業界における運転手の高齢化は深刻です。バス業界では平均年齢が50代後半に達している事業者もあり、定年退職の増加が今後さらに加速する見込みです。
一方で、若年層の新規参入は伸び悩んでいます。その要因のひとつが、取得条件の厳しさです。特に21歳・運転歴3年以上という要件は、高校卒業後すぐの就職希望者にとって大きな障壁でした。
この制度のままでは、若年層が実際に二種免許を活かせるのは20代中盤以降となり、それまでの数年間は現場での実務が制限されます。結果として業界からの離脱や他業種への転職が起こりやすく、構造的に若手が定着しにくい環境となっていました。
緩和制度はこうしたサイクルを断ち切るための方策であり、人材の持続的な循環を生み出すことが期待されています。
制度設計上のミスマッチと空白期間
これまでの制度設計では「働きたい若年層」と「免許がなければ実務を任せられない現場」の間に、明確なギャップが存在していました。
高校卒業後に旅客業界へ就職したとしても、二種免許を取得できるまでの約2年間は直接的な運転業務に従事できません。その間は清掃、配車、事務補助といった間接業務に回されることが多く、モチベーション維持が困難でした。
結果として「業界に入ったが仕事が面白くない」「実際に運転できる頃には辞めてしまう」といったミスマッチが頻発していました。制度改正は、こうした空白期間を解消し、本人のやる気と現場の人手不足をマッチングさせるための政策的調整でもあります。
特例教習を条件に緩和されることで、最低限の教育を担保しつつ、即戦力としての実務参加が可能になります。
サービス提供の維持・交通空白地の拡大防止
地方都市や山間部を中心に「交通空白地」の拡大が深刻化しています。交通空白地では高齢者の移動手段が失われており、生活・医療・買い物などあらゆる面での支障につながります。
路線バスやコミュニティバスの運行本数は減少傾向にあり、乗合タクシーやオンデマンド交通に頼らざるを得ない地域も増えています。しかし、これらのサービスも運転手不足により維持が困難となってきました。
免許制度の緩和は、こうした地域社会の持続可能性を高める視点からも推進されています。単なる雇用政策ではなく、地域交通インフラの維持という観点から、政策的な意義は大きいといえるでしょう。
特に観光地や福祉施設など、送迎ニーズが高い地域では、若手運転手の確保が事業継続のために重要です。
教習制度の重複・効率改善によるハードル引き下げ
従来の教習制度では、一種免許取得時と二種免許取得時で学習内容に重複が多く見られました。たとえば経路設定や標識知識など、一度学んだ内容を再び履修する必要があり、時間と費用の面で負担が大きかったのです。
こうした制度的な冗長性が、免許取得意欲を削ぎ、結果として人材確保の妨げとなっていました。今回の見直しでは、重複項目を省略し、合理化されたカリキュラムが導入されています。
さらに、教習時間の短縮により、仕事をしながらでも取得を目指しやすくなります。これは、副業や転職を視野に入れた社会人層にも有効なアプローチです。
制度緩和と教育内容の合理化が両輪で進むことで、「時間・費用・労力」という三大ハードルを下げ、より多くの人が取得に踏み出せるようになると期待されています。
二種免許取得条件の緩和でドライバー不足の解消へ
二種免許の取得条件緩和は、業界全体の構造改革と人材確保の両面から進められた制度改正です。若年層の参入を促し、地域交通の持続性を高めることが目的です。
制度の緩和に伴い、これまで取得を見送っていた人材が新たに参入できる環境が整いつつあります。教習制度の簡素化と特例制度の導入により、二種免許取得のチャンスが広がりました。
今回の改正がドライバー不足解決への一歩となることが期待されています。