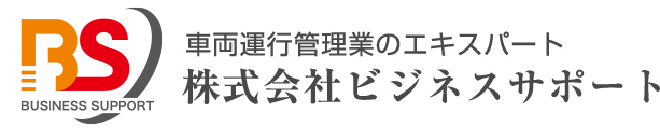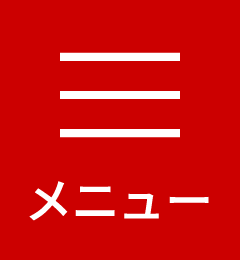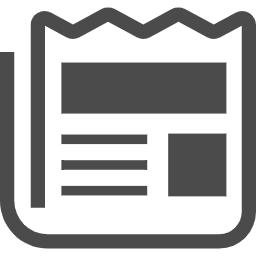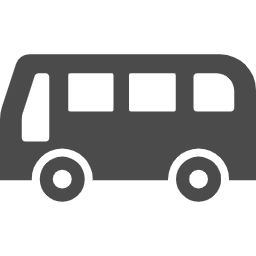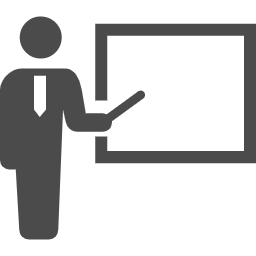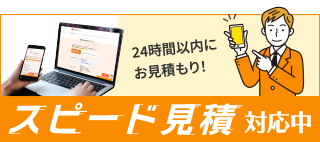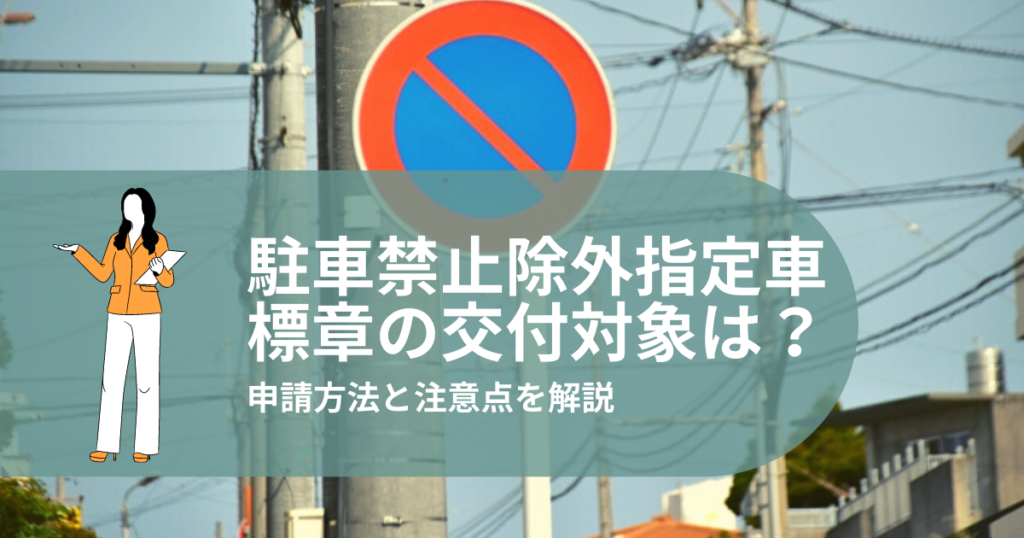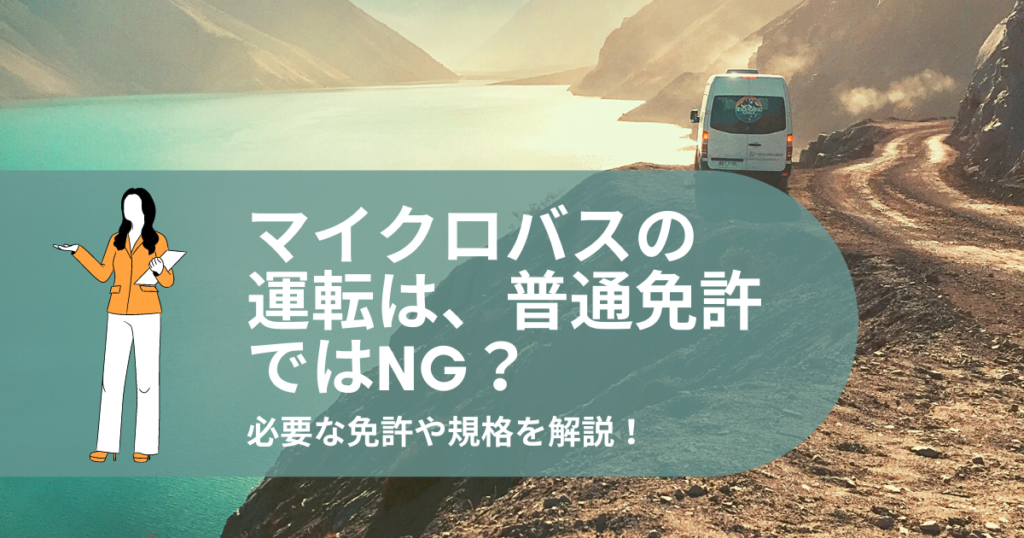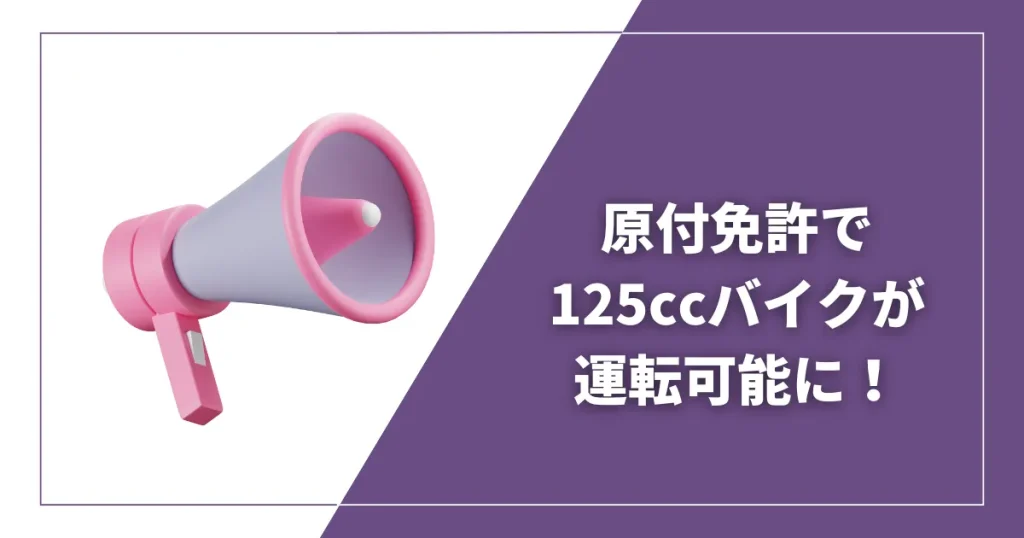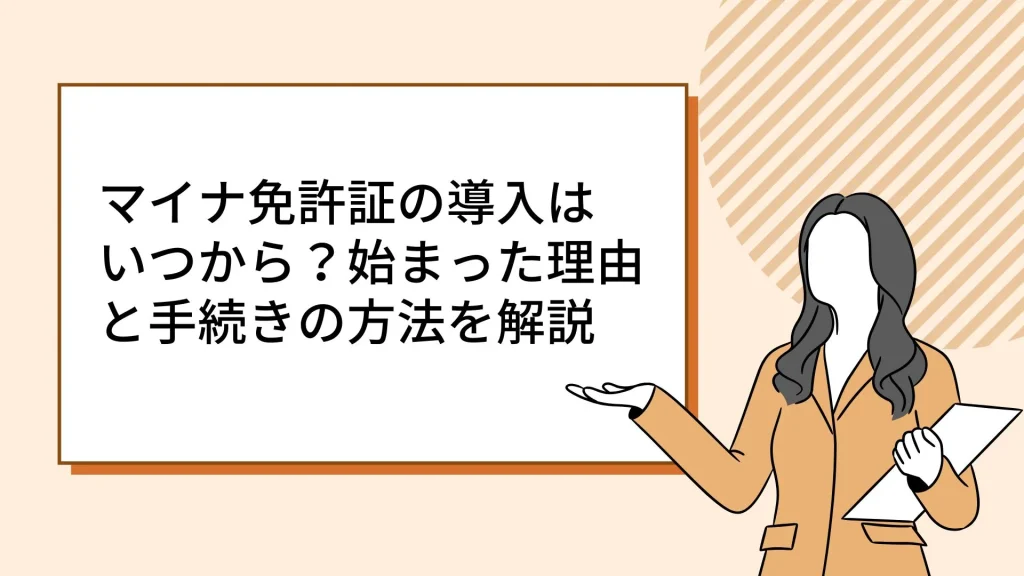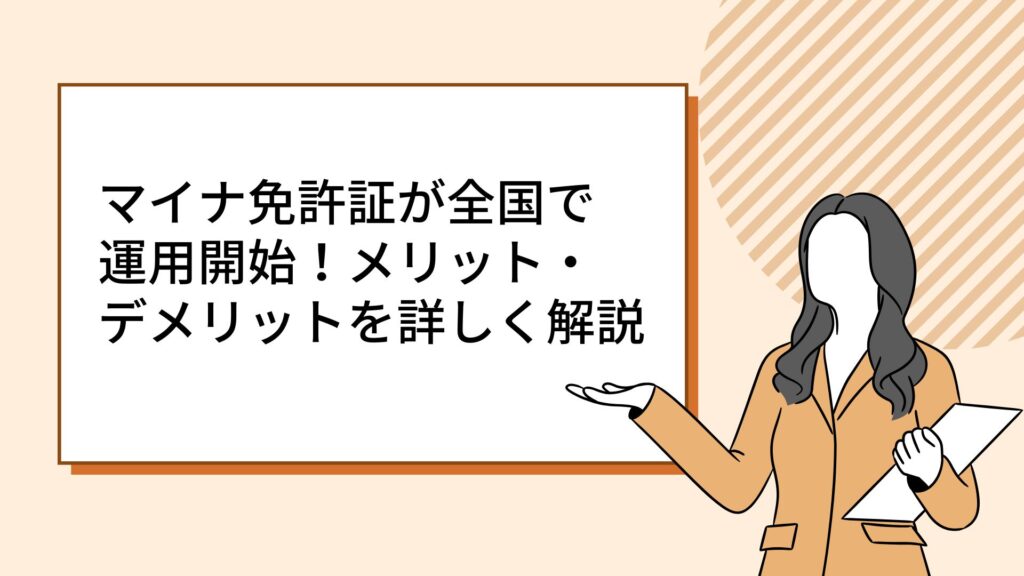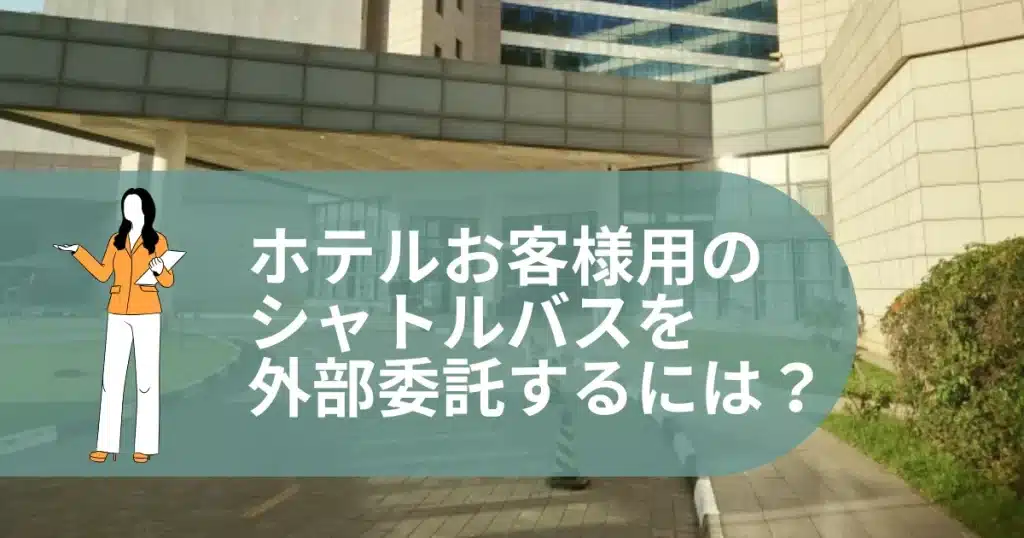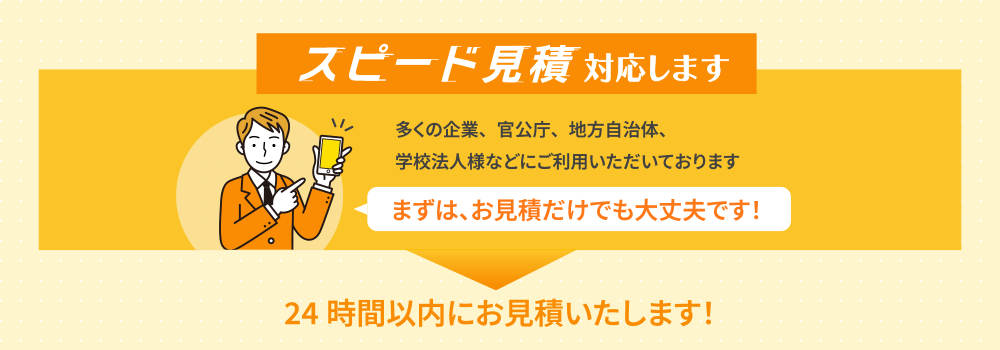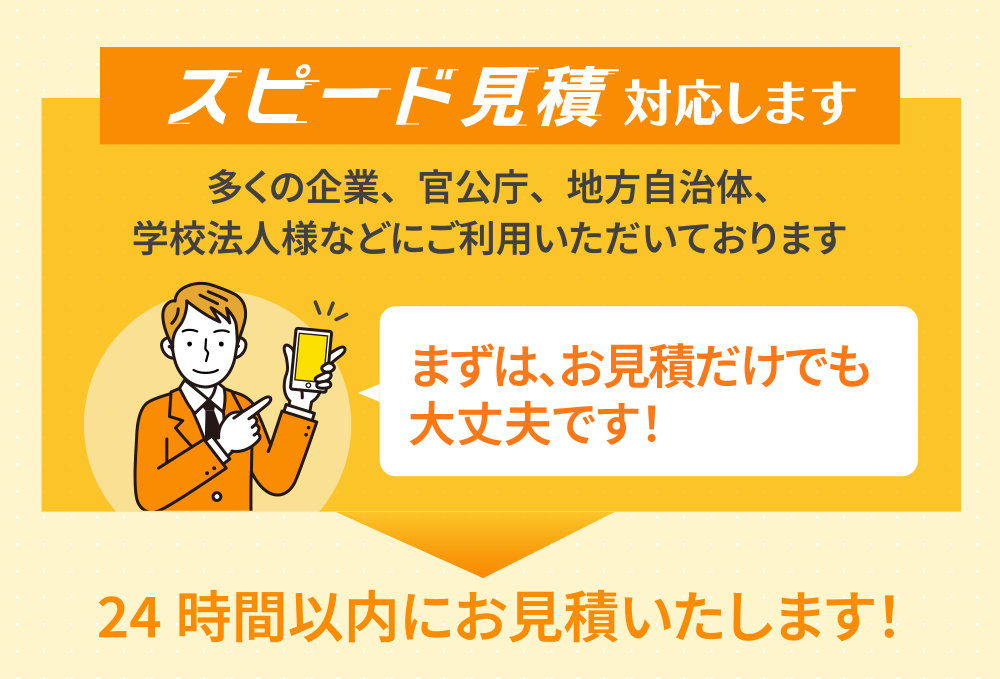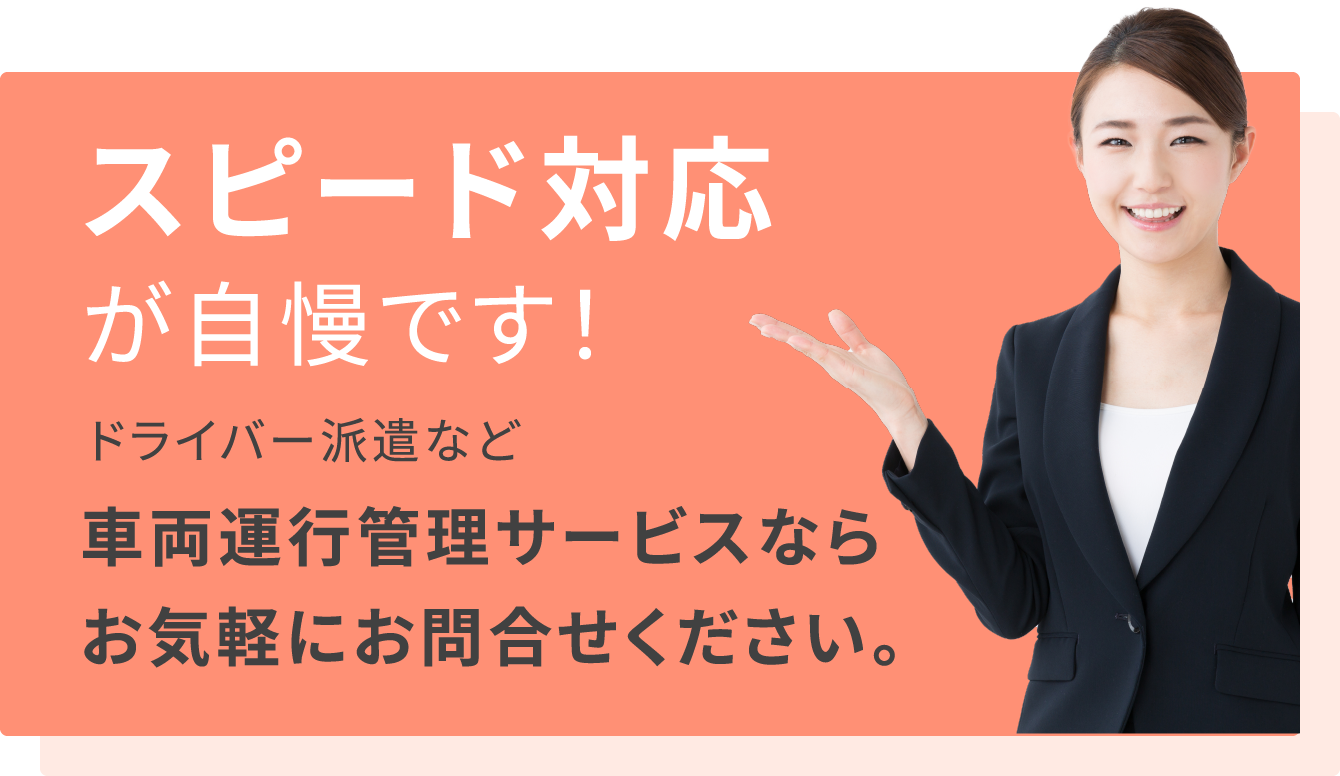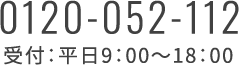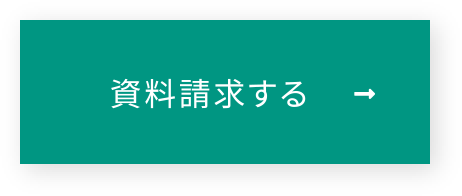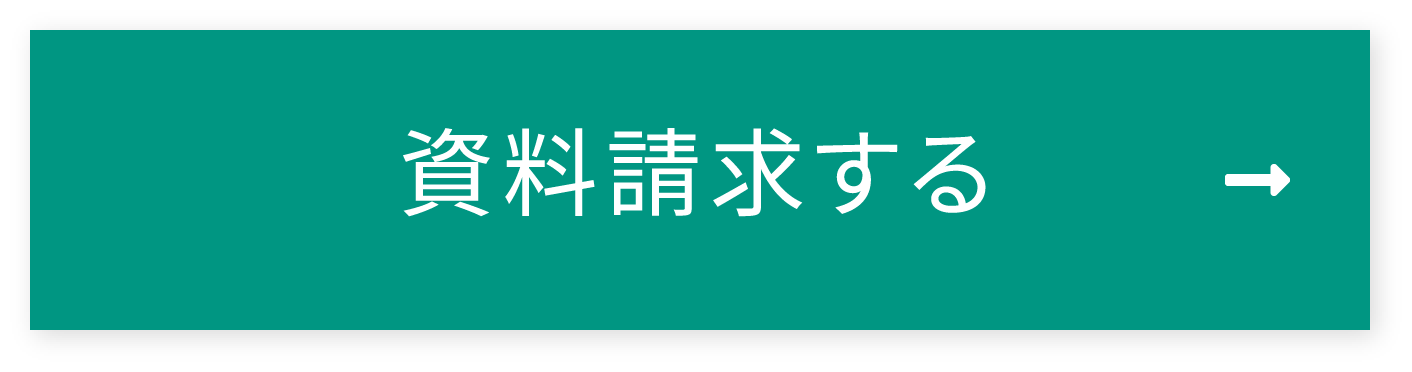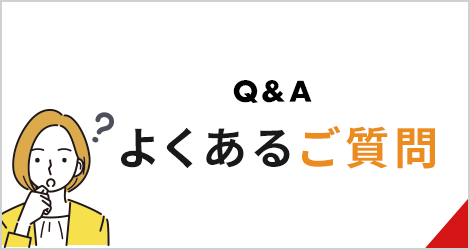2023.01.20
カテゴリ:運行管理
タグ:事故対応
社用車の事故で事業者が負うべき負担とは?賠償責任と修理代について解説送迎車や運搬車など、業務の際に車が欠かせないという事業者も多いでしょう。車を利用する場合、交通事故のリスクについても考えておかなければなりません。
しかし、実際に社用車での交通事故が発生したとき、事業者がどんな負担や責任を負わなければならないのか具体的にはよく知らないというご担当者様も多いかと思います。
社用車で交通事故を起こした場合、従業員だけではなく事業者にも責任が発生します。
今回は、社用車の交通事故における事業者の負担と責任について解説します。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
社用車で交通事故を起こした時に事業者が負担する責任の種類
従業員が社用車で交通事故を起こした場合、事故を起こした当人だけでなく事業者にも責任が発生します。事業者が負うべき責任は次の2種類です。
- 1.使用者責任
- 2.運行供用者責任
それぞれ、詳しく解説します。
1.使用者責任
使用者責任とは、業務にあたって従業員が他人に損害を与えた場合に、従業員だけでなく事業者もその責任を負うという法律の制度のことです。
使用者等の責任 第715条
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
引用:民法|e-Gov法令検索
事業者は従業員の活動によって売上・利益を得ているため、活動による損失についても責任を負うべきだとの考え方から生まれました。交通事故を含む業務上の事故だけでなく、社内での暴力やセクハラなどの場合にも使用者責任が問題になることがあります。
この使用者責任は、「業務中に他人に損害を与えたこと」が問題となるため、業務中に自家用車で事故を起こした場合も責任の対象です。また、使用者責任は人身事故と物損事故、どちらの場合でも発生します。
2.運行供用者責任
交通事故の場合、事故を起こした当人だけでなく、運行供用者にも責任が発生します。運行供用者とは、一般的に車の所有者が運行供用者となります。
自動車損害賠償責任 第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用:自動車損害賠償保障法|e-Gov法令検索
社用車の場合には事業者が運行供用者となるため、交通事故時は運行供用者責任を負わなければなりません。運行供用者責任は、人身事故の場合のみ発生します。
従業員の負う責任は、不法行為による損害賠償のみ
社用車での交通事故では、従業員は不法行為による損害賠償の責任を負います。
社用車で事故を起こした場合、基本的には事業者が使用者責任と運行供用者責任を負いますが、実際に運転していたのは従業員ですから、道路交通法の罰則は従業員自身が負わなければなりません。罰則を受けたり、罰金を支払ったりするのは従業員です。
ただし、業務外に社用車で事故を起こした場合には、事業者が従業員に損害賠償を請求できる可能性もあります。
交通事故が起きた状況による事業者の責任の違い
社用車で交通事故を起こしてしまった場合、業務中の事故か、業務外の事故かによって事業者が負うべき責任は異なります。
業務中の場合
交通事故が業務中に発生した場合、事業者には使用者責任と運行供用者責任の両方が発生します。営業先への移動中など業務の範囲内で車両を使用した場合だけでなく、通勤など、業務のために必要があって車両を使用している場合も業務中とみなされます。
業務外の場合
業務外の社用車による交通事故では、事業者には運転供用者責任のみ発生します。使用者責任とは、業務中の従業員に対して発生する責任であるため、業務外の場合は発生しません。
しかし、業務外であっても事業者が車両の運行供用者であることに変わりはないため、業務外の交通事故でも運行供用者責任を伴います。
社用車事故の賠償責任の割合
社用車による交通事故で事業者に責任が発生する場合、賠償責任は事業者と実際に車を運転していた従業員の連帯責任となります。賠償責任の割合はどちらも100%で、法律用語ではこれを「不真正連帯債務」と呼びます。
両方に賠償責任が発生するため、被害者は従業員と事業者のどちらにも賠償請求が可能です。多くの場合、支払い能力がある可能性が高い事業者への損害賠償請求が行われます。
事業者が賠償金を支払った場合、その一部を従業員に請求することが可能です。これを、求償権と呼びます。
一方、従業員が賠償金を支払った場合に一部を事業者に請求することについては「逆求償」と呼ばれ、従来その権利は認められないと考えられていました。本来は事故を起こした当人が賠償金を支払うべきであり、事業者に賠償金を請求できるのは被害者保護が目的であると考えられていたためです。
しかし、2020年2月には、最高裁判所で逆求償を認める判決が下されています。被害者が誰に賠償請求をするかによって、賠償金の負担割合が変わるのは公平ではないというのが、逆求償が認められた理由です。
そのため今後は、従業員が事業者に賠償金の一部を請求する逆求償についても認められると考えておいた方が良いでしょう。
交通事故を起こした社用車の修理費の負担
交通事故を起こした社用車の修理費は、事業者が負担するケースが多いようです。労働基準法第16条では「賠償予定の禁止」が定められており、事前に違約金や損害賠償額を予定する契約をしてはならないと決まっているためです。
賠償予定の禁止 第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
しかし、従業員に損害賠償を請求することや、修理費を負担させることを絶対に禁止しているわけではありません。そのため、同じ従業員が何度も事故を繰り返し、そのたびに修理費が発生している場合や、運転中のスマホ使用による脇見運転のように重大な過失がある場合、無許可で社用車を利用していたなどの場合には、修理費を請求するケースもあります。
社用車による交通事故の負担に関する注意点
社用車による交通事故の負担に関して、注意が必要なポイントを3つ紹介します。
- 全額を従業員に請求するのは難しい
- 雇用契約書などで賠償金や修理費の負担を約束させてはいけない
- 就業規則に記載されていないペナルティは与えてはならない
賠償額や修理費の全額を従業員に請求するのは難しい
前述の通り、社用車による交通事故の場合、実際に運転していた従業員と事業者のどちらにも責任があります。そのため、賠償額や修理費のうち、従業員に請求できるのは一部のみです。全額を請求するのは難しいと考えておきましょう。
雇用契約書などで賠償金や修理費の負担を約束させてはいけない
万が一の事故に備えて、事前に雇用契約などで、賠償金や修理費の負担金額について定めておけば良いと考える方もいるでしょう。しかし、賠償金や修理費の支払いを事前に決めておくことは法律で禁止されています。これを、「賠償予定の禁止」といいます。事前に決まりを作る場合には、賠償金や修理費を請求する「場合がある」といった表現であれば可能です。
就業規則に記載されていないペナルティは与えてはならない
事業者は、就業規則に記載されていないペナルティを従業員に与えてはいけません。
従業員が交通事故を起こしたときに、厳重注意や降格、減給などの処分を検討することもあるでしょう。しかし、就業規則でこうした処分を行う可能性があることを事前に示していなければ、ペナルティを与えることはできないため注意しましょう。
また、降格や減給処分については、労働基準法にも定めがあります。ペナルティを与える際には、就業規則や法律違反にならないか、事前に十分確認してください。
従業員の負担を軽減するなら、送迎のアウトソーシングも検討する
送迎が必要な施設などでは、従業員が通常の業務に加えて送迎業務を行う場合もあります。しかし、本来施設内の仕事をメインとしているスタッフにとって、送迎業務は負担となってしまうこともあるでしょう。
事故は一瞬の不注意から発生するものです。従業員の交通事故を防ぐためにも、送迎業務をアウトソーシングすることも検討してみてください。
送迎業務をアウトソーシングすれば、これまでドライバー業務を担ってきた従業員の負担を減らすことができます。また、万が一委託会社が業務中に事故を発生させてしまった場合にも、管理請負自動車保険が適用され自分たちで事故処理を負担する必要はありません。
事故のことを考えず本来の業務に集中できるだけでも、送迎業務をアウトソーシングするメリットは大きいといえます。
もし、委託会社が事故を起こしてしまったら?
委託会社が事故を起こしてしまった場合、当日その場での対応からその後必要な処理まで、委託会社が行います。損害賠償を支払うのも代行業者です。
また、事故によってドライバーの負傷や車両の破損が発生した場合、その後の輸送手段に困ってしまうこともあるでしょう。外部委託の場合には、委託業者が代理のドライバーや輸送手段を用意します。万が一事故があっても、翌日以降の営業を心配する必要なありません。
まとめ◆社用車での交通事故では事業者にも負担が発生する
社用車で交通事故を起こした場合、実際に運転していた従業員だけでなく、事業者にも損害賠償などの責任が発生します。そのため被害者は、事業者と従業員、どちらにも損害賠償を請求可能です。
修理費は、特別な事情が無い限り事業者が負担することが多い傾向があります。
送迎業務をアウトソーシングした場合、事故の対応は委託業者が行います。事業者が事故処理の心配をする必要はありません。
この記事を参考に、ぜひ一度万が一の事故についても考えてみてください。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。