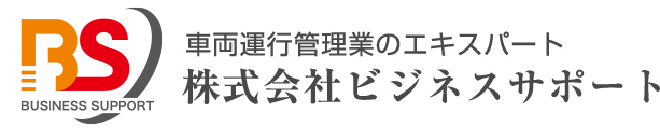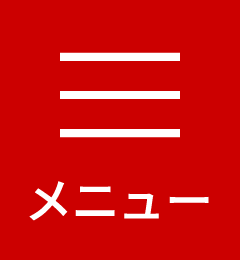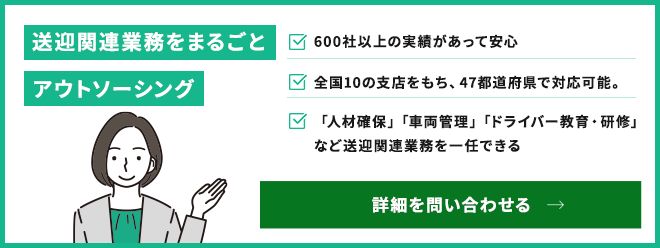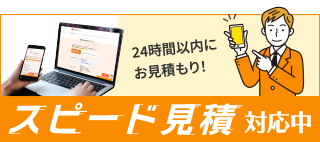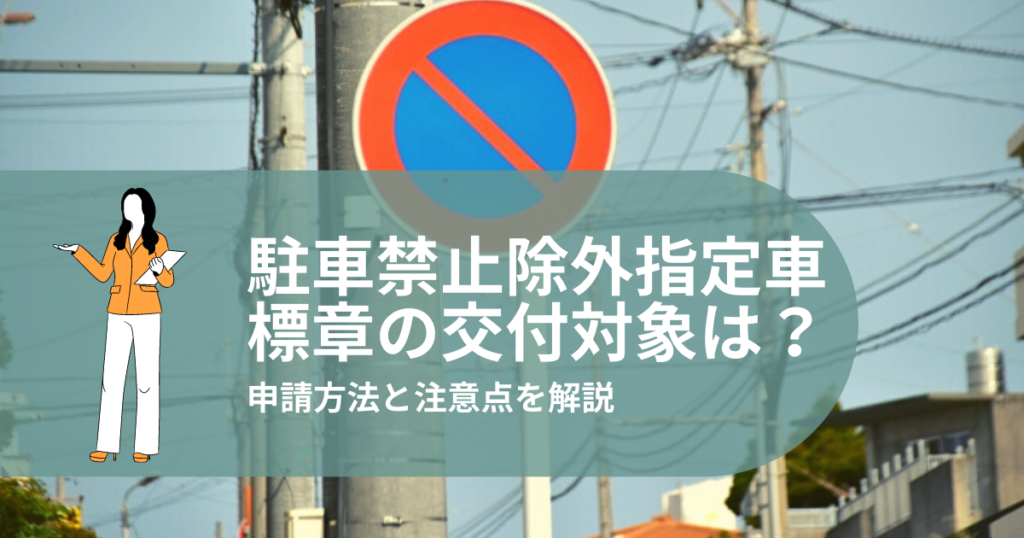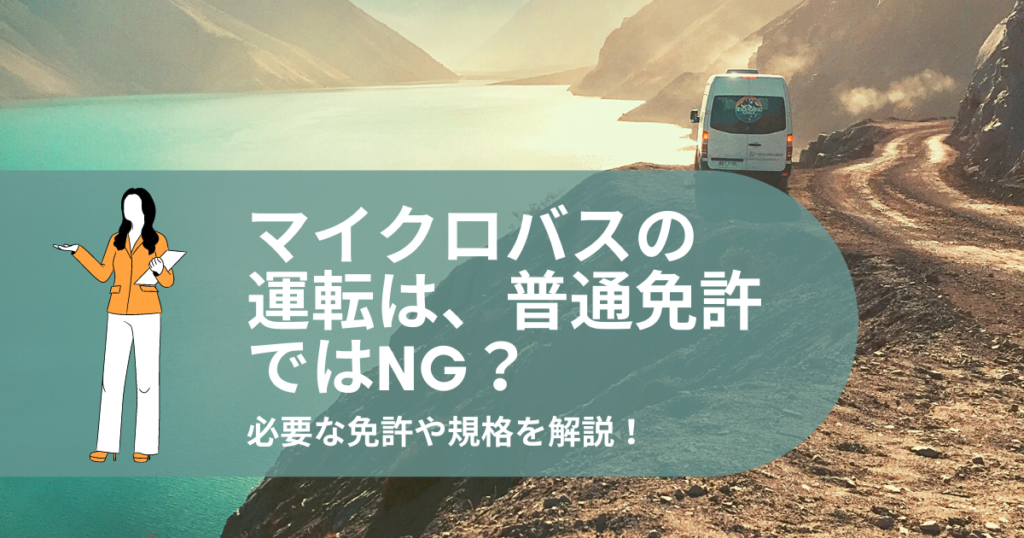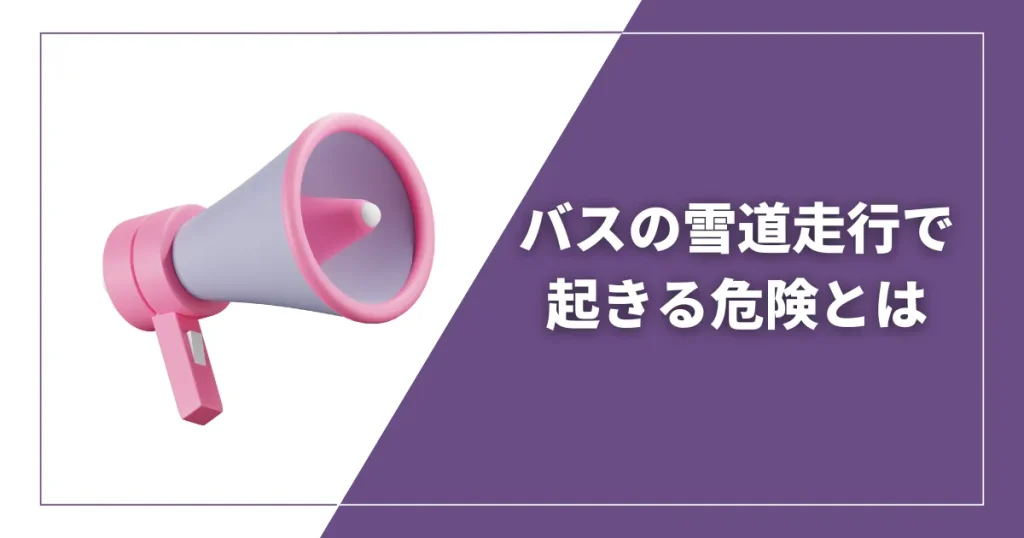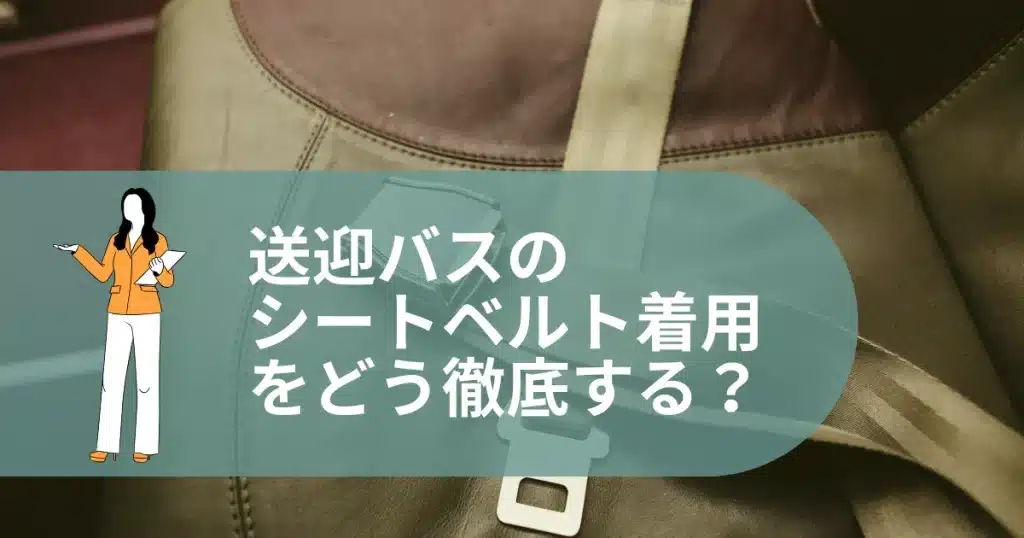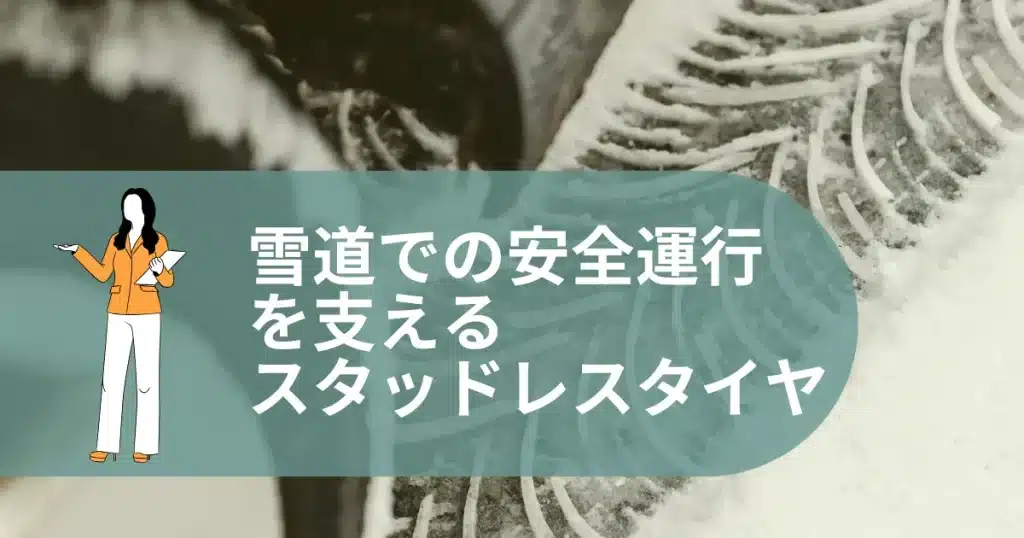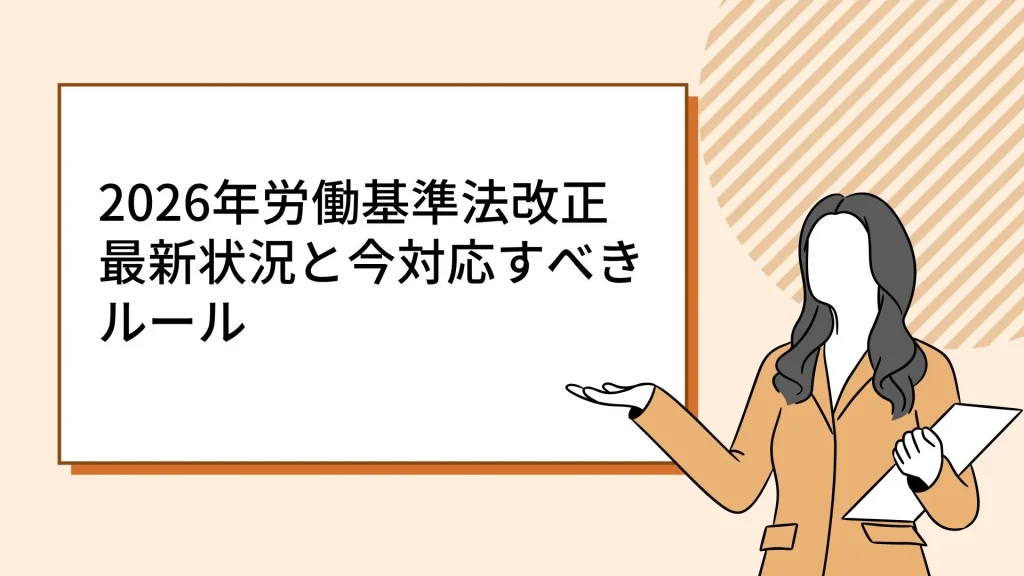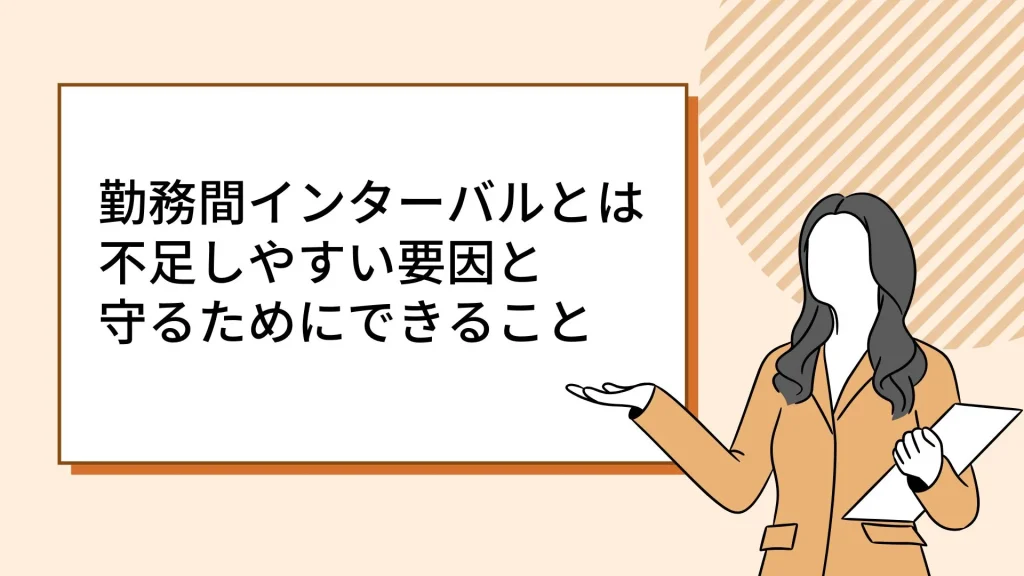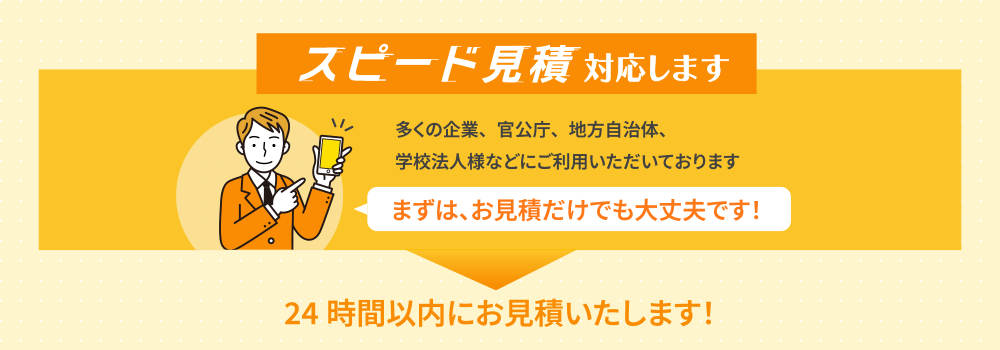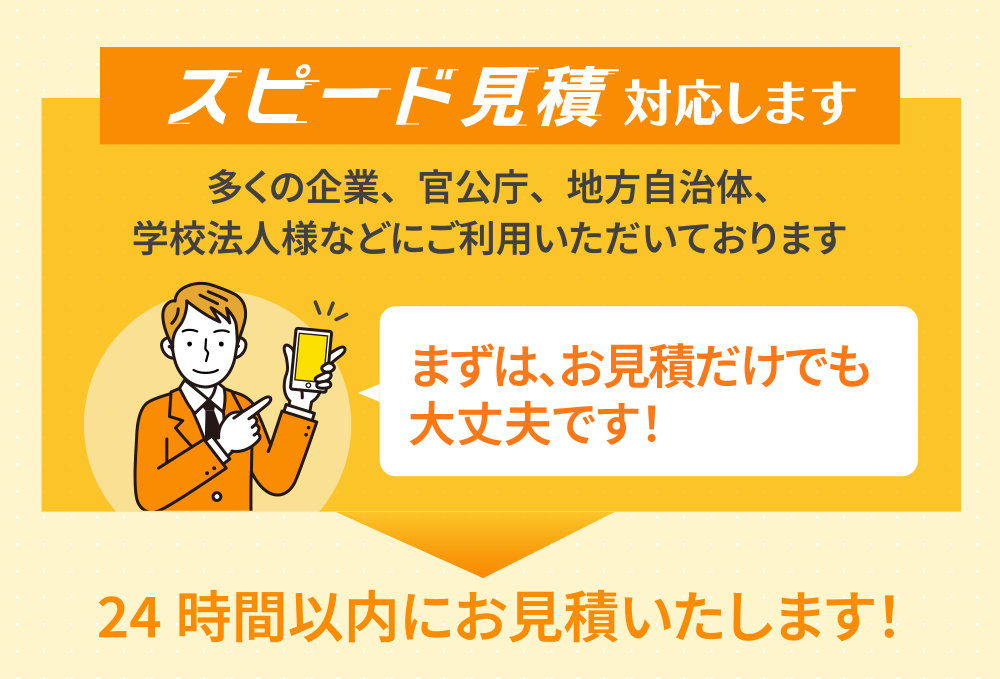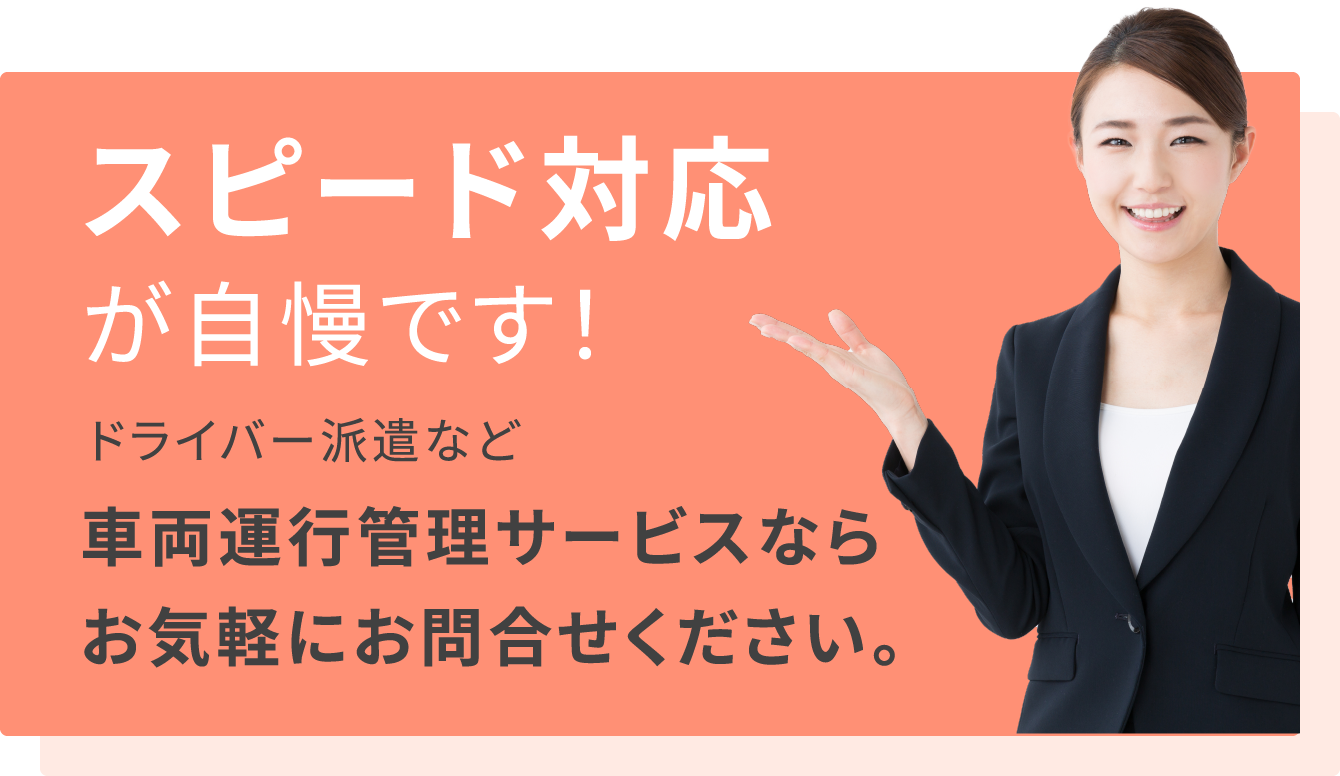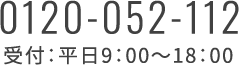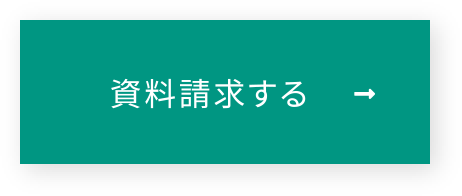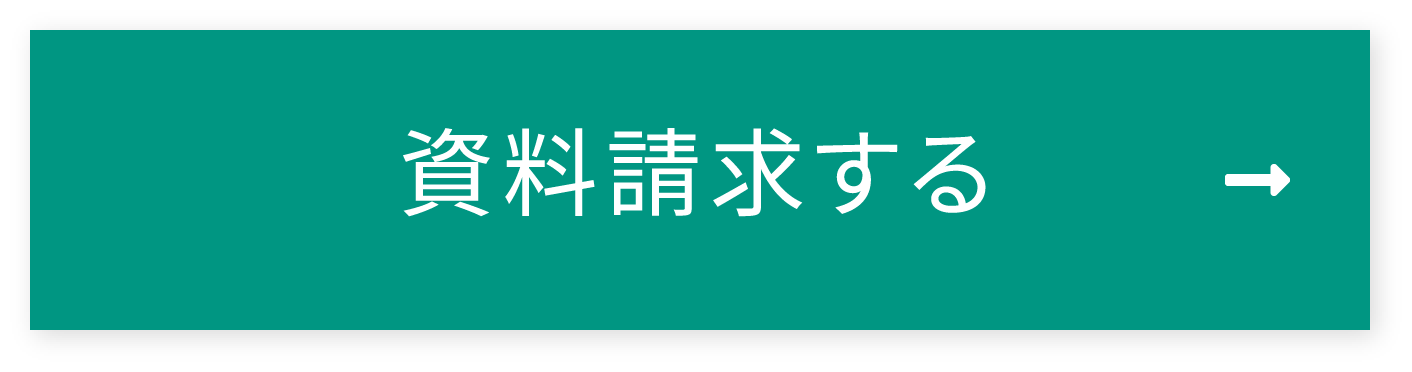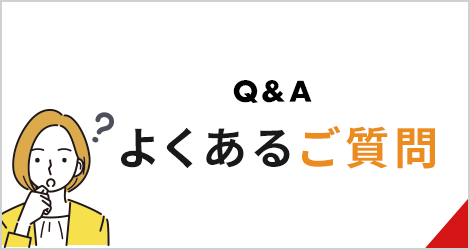2025.04.13
カテゴリ:自動車運行管理DX
タグ:デジタルシステム
送迎マニュアル作成の目的やデジタル化に向けた企業の取り組みを解説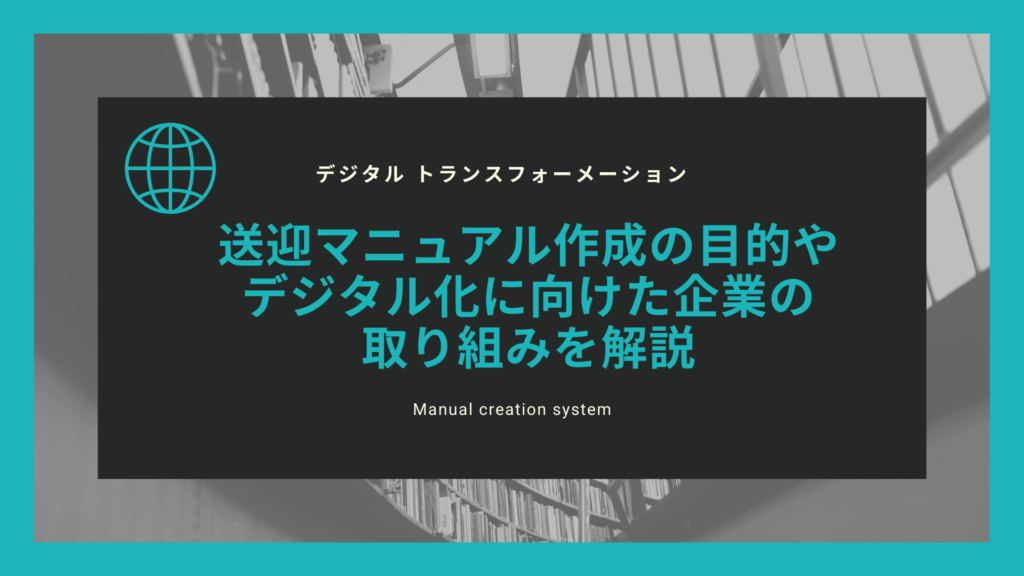
送迎代行業務において、福祉車両や送迎バスなどは普通車と異なる操作を行います。そのため、正しい操作方法やルールをマニュアルで全員に共有することが必要です。安心安全に送迎代行業務を行うためには、万が一の事故や緊急時の対応の把握も必要になります。
本記事では、送迎マニュアル作成の目的や記載すべき内容、マニュアル作成の方法などをご紹介します。送迎業務のマニュアル作成でお悩みの方はぜひ、ご覧ください。
送迎マニュアルを作成する目的とは
送迎マニュアルとは、出退勤の方法や車両の扱い方、自動車の運転を行う際のルール、乗降時の注意事項、緊急時における対応方法などを定めたものです。マニュアルを見れば正しいルールや手順がわかる状態にすることで、全てのドライバーが共通のルールを理解でき事故防止にも繋がります。送迎マニュアルを作成する目的は、大きく4つあります。
- 1.送迎業務に関するルールの明確化
- 2.定期的な車両点検の方法の周知
- 3.事故時の対応方法の把握
- 4.緊急時(体調不良など)の対応の把握
1.送迎業務に関するルールの明確化
介護施設で使われる福祉車両など普段操作をしたことない車両を取り扱う場合、リフトや乗降用のステップなど初めて行う操作がたくさんあります。福祉車両に慣れていないと、ご利用者様に注意が集中してしまい車両の安全確認が疎かになる可能性があります。車両の操作方法、シートベルトの着用、乗降介助の方法などをマニュアルで事前に確認しておくことで、福祉車両の送迎経験がない方でも安心して業務に取り組むことができます。
2.定期的な車両点検の方法の周知
現在の法律では、「日常点検として適切な時に運転者に点検する」ことが定められています。以前と違い、1日1回車両の運転前点検の義務は緩和されていますが、安全な送迎業務のため運転前点検と終業後点検の計2回行っています。車両点検の方法やチェック項目も、マニュアルがないと個人により判断が異なってしまいます。正しい車両点検には、マニュアルを作成し全員が共通した内容の点検を定期的に行うことが重要です。
3.事故時の対応方法の把握
送迎業務でのトラブルとして、交通事故が一番懸念されます。マニュアルには、事故が発生した際の対応方法を明記しておく必要があります。万が一、事故が発生してしまった場合でもパニックを起こさずに初期対応を行えるようにするためです。ドライバーがパニックになれば、乗っているご利用者様も不安になり混乱してしまいます。事故発生時は、二次災害を防ぐため迅速な対応が求められます。事故発生時の対応方法をマニュアル化することで、やるべき行動が明確になりスムーズな事故対応を行うことができます。
4.緊急時(体調不良など)の対応の把握
介護施設内や保育園であれば、体調不良などの緊急時に対応できる人が複数人いますが、送迎中はドライバーのみです。ドライバーが、その場で状況を判断する必要があります。救急車を呼ぶ場合の条件や、異変が起きた際の対応などを明確にしておきましょう。嘔吐した場合なども想定し、感染症対策に関しての手順や方法もマニュアル化しておくと安心です。
送迎マニュアルに記載すべき内容
具体的に送迎マニュアルへ記載すべき内容は、以下の通りです。
- 車両の操作方法と装備の使い方
- 送迎ルートと運行計画
- 乗降介助と安全確認
- 走行中のルールと声かけ
- 事故・緊急時の初期対応と連絡手順
- 記録の残し方と報告書の作成方法
車両の操作方法と装備の使い方
送迎マニュアルには、使用する車両ごとの基本的な操作方法を明確に記載しましょう。特に福祉車両には、リフト、ステップ、手すりの操作など一般車とは異なる装備があるため、初めて使う人でも戸惑わずに扱えるよう、写真やイラスト付きで手順を示すことが重要です。
また、エンジンの始動や停止、サイドブレーキ、ウィンカーやランプの位置など、車種によって異なる細かい部分もあらかじめ把握しておくことで操作ミスを防げます。加えて、シートベルトの締め方やチャイルドシート・車いす固定装置の取り付け方法など、安全に直結する装備は必ず図解付きで掲載しましょう。
送迎ルートと運行計画
効率的かつ安全な送迎を行うには、事前に最適な送迎ルートと運行スケジュールを設計し、それをマニュアル内で共有することが大切です。例えば、通行量の多い時間帯や道路の混雑状況、迂回路の有無、天候時の代替ルートなども盛り込むと、予期せぬトラブルへの備えになります。
また、施設ごとに決まった停車場所や、乗車・降車の際の順番、送迎対象者の個別ニーズも併せて記載すると、運転手が現場で迷わず対応できるはずです。
乗降介助と安全確認
乗降介助においては、利用者の安全を確保するための注意点を細かくマニュアル化することが不可欠です。高齢者や子ども、身体的ハンディキャップを持つ方など、対象によって介助の方法は異なります。
例えば、車いすの方を対象とする場合にはスロープやリフトの操作、体の支え方を、子どもを対象とする場合には声かけや手の引き方などを明記します。
また、全乗客の乗車後・降車後に人数確認を行うルールも必須です。視認・呼名・リストによるチェックなど、確認方法を具体的に記載することで、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
走行中のルールと声かけ
運転中のルールには、安全運転だけでなく利用者の安心感を支えるコミュニケーションも含まれます。法定速度の遵守や急ブレーキの回避といった基本に加えて、利用者に対する「カーブに入ります」「あと5分で到着します」などの声かけは、安心感を生み出します。
特に認知機能が低下している方や不安を感じやすい方が利用する場合には、運転者の声かけが大きな安心材料となるでしょう。こうしたルールもマニュアルに明記し、全ドライバーが同じ対応を取れるよう統一を図ることが求められます。
事故・緊急時の初期対応と連絡手順
事故や体調不良などの緊急事態が発生した場合、適切な初動対応を取ることが被害拡大を防ぐ鍵になります。そのため、送迎マニュアルには緊急時の対応手順を明確に記載しておく必要があります。
例えば、事故発生時の初期対応、体調不良時の判断基準、救急車の要請基準、施設や保護者への連絡フローなどを、フローチャート形式で掲載するのも有効です。また、二次災害を防ぐための具体的な行動や通報時に伝えるべき情報のテンプレートを用意しておくと、慌てずに行動できます。
記録の残し方と報告書の作成方法
送迎中に発生したトラブルやヒヤリハット事例を記録に残すことは、再発防止のために欠かせません。マニュアルには、事故報告書や体調不良対応記録、点検チェックリストなど、必要な書類の記載方法や提出先、保管方法などを明記しておきましょう。
特に事故報告書については、記録すべき項目を例示しひな形をマニュアルに添付しておくとスムーズです。記録の習慣化は、送迎業務の透明性を高めるとともに、施設全体の安全意識の向上にもつながります。
ヒューマンエラー事故防止対策
ヒューマンエラー事故の防止対策と発生時の対応方法もマニュアルに記載するようにしましょう。具体的に記載すべき項目の例は次の通りです。それぞれ、詳しく解説します。
- 降車確認のチェックリスト運用
- Wチェック・点呼ルールの整備
- 置き去り防止装置やAIカメラとの連携
降車確認のチェックリスト運用
送迎後の「降ろし忘れ」は、最も重大なヒューマンエラーです。これを防ぐには、乗客が全員降車したことを確認するためのチェックリストの導入が有効です。
例えば、降車時に個別にチェックを付ける用紙を用意し、最後の1人が降りた後には「後部座席の確認」を明記することで、確認漏れを物理的に防ぐ工夫ができます。施設によっては、車内をスマホで撮影し保存するなど、二重の確認を導入している例もあります。
こうした手順をマニュアル化し、チェックリストのフォーマットも併せて掲載することが重要です。
Wチェック・点呼ルールの整備
人の記憶や注意力だけに頼らず、確認作業に複数人の目を通す「Wチェック」はヒューマンエラー対策の基本です。運転者が降車後の確認を行ったあと、別のスタッフが点呼を取ってダブルチェックする体制を整えることで、リスクを大きく減らせます。
また、運行開始時や終了時に実施する点呼をルール化し、マニュアルに手順として組み込むことで、習慣として根付きやすくなります。音声点呼やデジタル点呼ツールの導入も検討してみましょう。
置き去り防止装置やAIカメラとの連携
2022年以降、園児の送迎バス置き去り事故をきっかけに、国は置き去り防止装置の設置を義務化しました。これにより、乗車後・降車後に車内に人が残っていないかをセンサーで検知し、音声やアラームで警告を発する機能が普及しています。
また、AIカメラや車内の死角を監視する防犯カメラの導入により、人の目が届きにくい部分の確認も可能になっています。マニュアルでは、こうした機器の使い方や点検手順、作動チェックのタイミングなどを具体的に記載し、機械と人の双方による多重チェック体制を整えておきましょう。
送迎マニュアルの作成ステップ
送迎マニュアルは、次の手順で作成するとよいでしょう。それぞれ、詳しく解説します。
- 現場の棚卸しとリスクの洗い出し
- 手順・ルールの明文化
- 写真・動画を活用した可視化
- レビューと改善・現場でのテスト
現場の棚卸しとリスクの洗い出し
マニュアル作成の第一歩は、現場の現状把握とリスクの洗い出しです。どのような車両を使っているか、ルート上に危険箇所はないか、過去にどのようなヒヤリハットや事故があったかを、ドライバーや現場スタッフと一緒に確認しましょう。
現場での声を反映させることで、形式的なマニュアルではなく実態に即した内容に仕上げます。また、チェックリスト形式で課題を洗い出すことで、後の項目整理や構成に役立ちます。
手順・ルールの明文化
実際に行われている送迎業務を「誰が見ても同じようにできるようにする」ためには、業務手順の明文化が不可欠です。ベテランが無意識に行っている操作や判断も、明文化しなければ新人には伝わりません。
「○○をした後に、△△を確認」「□□のときは××に連絡」といった具合に、状況に応じた判断と行動を具体的に記載しましょう。できる限り曖昧な表現を避け、選択肢が複数ある場面では、推奨される行動を明示します。
写真・動画を活用した可視化
操作手順や注意ポイントは、文字情報だけでなく視覚情報で伝えると効果的です。例えば、「リフトの展開方法」や「安全確認の姿勢」などは、写真や動画を使って説明することで理解が深まります。
可視化されたマニュアルは、外国人スタッフや読み書きに不安がある人にも伝わりやすいという利点があります。
レビューと改善・現場でのテスト
マニュアルは作成して終わりではなく、現場でのテストと改善が必要です。実際にマニュアルを使って送迎を行ってみて、使いにくい点や抜けている情報がないかを確認してください。
また、ドライバーや関係者からフィードバックを受け、必要に応じて加筆修正を加えましょう。このプロセスを「1回きり」で終わらせず、年に数回の見直しと定期更新を行うことで、常に現場の変化に対応した「生きたマニュアル」として活用できます。
マニュアル作成にかかる業務負担を減らす方法
送迎業務において、マニュアルの作成は重要であることが分かりました。しかし、マニュアルの作成には手間や時間が掛かり、定期的に情報を更新しなければなりません。そのため、マニュアル作成が、大きな業務負担になっている企業が多いのが現状です。
ビジネスサポートでは、マニュアル作成にITシステム「Teachme Biz」を導入してオンライン化しています。これまでエクセルやパワーポイントなどで作成していたマニュアルですが、IT化することでシステムのテンプレートを活用できます。作成方法は、テンプレートに沿って、画像と文字を入れるだけです。システム上で画像や動画の編集ができるため、一つのシステムでマニュアル作成が完結します。
また、マニュアルのIT化によって情報共有がよりしやすくなりました。オンライン上でマニュアルを管理することで、最新のマニュアルを常に全員が閲覧できます。フォルダごとの管理や、キーワード検索を使えばすぐに必要なマニュアルが見つかります。共有漏れや、どれが最新のマニュアルか分からなくなることを防ぐことが可能です。作成したマニュアルを、タスクとして配信することでマニュアルの閲覧状況も把握でき、人材教育の時間短縮にも繋がっています。
業務負担の軽減には、マニュアル作成のシステム化がおすすめ
安心安全な送迎業務を行うため、送迎業界においてマニュアルの作成は重要だと言えます。マニュアルとは、「送迎業務に関するルールの明確化」「定期的な車両点検の方法の周知」「事故時の対応方法の把握」「緊急時(体調不良など)の対応の把握」などを全員に共有することを目的としています。
マニュアルに関して、事故防止対策は特に大切です。送迎業務では、交通事故だけでなく過去にご利用者様の降ろし忘れなどの事故も発生しており、こうした事故を未然に防ぐためにもミス防止の対策を明確にしたマニュアルの活用が有効です。送迎業界にとって欠かせないマニュアルですが、作成や内容の更新に手間や時間が掛かり負担になっているのが現状です。マニュアル作成をIT化することで、手間が省け時間の短縮にも繋がります。一つのシステム上で全てを管理できるため、情報共有の漏れを防げることもメリットです。ぜひ、マニュアル作成のIT化を検討してみてはいかがでしょうか。
記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。