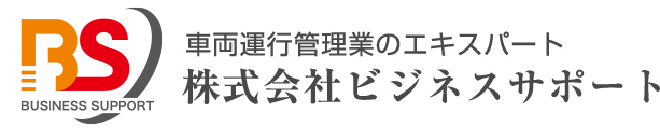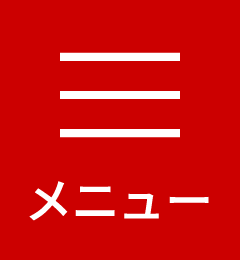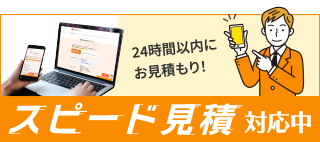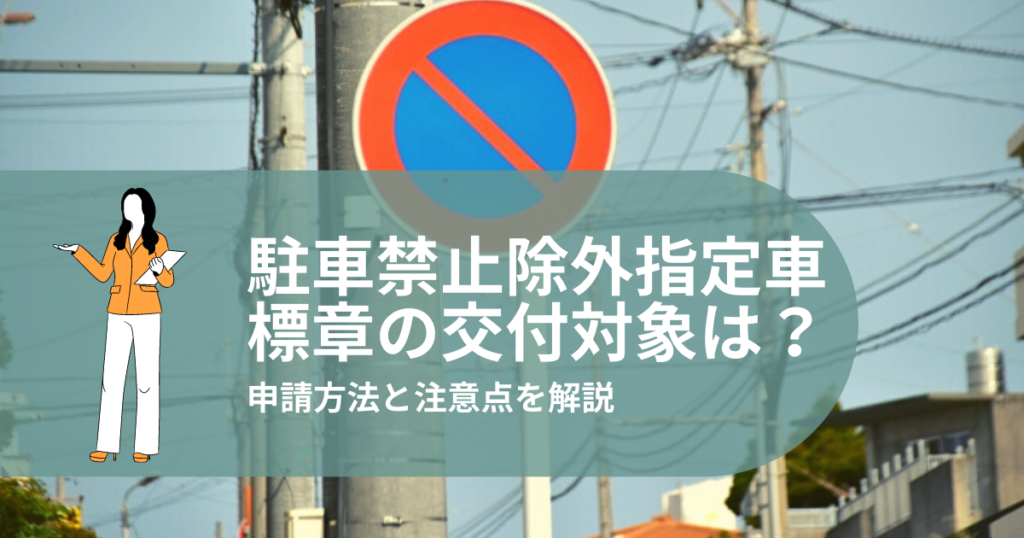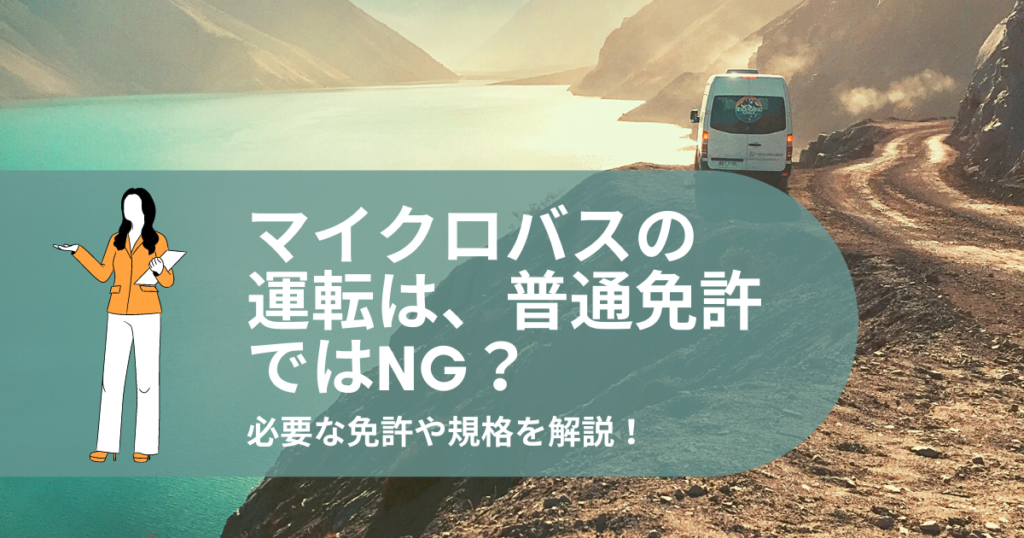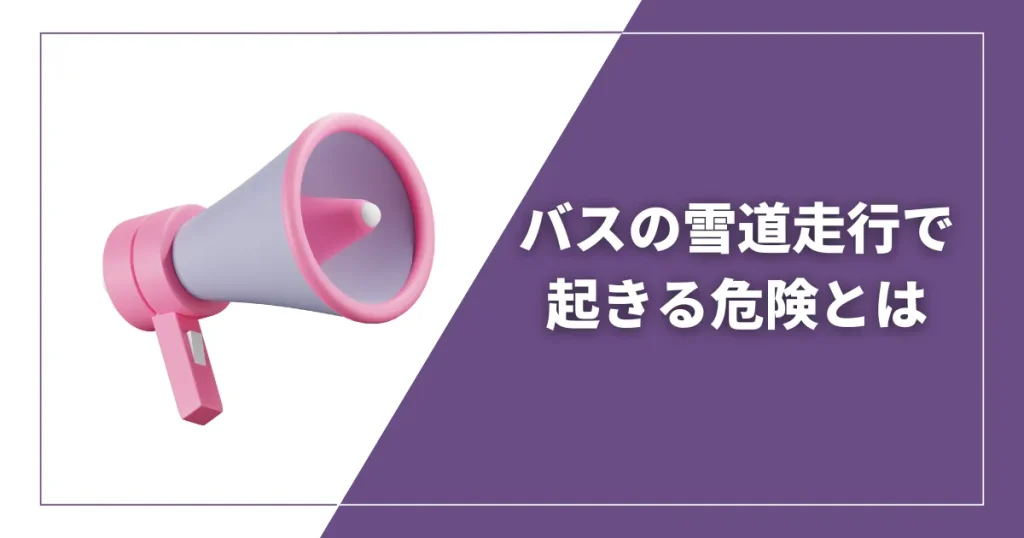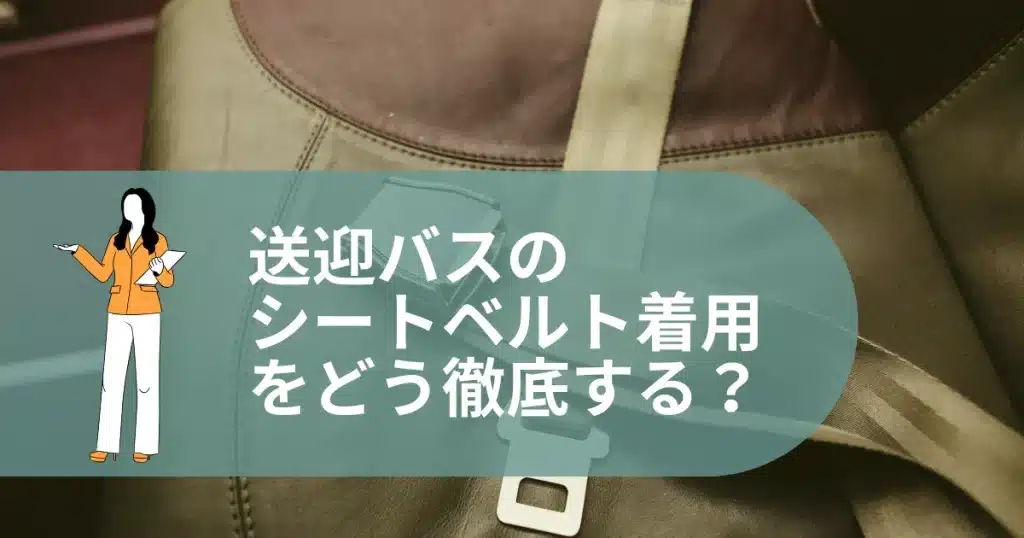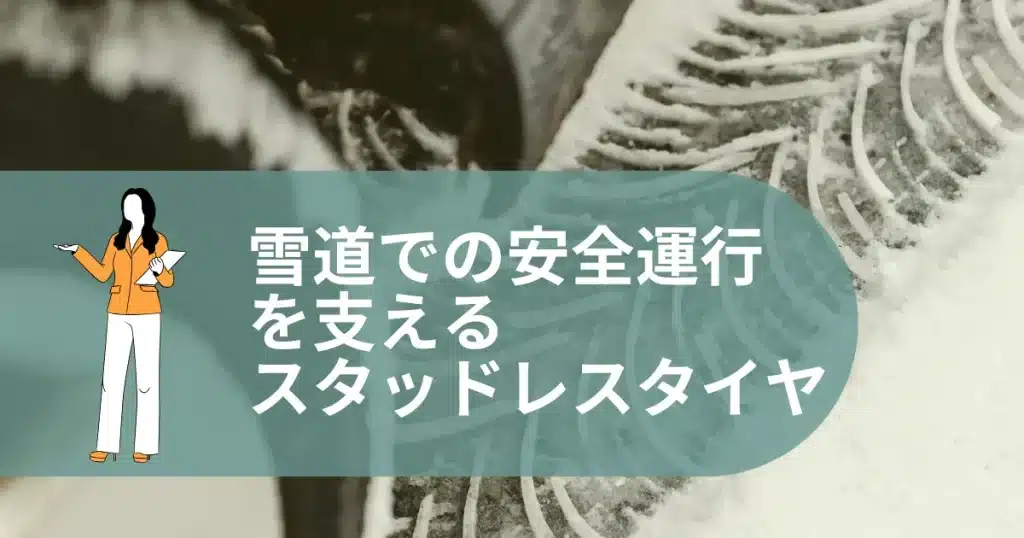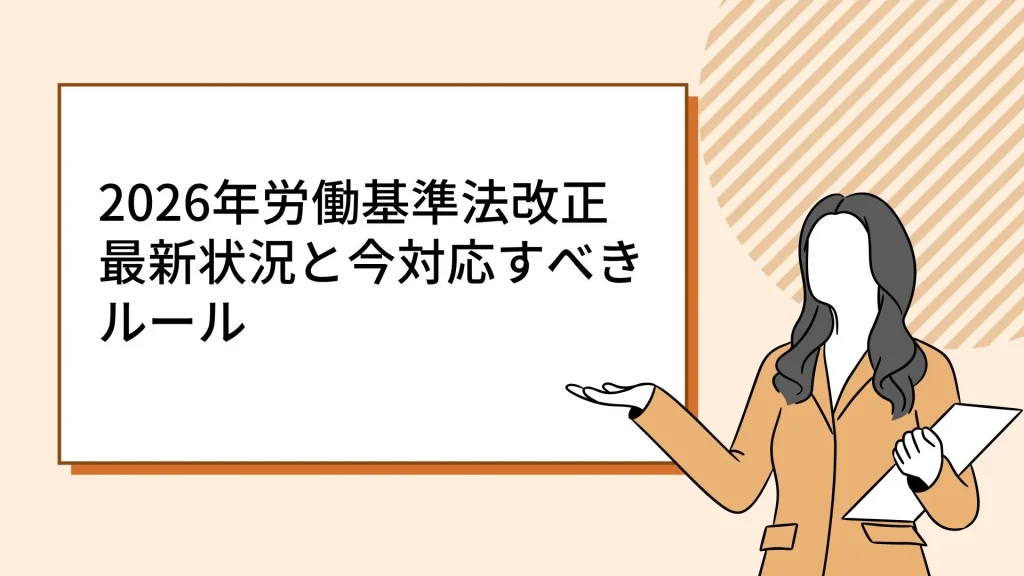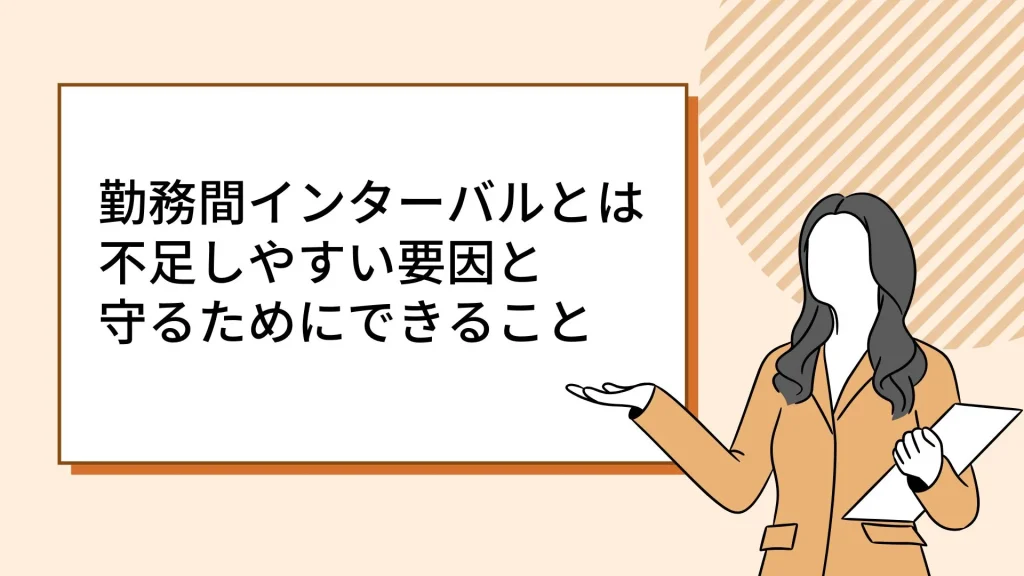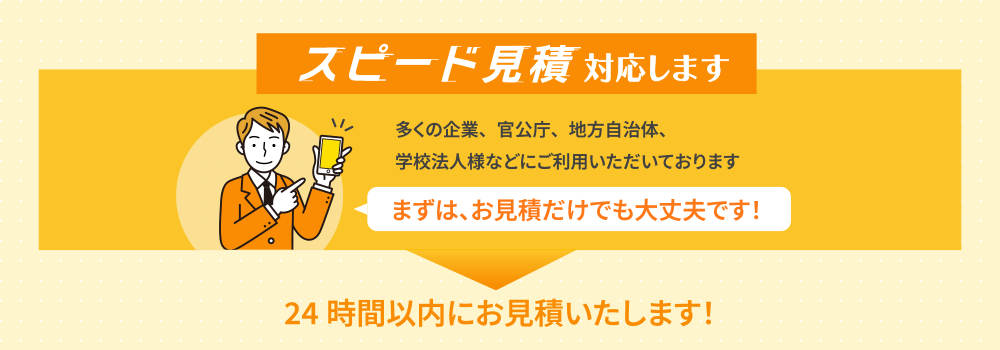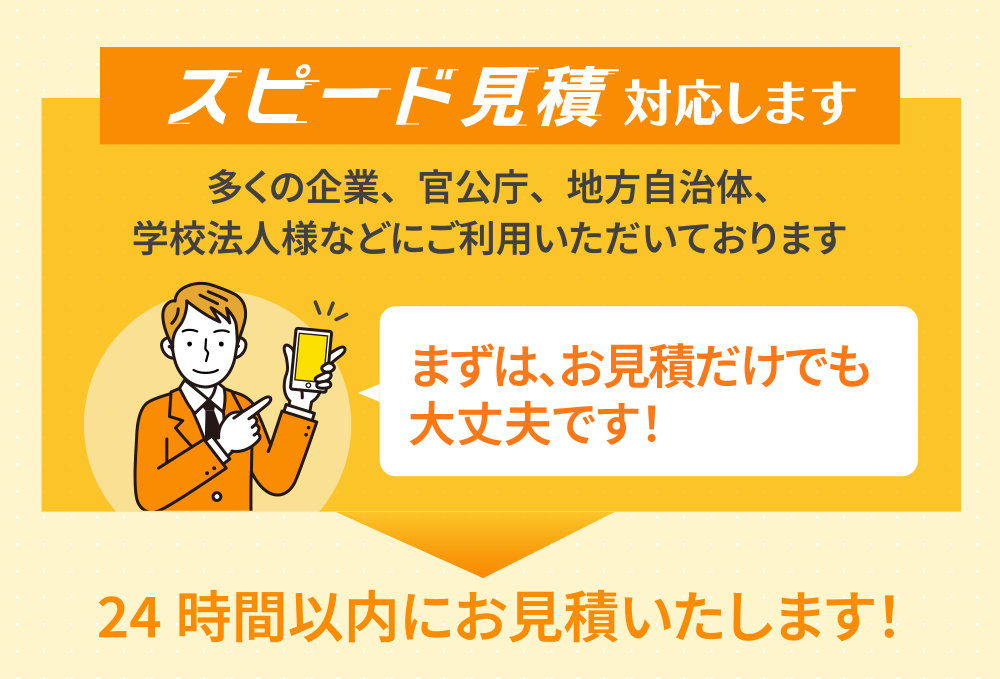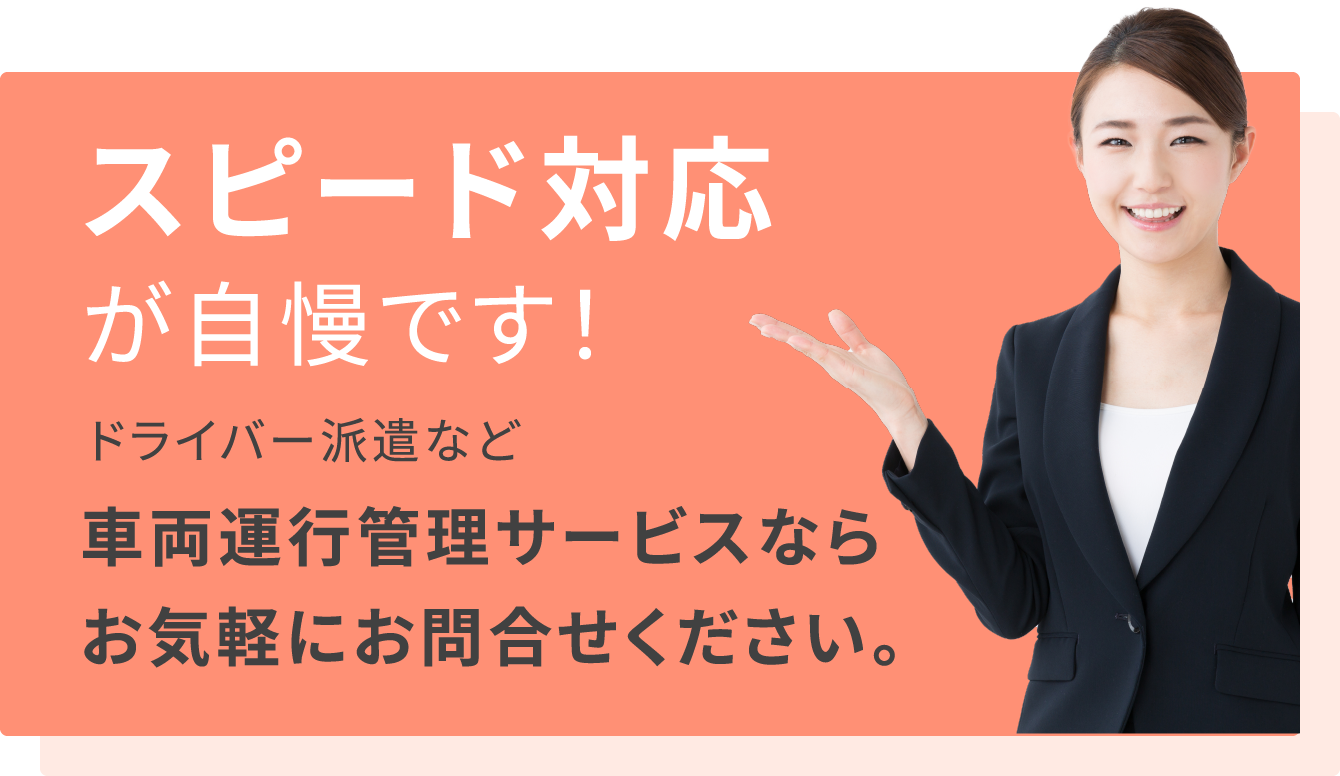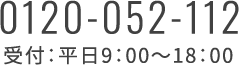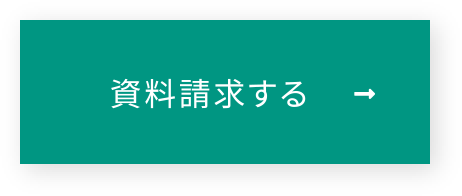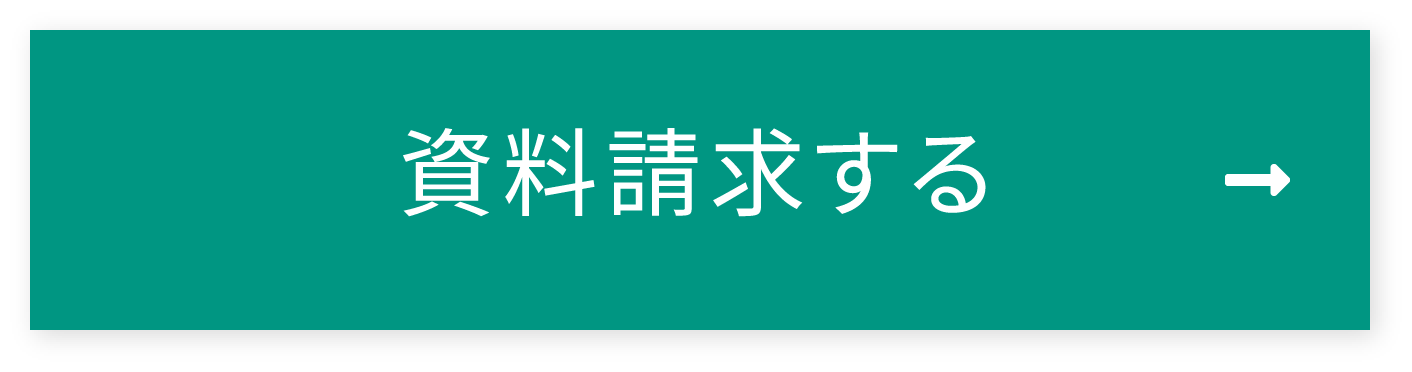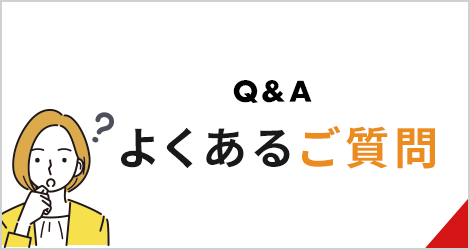2025.02.26
カテゴリ:安心/安全/教育
タグ:安全対策
送迎時に発生する交通事故の原因と事例|事故を防止するためには送迎車が事故を起こしたニュースを聞いて、不安に感じたことがある方もいるでしょう。プロが運転する送迎車両であっても、運行時に事故を起こすことは少なくありません。
この記事では、送迎車における事故の原因や、具体的な事故の例を紹介。さらに、必要とされる事故防止対策についても解説します。
事故の原因や例を知り、安全な送迎車両の運行に役立ててください。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
発生している交通事故の原因

事故を防ぐためには、まず事故が起きている原因を知っておかなければなりません。
警察庁が発表した令和4年(2022年1月〜12月)の交通事故死者数は2610人で、前年比1.0%減、26人減少しています。減少の要因は、先進運転支援システム(ADAS)の普及によるものとされています。交通事故での死者は減少傾向にあるものの、子供が犠牲になる痛ましい事故なども未だ後を絶ちません。
こうした交通事故の主な原因は、「ドライバーの不注意」と「ドライバーの運転技術不足」の2つがあります。
1.ドライバーの不注意
- 安全不確認(一時停止や減速だけで、左右確認などの安全確認が不十分なまま運転すること)
- 脇見運転(タバコを吸いながら、スマホを操作しながらなど他のことに気を取られた状態で運転すること)
- 動静不注視(他の車両や歩行者の確認を怠って運転すること)
- 漫然運転(ぼんやりしながら運転すること)
2.ドライバーの運転技術不足
- 運転操作不適(ハンドルの誤りやアクセルの踏み間違い)
- 速度感覚の欠如(車間距離が短くなったり、減速の遅れが生じ追突事故に繋がっている)
毎年4割近い件数を占める最も多い事故は「追突事故」です。追突事故は前方不注意や交差点進入時の追突など、様々な要因で発生する可能性があります。その他にも、見通しが悪い場所での「出会い頭衝突」や、右折時・左折時の衝突など、ドライバーの油断や確認不足によって発生する事故がほとんどです。
どちらの原因も事前の対策で、十分に事故を防ぐことができます。そのため、ドライバーは事故防止対策にしっかりと取り組み、意識を高めていくことが求められます。
送迎中に発生した事故の例
車両を利用した送迎では、事故が発生することもあります。ここでは、実際に送迎車両が関わった事故の例を紹介します。
- アクセルとブレーキの踏み間違えによる転落事故
- 施設の送迎車に利用者がはねられる事故
- 園児を乗せたバスが住宅の外壁に衝突する事故
なお、ここでは交通事故の例のみを紹介していますが、保育園・幼稚園バスでは置き去り事故も発生しています。置き去り事故の原因や防止策については別記事「幼稚園バスの置き去り事故を防ぐ!安全を確保する6つの対策」で解説していますのであわせてご覧ください。
アクセルとブレーキの踏み間違えによる転落事故
2023年11月20日、福岡県北九州市で介護施設の送迎車がガードレールを突き破る事故がありました。車両は3メートル下の県道まで転落し、乗っていた男女6人のうち5人が病院に搬送されています。
事故の原因について、50代のドライバーは「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しています。
参考:介護施設の送迎車がガードレール突き破り転落 男女5人ケガ 50代運転手「踏み間違えた」(FBS福岡放送) – Yahoo!ニュース
施設の送迎車に利用者がはねられる事故
2023年9月13日、埼玉県内の介護施設で施設の送迎車に利用者3人がはねられる事故が発生しています。
施設の玄関には、事故当時4台の車両が停車していました。3人が停車していたうち1台の車両に乗車しようとしていたところ、向かいから突っ込んできた送迎車にはねられました。事故後の調査で現場にブレーキ跡が見つからなかったことから、送迎車は3人と衝突する直前にスピードを上げたとみられています。
この事故で、1名が軽傷を負い、2名が死亡しています。運転していたのは、75歳のアルバイト運転手でした。
この事故のあと、運転手が施設に詐称した免許を提出していたこともわかりました。施設に提出された運転免許のコピーは7歳若く詐称されており、施設側も免許証の原本を確認しなかった責任を認めています。
参考:埼玉の介護施設で送迎車事故 千葉の施設は対策を徹底 | NHK
参考:年齢制限なかったが…送迎車運転の男、7歳若く書類偽装 さいたま介護施設事故 「原本確認せず」運営会社が謝罪
園児を乗せたバスが住宅の外壁に衝突する事故
2023年9月22日、神奈川県逗子市で幼稚園児5人を乗せた送迎バスが、住宅の外壁に衝突する事故がありました。
園児に怪我はなかったものの、運転していた67歳の男性と付き添いの57歳女性が足に軽い怪我をし、病院に搬送されました。調べに対して、ドライバーは「考え事をしてぼーっとしていた」と話しています。
参考:園児乗せた送迎バス衝突 園児にけがなし 神奈川 逗子 | NHK | 事故
送迎車で事故を起こした場合のリスク
送迎車で事故を起こした場合には、次のようなリスクがあります。それぞれ、詳しく解説します。
- 刑事事件と民事責任
- 行政責任が発生する可能性
- 信用低下と経営への影響
刑事責任と民事責任
送迎車で事故を起こした場合、運転者には刑事責任が、事業者には民事責任が発生する可能性があります。特に死亡事故や重傷事故が発生した場合には、罰則や損害賠償の負担が大きくなります。
刑事責任は、法律違反や過失による事故で科されるものです。運転者が逮捕・起訴される可能性があります。一方民事責任は被害者の賠償を求められるもので、事業者が使用者責任や運行共用者責任を負うことがあります。
刑事責任を回避するためには、安全運転を徹底することが重要です。また、民事責任を最小限に抑えるためには、事業者が適切な教育・指導を行い、事故防止策を強化しなければなりません。
行政責任が発生する可能性
送迎車で事故を起こすと、施設や事業者に対して行政処分が下される可能性があります。特に重大事故が発生した場合には、業務改善命令や事業停止処分が科される可能性があることも知っておかなければなりません。
事業者には、送迎業務の安全管理が義務付けられています。事故が発生し安全対策が不十分だと判断されると、自治体や監督官庁から指導や処分が行われる可能性もあります。また、事故の報告を怠った場合には、さらなる厳しい処分が下されることもあるのです。
施設や事業者は事故を防ぐために送迎業務の安全管理を徹底し、法令遵守を徹底する必要があります。また、事故が発生した際には速やかに報告し、適切な報告を行うことが重要です。
信用低下と経営への影響
送迎車の事故は、施設や事業者の信用を大きく損ない、新規利用者の減少や契約打ち切りなど経営に深刻な影響を与える可能性があります。
事故が発生するとニュースやSNSで話題となり、施設の評判が急速に低下します。また、事故の対応が不十分な場合には、利用者の家族から信頼を失い、契約解除や新規入所者の減少につながるケースもあるでしょう。
送迎業務において事故を防ぐことは、事業継続に不可欠です。さらに、事故発生時の対応を適切に行い誠実な対応を取ることで、信用低下を最小限に抑えられます。
必要とされる事故防止対策
送迎代行を依頼した際の事故は、運転手個人だけではなく企業としても大きい損害が出る可能性があります。送迎代行サービスを利用する場合は、安全に対する意識をしっかり持ち事故防止対策を行なっている会社へ依頼することが重要です。具体的な事故防止対策についてご紹介します。
1. 安全運転講習会
最新の自動車社会の情報を常に把握しておくためには、法律や交通情報事故情報を定期的に勉強することが重要です。愛知県警・自動車事故対策センター・損保会社などの専門家から講演を受けることで、ドライバーは情報をアップデートし現代社会の情勢を把握しています。こうした講演によって、会社全体に事故防止の意識が生まれ、より運転管理者のプロ意識が高まります。
2.実車体験研修
実車体験とは、実際に自分が車椅子で「乗客」として送迎車に乗る体験をすることです。自分が利用者を体験することで、事故防止の徹底だけでなく乗客の気持ちになって運転することの大切さを実感できます。乗客の負担になる操作(急発進・急ブレーキ・急ハンドルなど)を避けるためにはどのようにすれば良いか、研修の参加者と議論し日々の業務に活かすことが目的です。
3.運転適性診断
入社研修時に、外部団体の「独立行政法人 自動車事故対策機構」にて初任者診断を受講します。送迎サービスは人が車を操縦するため、個人によって得意不得意も変わります。科学的な診断結果のもと、それぞれが持つ運転特性に応じて研修やコーチングを行います。指導者だけでなく本人も、自身の苦手を理解したうえで運転にあたるため、普段から注意力が高まり事故の発生率が低くなります。
4.日常点検
車両のメンテナンスも、事故防止には欠かせません。車検を受けたばかりでも、油断せず毎日しっかりと点検を行うことが大切です。万が一のトラブルを避けるため、運転前と業務終了後に車に異常がないか確認しておく必要があります。送迎車両の日常点検は自動車運送法に基づき記録し、毎日の細かなメンテナンスを怠らないことが、安全対策の第一歩です。
5.ドライブレコーダーの設置
講演や研修など事故防止に関して事前の対策も必須ですが、運行中の対策も同様に重要です。AIを搭載したドライブレコーダーは、運転手の目の動きや道路標識を認識して、わき見運転や一時停止違反などの危険運転へリアルタイムにアラートを出します。
これまでの通信型ドライブレコーダーで検出できるアクシデントは「衝撃」や「急加速・急ブレーキ」などに限られていましたが、AIを搭載することで映像を分析し「あおり運転」や「脇見運転」なども検出できるようになりました。また、運転中の映像が記録として残るのでドライバーの特徴に合わせた運転指導が可能になり、ドライバーの意識改善や危険運転の防止に繋がっています。
ドライブレコーダーは事故の記録としての役割だけでなく、事故防止の役割としても今後さらに必要とされていくのではないでしょうか。
事故発生時に取るべき適切な対応
事故発生時に取るべき適切な対応は次の通りです。それぞれ、詳しく解説します。
- 安全確認と負傷者の救護
- 救急・警察への通報
- 二次被害の防止
- 施設・管理者・関係者への報告
- 事故現場の記録・証拠保全
- 保険会社への連絡
安全確認と負傷者の救護
事故が発生した際には最優先で負傷者の確認を行い、救護措置を取ることが重要です。人命救助が最も優先されるため、負傷者がいる場合にはすみやかに応急処置を行わなければなりません。
例えば、利用者が意識を失っている場合にはすぐに心肺蘇生を実施する、出血が多い場合には止血するといった対応が必要です。適切な初動対応を行うことで、被害を最小限に抑えられます。
救急・警察への通報
事故が発生した場合には、速やかに警察に通報しましょう。また、負傷者がいる場合には応急処置と並行して救急への通報も行わなければなりません。
交通事故は法的に報告義務があり、警察への通報を怠ると報告義務違反として処罰の対象となる可能性があります。
例えば、軽微な接触事故だからと警察を呼ばなかった場合、後から相手が「むち打ちになった」と主張しトラブルになることが考えられるでしょう。また、負傷者がいるにもかかわらず救急への通報が遅れた場合には「救護義務違反」として刑事責任を問われる可能性があります。
すべての事故は必ず警察に報告し、必要に応じて救急要請を行わなければなりません。
二次被害の防止
事故現場では、さらなる事故を防ぐための措置を取る必要があります。
放置された車両や無防備な状態の利用者がいると、後続車の追突事故や接触事故のリスクがあるため、適切な安全管理が求められます。
例えば後続車が多い道路で事故が発生した場合には、三角停止板や発煙筒を使用し、後続車に注意を促す必要があるでしょう。利用者が車内に残っている場合には、車外に避難させ、安全な場所へ誘導する必要があります。
二次被害を防ぐための適切な行動を取り、安全を確保することが重要です。
施設・管理者・関係者への報告
事故発生後、ドライバーは施設の管理者や関係者に速やかに報告し、適切な対応の指示を受けることが重要です。
管理者や関係者への報告が遅れると、事故対応が後手に回り利用者の家族対応や保険手続きが滞る可能性があります。また、施設側での再発防止策の検討や必要な追加対応の指示が出せないため、状況が悪化してしまうリスクもあるでしょう。
施設・管理者・関係者への速やかな報告により、スムーズな事故対応と信頼回復が可能になります。報告ルールを事前に定め、事故時に迅速に動ける体制を整えておきましょう。
事故現場の記録・証拠保全
事故の詳細を正確に記録し証拠を確保することで、責任の所在を明確にし、後のトラブルを防げます。
証拠が不十分だと過失割合の判断が曖昧になり、損害賠償請求の際に不利になる可能性があります。また、事故の状況を正確に把握することは、施設側の責任を適切に説明するためにも重要です。
例えば、車両の位置関係や道路状況を写真で記録しておくことで、後からどちらに過失があるか判断しやすくなります。また、ドライブレコーダーの映像を確保しておくと、相手が不適切な主張をした場合でも、正しい証拠を提示可能です。
事故現場の記録と証拠保全を徹底することで、事業者や運転者が不当な責任を負うことを防ぎ、公正な事故処理ができます。
保険会社への連絡
事故発生後は速やかに保険会社へ連絡し、補償内容の確認と必要な手続きを進めましょう。
保険会社への報告が遅れると、補償が受けられなかったり、手続きが複雑化したりする可能性があります。また、事故の対応を間違えると、損害賠償請求を受けた際に不利になることもあるため、正しい流れで進めなければなりません。
事故後のリスクを最小限に抑えるためには、保険会社と密に連携し、適切な補償を受けられるよう手続きを進めることが不可欠です。事前に保険の適用範囲を把握し、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。
送迎代行サービスの利用も選択肢のひとつ
少子高齢化が進み、労働人口が減少することが見込まれる日本では、企業での業務効率化が求められ、業務負担を軽減するシステムやサービスの導入が進んでいます。送迎代行サービスは、介護施設や幼稚園などで負担になっている「送迎業務」を外部委託できるサービスとして期待されています。
送迎業務は送り届けるだけでなく、毎日の車両点検や感染症予防対策など細かなメンテナンスが必要です。そのため、通常の業務よりも負担が大きいとされています。送迎代行サービスを活用すればメンテナンスも含めて全てを一任できます。
人手不足の企業はもちろん送迎に関連する事務作業が煩雑だと感じる企業にも求められているサービスです。
送迎代行を活用するメリット
送迎代行を活用する具体的なメリットは次の4つです。それぞれ、詳しく解説します。
- プロのドライバーによる送迎を実施できる
- 送迎に関連する各種業務をまるごと委託できる
- 必要な時だけ利用できる
- 事故の対応を任せられる
プロのドライバーによる送迎を実施できる
送迎代行業者に依頼した場合、プロのドライバーが運転を担当します。
施設によっては、普段介護や保育など施設内の業務を担当しているスタッフが一時的に送迎業務を担当するケースも少なくありません。そうしたスタッフにとって送迎は専門としている業務ではないため、十分な研修を受けていないこともあります。また、運転が苦手なのにも関わらず、送迎業務を担当しなければならないこともあるでしょう。
送迎代行業者を活用すれば、研修を受けたプロのドライバーが運転を担当するため、事故の可能性を下げられます。運転が苦手なスタッフにストレスを与えてしまうこともありません。
送迎に関連する各種業務をまるごと委託できる
上記でも解説した通り、送迎代行業者に依頼すると関連する各種業務をまるごと委託できます。
例えば、送迎用の車両は日々の清掃や給油といったメンテナンスが必要です。また、ルートの作成や定期点検なども行わなければなりません。ドライバーを自社で雇用する場合には、労務管理も必要です。
送迎代行業者を利用すれば、これらの業務をすべて委託できます。運転業務だけでなく、関連する業務分も負担を減らせるため、その分本来の業務に集中できるでしょう。
必要な時だけ利用できる
送迎代行業者は、必要な時だけ利用できるのもメリットです。
例えば、繁忙期で運行する送迎車両の本数を増やしたいときや、休みを取るスタッフが多い時期だけ送迎代行業者に依頼することも可能です。
一時的にドライバーが不足して悩むことが多い方は、送迎代行業者の利用を検討してみてください。
事故の対応を任せられる
プロのドライバーが運転するといっても、車両を利用する以上事故が起きたときのことは考えておかなければなりません。
送迎代行業者に依頼した場合、事故の対応はすべて業者に任せられます。現場での対応はもちろん、被害者がいる場合の示談交渉や保険会社とのやりとりも、すべて代行業者が実施します。
多くの人が、事故の対応には慣れていません。自社の車が事故を起こしたときに対応しようと思うと、慌ててしまうこともあるでしょう。
送迎代行業者に依頼すれば、プロが事故後の対応を引き受けてくれる点も安心です。
送迎代行サービス選びは、事故防止対策が万全な企業を選ぼう
送迎代行サービスとは、業務負担の大きい送迎業務を外部委託することができるサービスです。導入することで、人的リソースの確保と今後の労働力不足の改善にも繋がります。しかし、事故が発生すれば運転手個人だけでなく、企業にとっても大きな損失になります。そのため、安全対策をしっかりと行なっている企業に依頼することが重要です。
日本における令和4年度の交通事故死者数は2,610人で、交通事故の大きな原因はドライバーの「不注意」と「技術不足」が挙げられます。このような事故の対策として、常に最新の交通情報を得るための「安全運転講習会」や実際に送迎車に乗車して乗客の気持ちを体感する「実車体験研修」、運転時の苦手を知り改善する「運転適性診断」などがあります。
さらに、AIドライブレコーダーの設置で、リアルタイムにドライバーへ危険運転のアラートを出しています。ドライブレコーダーの映像を振り返ることで、ドライバーの意識改善と事故防止にも活用されています。ビジネスサポートでは、こうした事故防止対策を徹底して実施しています。送迎代行サービスの導入をお考えの方はぜひ、事故防止対策が万全なビジネスサポートの送迎代行サービスをご利用ください。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。