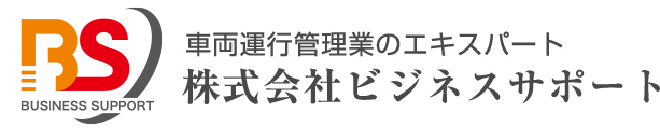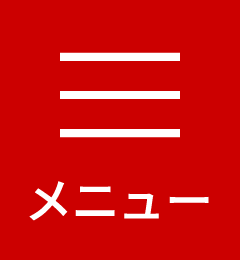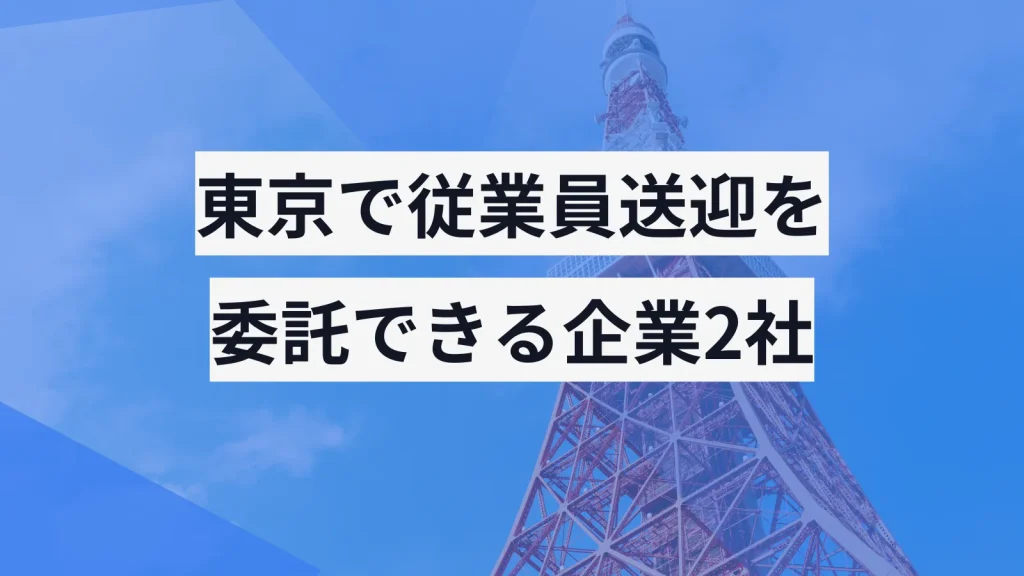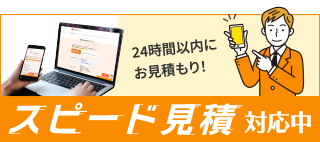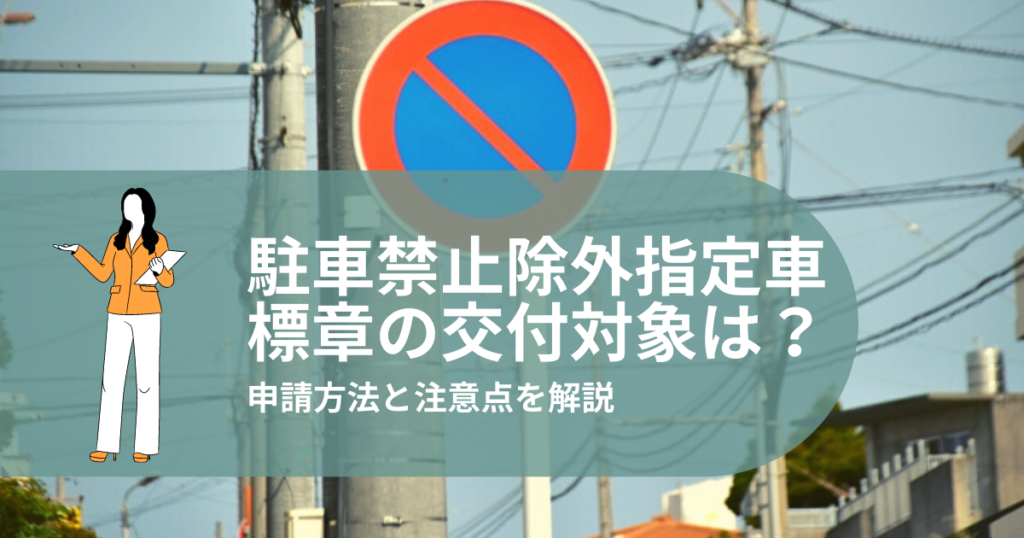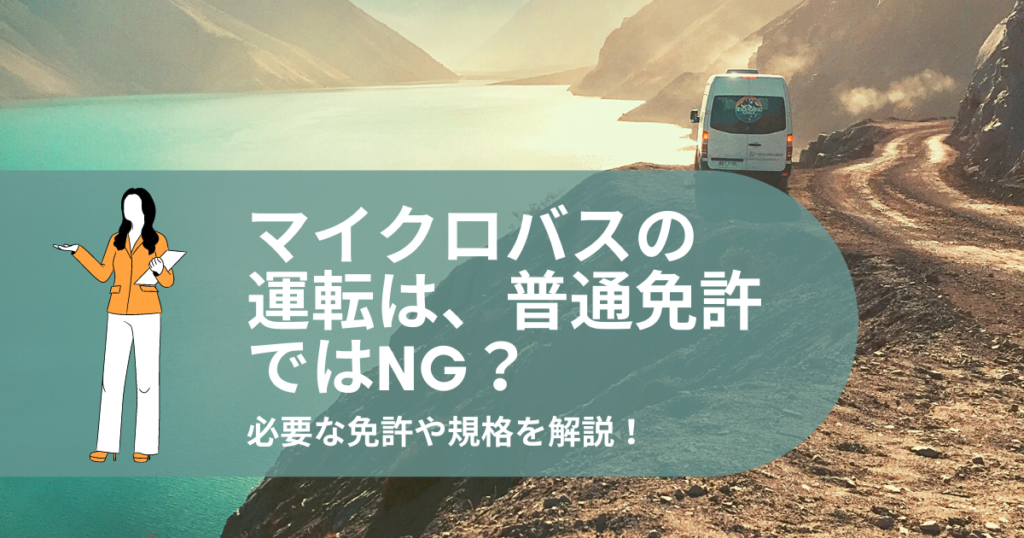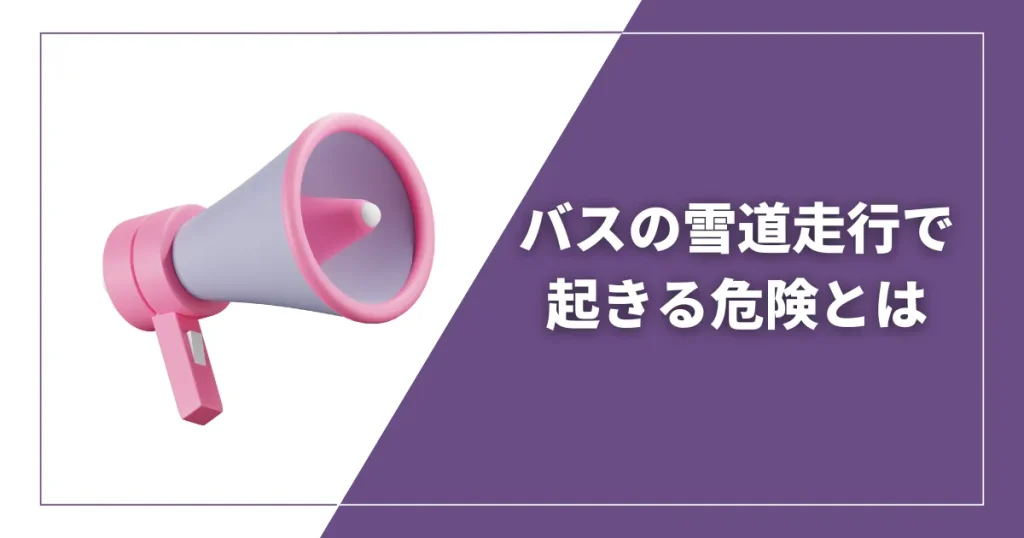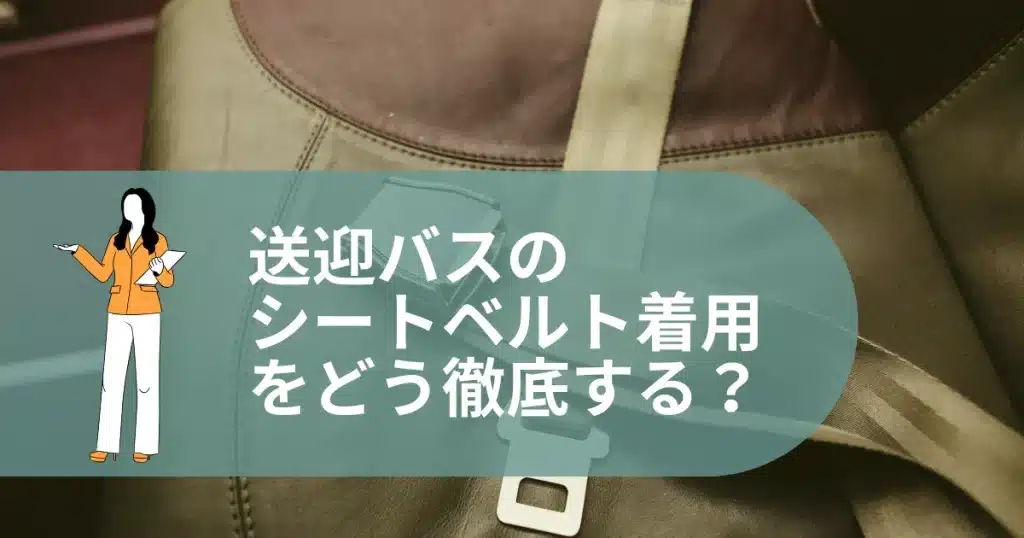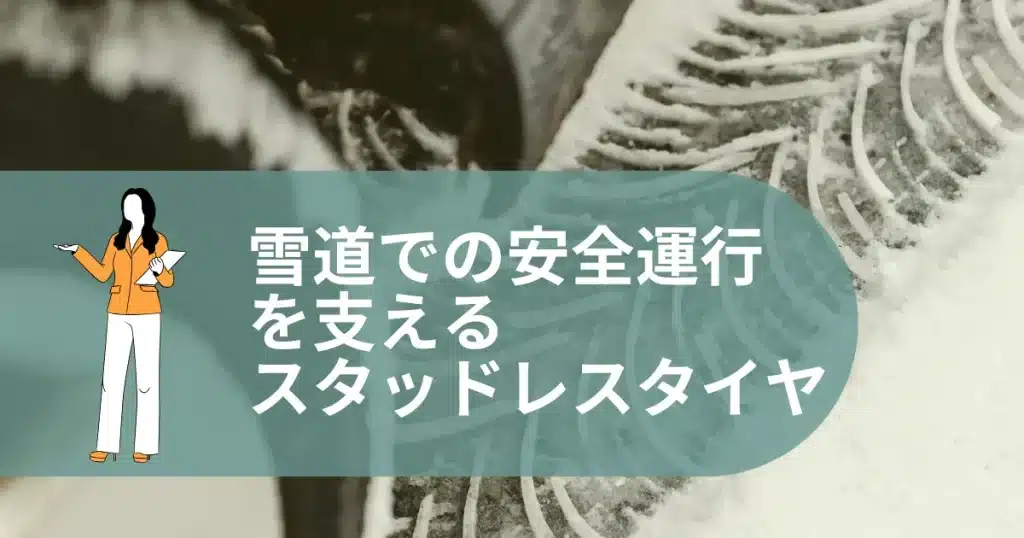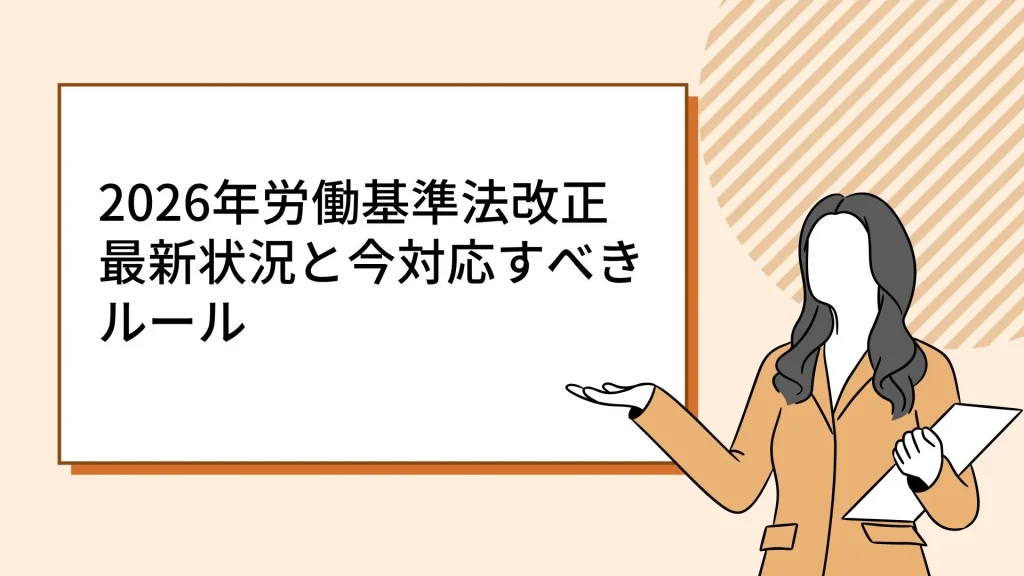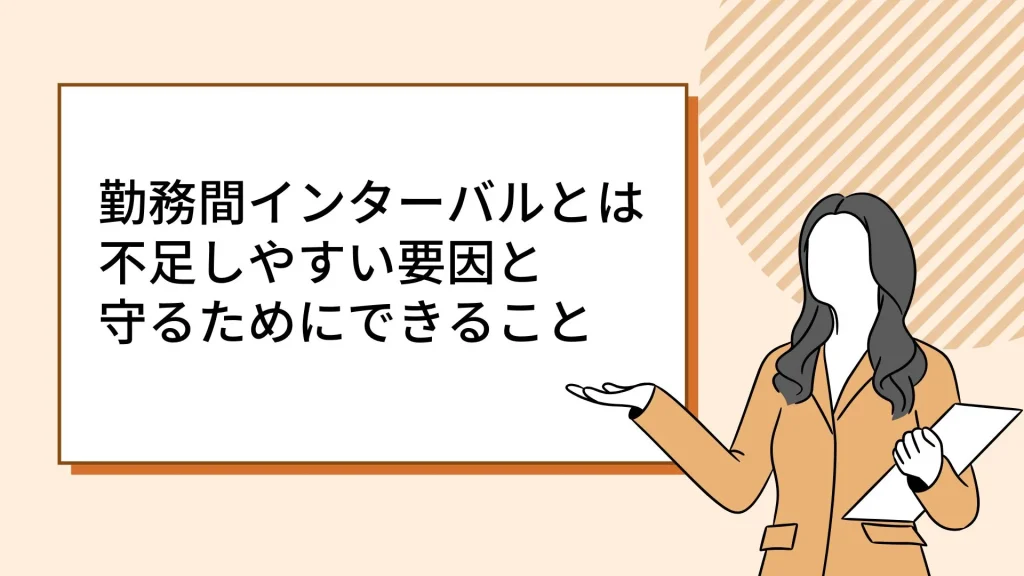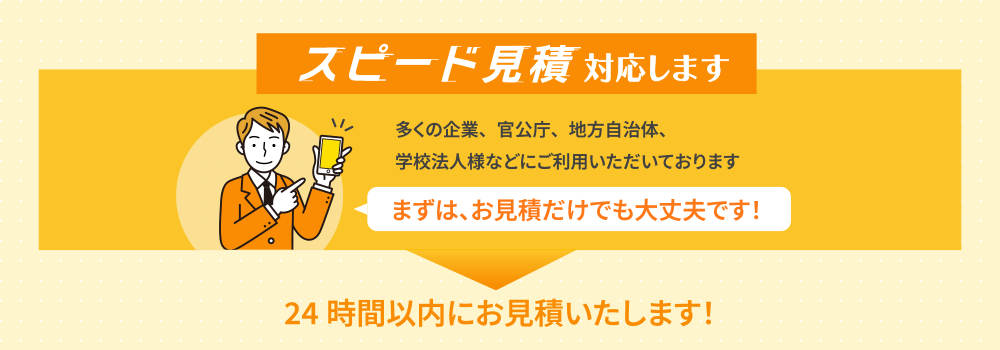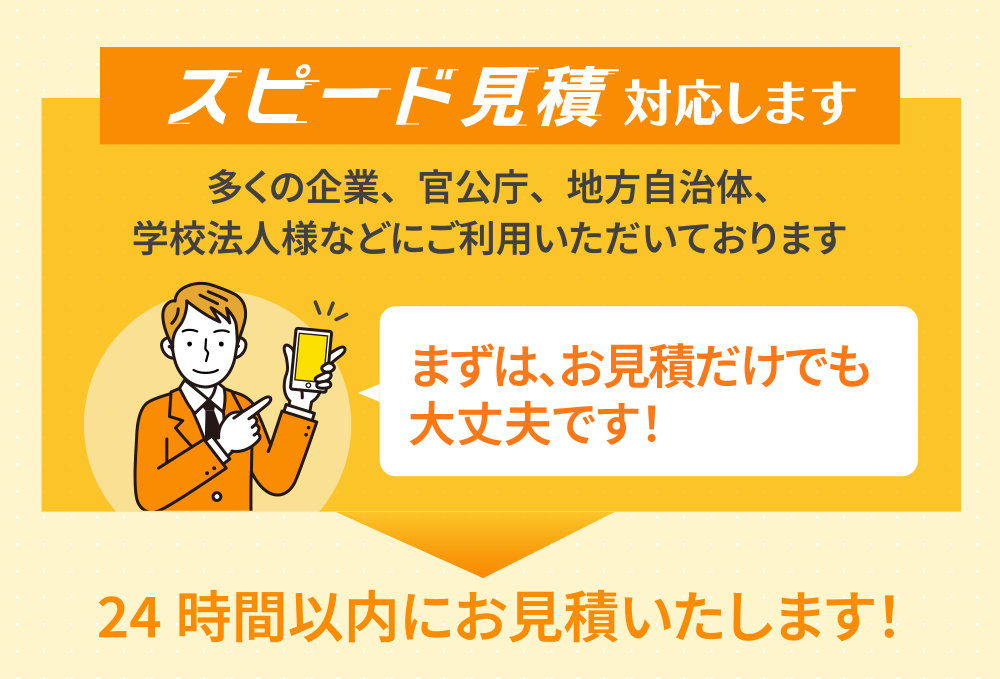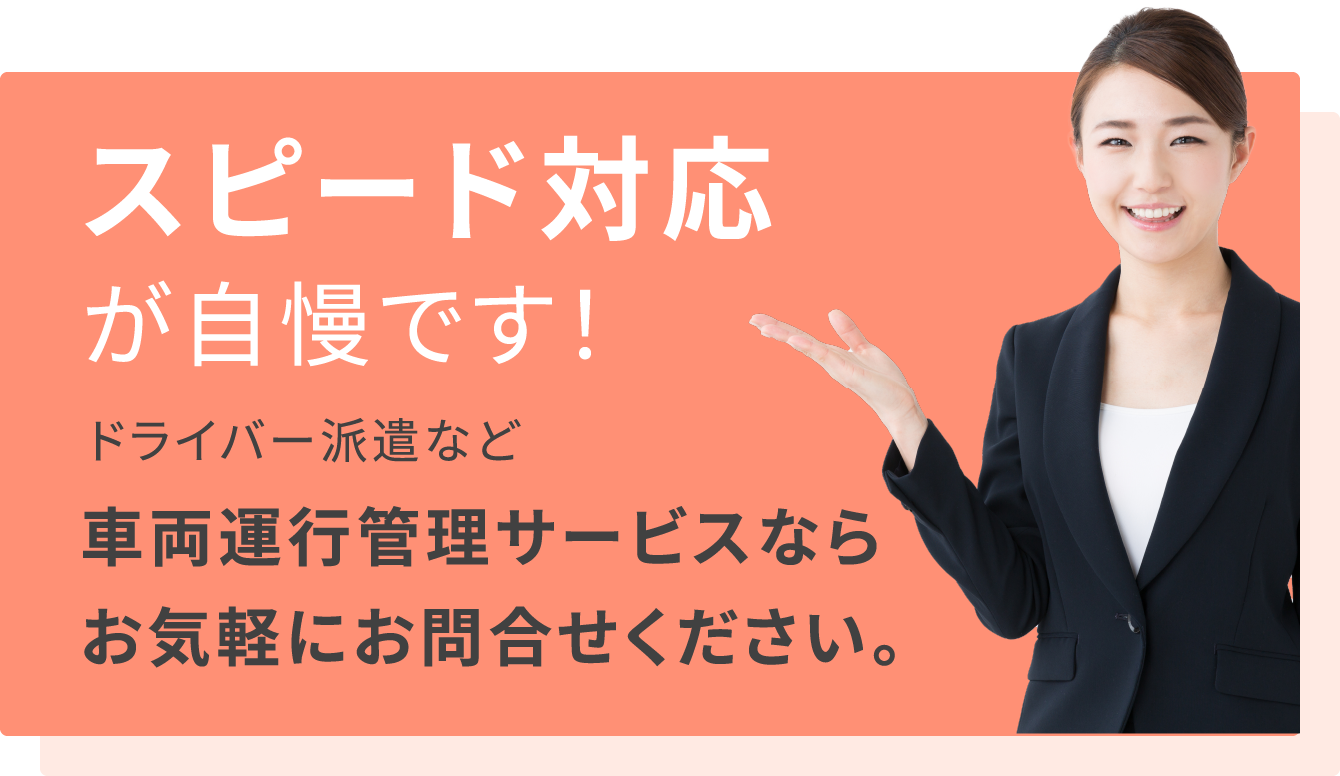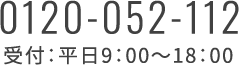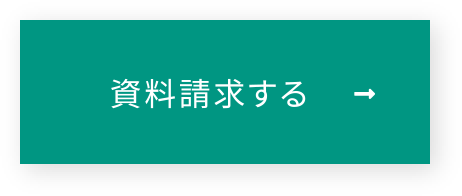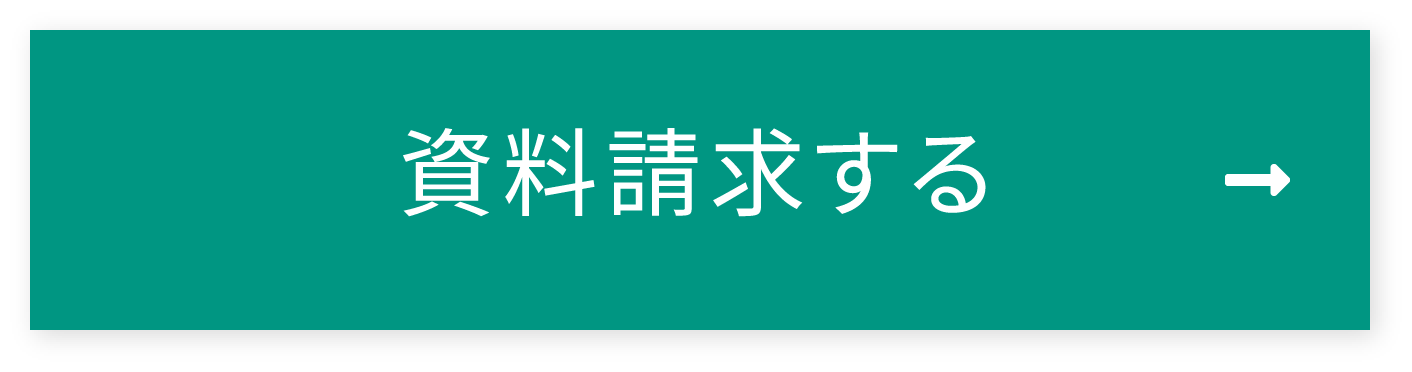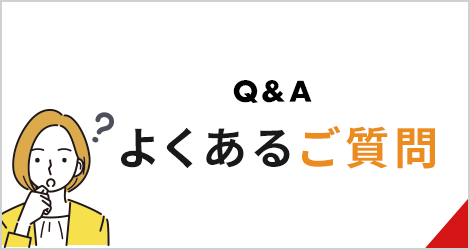2025.07.21
カテゴリ:運行管理
タグ:送迎委託
【従業員送迎 / 東京】送迎代行のおすすめ企業2選!成功のポイントも解説「郊外の勤務地に人が集まらない」
「学生アルバイトを採りたいけれど通勤がネックになる」
そんな悩みを抱える企業にとって、有効な打ち手となるのが従業員送迎バスの導入です。
この記事では、従業員送迎の導入メリットや導入に適したケース、成功させるためのポイントを解説。さらに、東京都内でおすすめの送迎代行業者も厳選してご紹介します。「人が集まらない」「定着しない」とお悩みの方は、ぜひご覧ください。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
人手不足の解消に従業員送迎が有効
人手不足の解消には、従業員送迎バスの導入が効果的です。特に地方や郊外に事業所を構える企業では、通勤手段の確保が採用の障壁となることが少なくありません。
送迎バスを活用することで、交通の便が悪い地域でも通勤が容易になり、応募者の間口を広げることが可能です。また、移動手段を提供することで、採用活動でのアピールポイントにもなり得ます。
たとえば、地方の製造業では「通勤手段がないため就職を諦めた」という求職者が一定数存在します。送迎バスを運行することで、そうした潜在的な人材の確保につながり、結果的に人手不足の緩和が期待できます。
人材確保に悩む企業にとって、送迎サービスは単なる福利厚生を超えた戦略的な投資といえるでしょう。
東京の従業員送迎におすすめな委託会社2選
東京都には、多数の送迎代行業社があります。それぞれに特徴があり、得意分野も異なるため、目的に合う業者を選ぶことが重要です。ここでは、東京都で従業員送迎が得意な送迎委託業者を2社紹介します。
- ビジネスサポート
- みつばモビリティ
1.ビジネスサポート
株式会社ビジネスサポートは「日本一まじめな運行管理会社」をテーマに掲げ、安全への取り組みを第一優先としながら運営している送迎代行業者です。DX化にも積極的に取り組んでおり、既存のプロセスをデータ化することで業務効率化を進めるとともに、リアルタイムに顧客に情報を届けています。
年間60万人以上の送迎体制が整っていることに加え、長年の実績に基づいて送迎環境で発生する「不満」「問題」「不安」を解消する企業です。
|
支援実績 |
|
|
創業 |
2006年 |
2.みつばモビリティ
※引用:みつばモビリティ
みつばモビリティは、食品工場や派遣スタッフの送迎において、多くの実績を持つ送迎支援サービス企業です。従業員の勤務時間や交通事情に合わせて、最適なバスコースや時刻表を柔軟に設計。通勤ストレスの軽減や業務効率化をサポートする送迎体制を構築しています。
独自開発の出勤管理システム「起きたらドットコム」により、ドライバーの出勤状況をリアルタイムで把握。直行直帰の勤務形態でも、寝過ごしやシフトの勘違いによる運行トラブルを防ぎ、安定した送迎を実現しています。
|
創業 |
1994年 |
従業員送迎バスの活用が特に効果的なケース
従業員送迎バスの活用は、次のような場合に特に効果的です。それぞれ詳しく解説します。
- 通勤手段が限られている
- 夜間の勤務がある
- 学生アルバイトが多い
通勤手段が限られている
通勤手段が限られる地域では、送迎バスの導入が大きな効果を発揮します。駅から遠い、バスの本数が少ない、交通機関の接続が悪いといった環境では、従業員の通勤が困難になりがちです。
このような場合、送迎バスによって自宅近くや主要駅までの直通ルートを確保できれば、通勤の負担を大きく軽減できます。結果として離職防止や定着率の向上にもつながります。
特に、郊外の工業団地や物流拠点においては、送迎の有無が応募数に直結する重要な要素だといえるでしょう。
夜間の勤務がある
深夜・早朝勤務がある職場では、公共交通機関が利用できない時間帯の通勤手段が課題になります。こうした時間帯に対応した送迎バスの運行は、従業員の安全確保と定着率向上に貢献します。
夜間勤務は体力的な負担が大きいため、通勤のストレスを減らすことは重要です。また、防犯上のリスクもある時間帯においては、企業としての責任ある対応が求められます。
従業員送迎は、職場環境の改善だけでなく、企業の社会的信頼にもつながります。
学生アルバイトが多い
学生アルバイトの雇用が多い企業にとって、送迎バスの導入は採用機会の拡大に寄与します。特に高校生などの若年層は、自動車免許を取得していない、あるいは自家用車を持っていないケースが大半です。そのため通勤手段が限られており、交通アクセスの悪い勤務地では応募をためらう傾向があります。
送迎バスを導入すれば、自家用車がないことを理由に応募を見送っていた層にもリーチできる可能性があります。通勤しやすい環境を整えることで学生にとっても働きやすい職場となり、企業側としては安定した人材確保につながるでしょう。
従業員送迎バスの導入を成功させるためのポイント
従業員送迎バスの導入を成功させるためには、次のようなポイントに注意しましょう。それぞれ、詳しく解説します。
- ニーズに合ったルート設計を行う
- 車両や運転手の安全対策を徹底する
- 従業員への周知・利用促進を行う
- コストと効果のバランスを見極める
ニーズに合ったルート設計を行う
送迎バスを効果的に運用するには、従業員の居住地や勤務時間帯に合わせたルート設計が不可欠です。通勤時間の短縮や乗車の利便性を意識し、無駄のない運行スケジュールを組みましょう。次のような点を意識すると、ニーズに合うルートを設計できます。
- 主要な駅やバス停を経由する
- 時間帯別の出勤・退勤ニーズを反映する
- 道路事情や渋滞リスクを考慮する
事前にアンケートなどで従業員の希望を把握すると、より実用的な設計が可能です。
車両や運転手の安全対策を徹底する
送迎バスの安全性は、企業の信頼性に直結します。安全な運行体制を整えることで、従業員の安心感と満足度が向上します。
車両の定期点検を確実に実施するとともに、経験豊富で安全教育を受けた運転手を採用すると安心です。緊急時対応マニュアルを整備しておくことで、急なトラブルにも慌てずに対応できるようになります。
安全面の配慮は、リスク管理だけでなく実際に送迎バスを利用する従業員への信頼材料としても有効です。
従業員への周知・利用促進を行う
導入した送迎バスを有効活用するためには、従業員への周知が不可欠です。利用方法や時刻表、乗車場所を明確に伝えることで、利用率が高まります。周知の方法としては、次のようなものが考えられます。
- 社内ポータルや掲示板での案内
- 入社時研修での説明
- 定期的な利用状況のヒアリングと改善
従業員の声を取り入れることで、制度として定着し利用率が高まるでしょう。
コストと効果のバランスを見極める
送迎バスはコストがかかる一方で、人材確保や定着率向上といった効果も期待できます。費用対効果を正しく評価し、導入の継続可否を判断することが大切です。次のような指標を確認しておくと、判断材料として活用できます。
- 採用数や応募率の変化
- 離職率の低下
- 業務開始時間の遵守率
定量的なデータをもとに、送迎バスの導入が企業成長にどう貢献しているかを定期的に見直しましょう。
従業員送迎をアウトソーシングするメリット
従業員送迎のアウトソーシングには、次のようなメリットがあります。それぞれ、詳しく解説します。
- 運行管理の負担を軽減できる
- 専門業者により安全性と信頼性を確保できる
- 必要に応じて柔軟な運行ができる
- 法令対応や事故時対応を任せられる
- ドライバーの欠勤時には代理のドライバーが派遣される
運行管理の負担を軽減できる
送迎業務をアウトソーシングすることで、企業側の運行管理の負担を大幅に軽減できます。特に中小企業では専任の担当者を置くのが難しいケースも多く、外部委託のメリットは大きいといえるでしょう。
スケジュール調整やドライバー手配、車両点検など、煩雑な業務を専門業者に任せることで、企業は本来の事業に集中できます。
専門業者により安全性と信頼性を確保できる
送迎の専門業者は、安全運行に関するノウハウと実績を持っています。適切な運転手教育や安全点検の体制が整っており、自社での運用に比べてリスク管理の精度が高くなります。
結果として、従業員にとっても安心感のある送迎サービスが提供でき、企業の信頼性向上にもつながるのです。
必要に応じて柔軟な運行ができる
繁忙期や短期的な人員増加に応じて、車両台数や運行時間を柔軟に調整できるのも外部委託の強みです。契約内容によっては必要なときだけの運行も可能なため、コスト効率の良い運用が実現します。
また、新規拠点の立ち上げやイベント時の臨時運行にも対応できるため、企業の事業展開に合わせた運用が可能です。
法令対応や事故時対応を任せられる
道路交通法や労働関連法規など、送迎に関わる法令遵守は煩雑かつ専門的です。アウトソーシングすることでこれらの対応を業者に一任でき、企業側の法的リスクを軽減できます。
万が一の事故発生時にも保険対応や関係機関との調整をスムーズに進められるため、迅速かつ適切な対処が可能です。
ドライバーの欠勤時には代理のドライバーが派遣される
自社で運用する場合、ドライバーの急な欠勤は業務の混乱につながります。一方、委託業者であれば、欠勤時に代理ドライバーを派遣する体制が整っているため、安定的な運行が可能です。
バックアップ体制があることで送迎サービスの信頼性を高めるとともに、従業員にとっても安心材料となります。
自社で送迎バスを運用するメリット・デメリット
代行業者を利用せず、自社で送迎バスを運用することも可能です。ここでは、自社で送迎バスを運用する場合のメリット・デメリットを解説します。
自社で送迎バスを運用するメリット
自社運用の最大のメリットは、運行内容を自社の都合にあわせて柔軟に調整できる点です。ルート、時間、車両の使い方などを自社の裁量で決められるため、細やかな対応が可能になります。
また、長期的に見ると委託費用を抑えられる可能性があり、車両を資産として保有できる点も利点です。ドライバーとの信頼関係が構築できれば、従業員とのコミュニケーションに良い影響を与えるケースもあるでしょう。
自社で送迎バスを運用するデメリット
一方で、自社運用には管理負担やコストリスクが伴います。車両の購入・維持費、保険、点検、人件費など多くのコストが発生します。また、ドライバーの採用・教育・シフト管理といった運行管理の負担も無視できません。
さらに、事故やトラブルが発生した際の対応もすべて自社で行う必要があり、企業のリスク管理能力が問われます。送迎サービスを安定的に運用するためには、相応の体制整備が求められます。
送迎運行サービスのご契約の流れ
マイクロバス送迎運行サービスのご契約は、次の流れで進めます。
|
事前準備 |
・送迎業務内容および見積書のご確認 ・当社自動車運行管理契約約款のご確認 発注書、車検証、自動車保険証書の受領後、当社より契約書をご提出致します |
|
ご契約手続き |
・自動車運行管理契約の締結 ・自動車保険加入証明書のご提出 ・管理車両にトライプレコーダーを設置 ドライバーの配属までは、最大で2ヶ月程度が目安です。※地域により異なる |
|
稼働 |
・ルート改善のご提案(都度) ・運行診断報告書のご提出(都度) ・ご契約プランの見直しご提案(随時) |
事前に各種書類をご確認いただいた後、弊社で発注書、車検証、自動車保険証書を受領してから契約書をご提出いたします。ドライバーの配属までは最大で2ヶ月程度かかるため、利用をご検討中の方はお早めにご相談ください。
送迎を外部委託した際の料金イメージ
送迎委託の料金は、利用する頻度によって異なります。例えば1日4時間未満の利用の場合、ビジネスサポートでは以下のように料金を設定しています。
1週間あたり3日間稼働:13万3,000円〜
1週間あたり6日間稼働:24万7,000円〜
※予め決められた曜日のみの対応となります。
一日の稼働が4時間を満たさなくても翌日以降に繰り越すことは不可です。
一日の稼働が4時間を超えた場合は、30分単位でカウントします。
送迎に付随する誘導介助は対応できますが、介護業務は対応不可です。
運行管理者(運転手)が起因する、対人・対物事故は全て補償します。
運行管理者(運転手)が起因する、単独物損事故は全て補償します。
保険・装備対応車両は、1契約あたり1台(お客様所有)となります。
エリアや地域の最低賃金の変動によって料金が異なります。
契約プランだけでなく、オプションによっても料金が変わります。詳細な料金を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
送迎代行サービスを有効活用しよう
従業員の送迎サービスがあると、公共交通機関が不便な場所や深夜・早朝の勤務でも従業員を集めやすくなります。人手不足に悩んでいる企業では、ぜひ導入を検討してみてください。
自社での運用が難しいと感じる場合には、送迎代行サービスの活用もおすすめです。送迎代行サービスを活用することで、安全性と信頼性を確保できます。さらに、必要な時には増発するなど、柔軟な対応も可能です。
この記事を参考に、自社に合う送迎サービスの導入方法を考えてみてはいかがでしょうか。
記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。