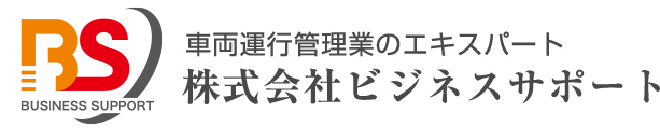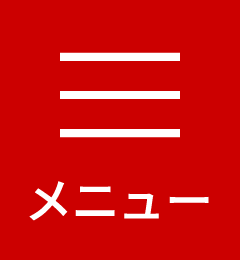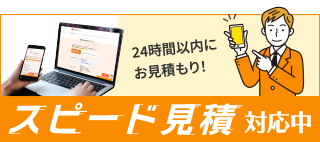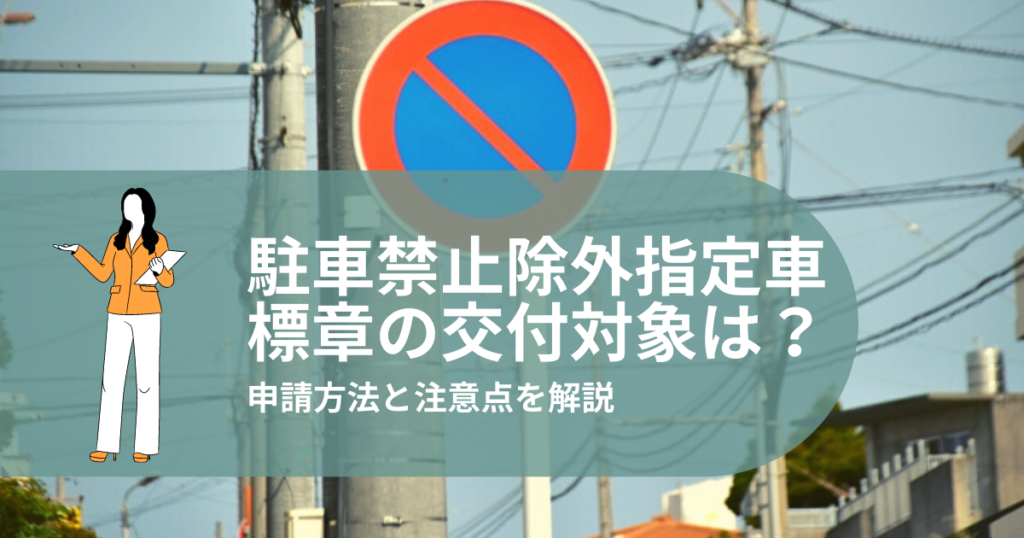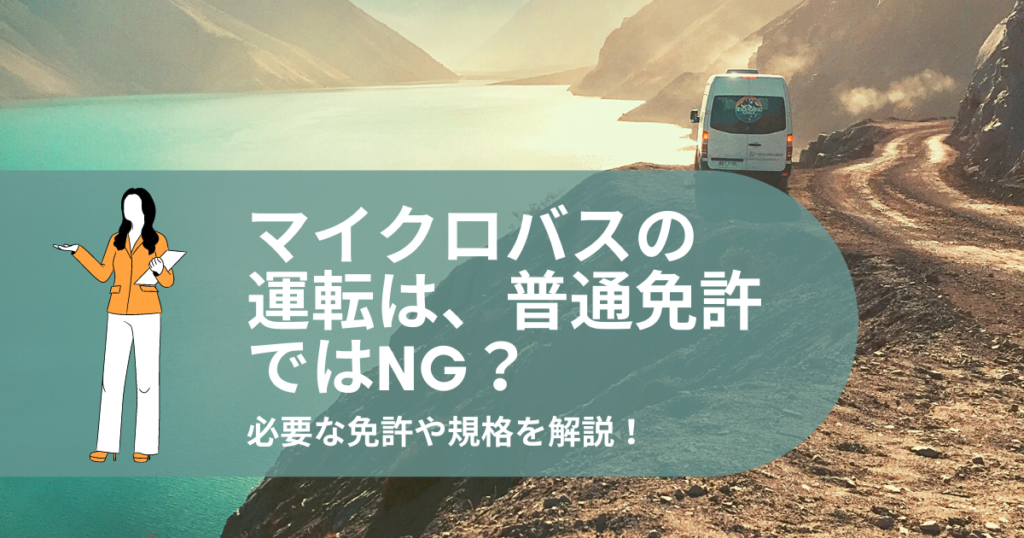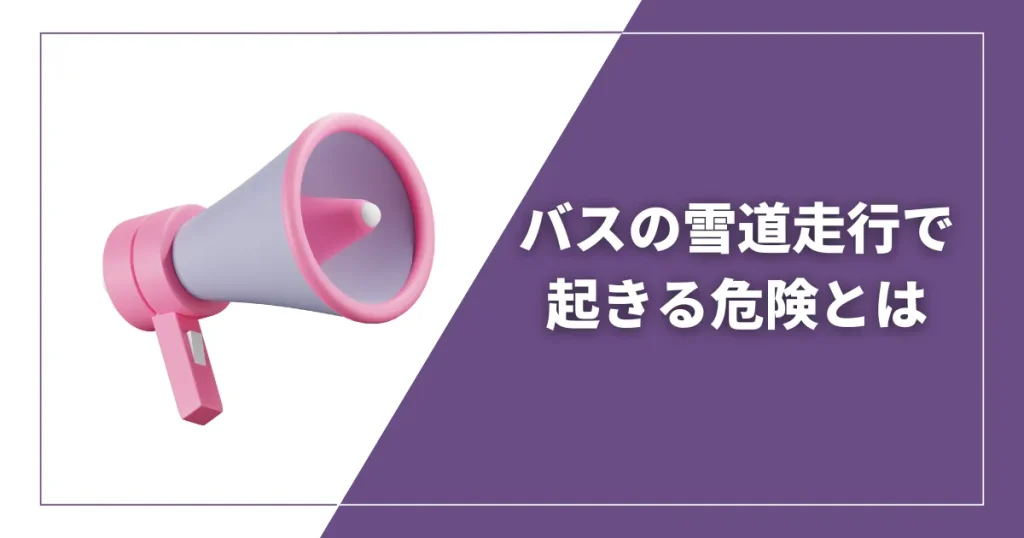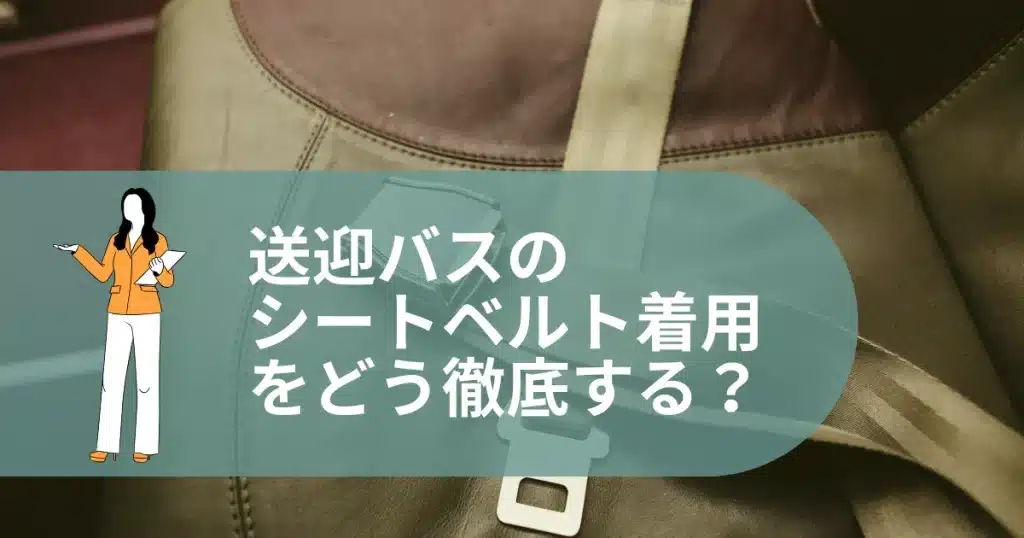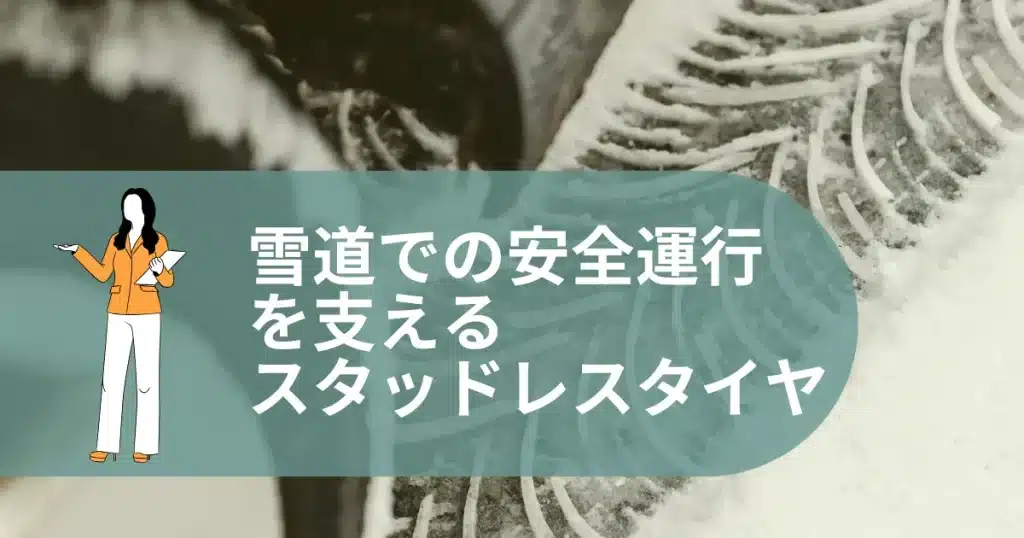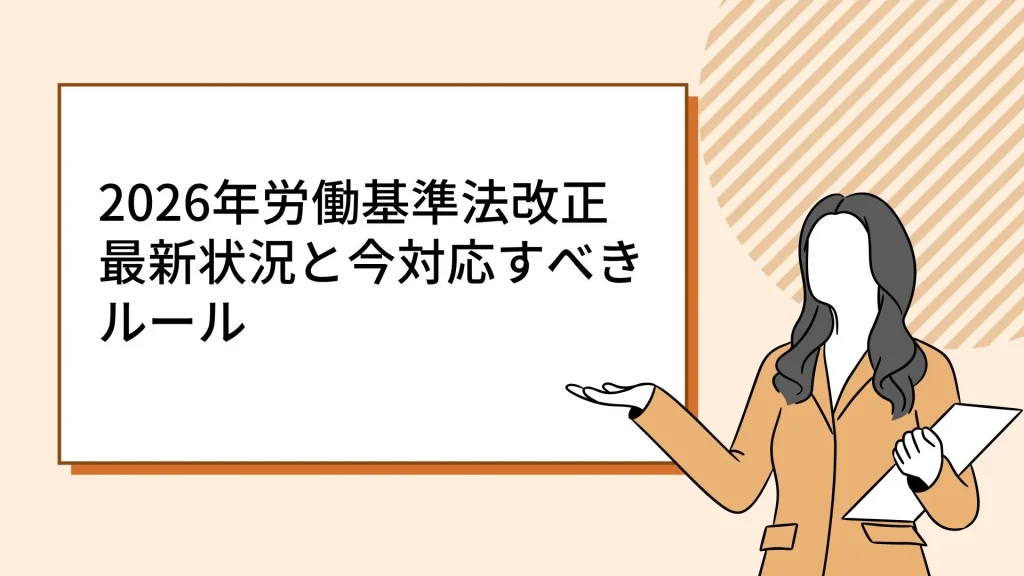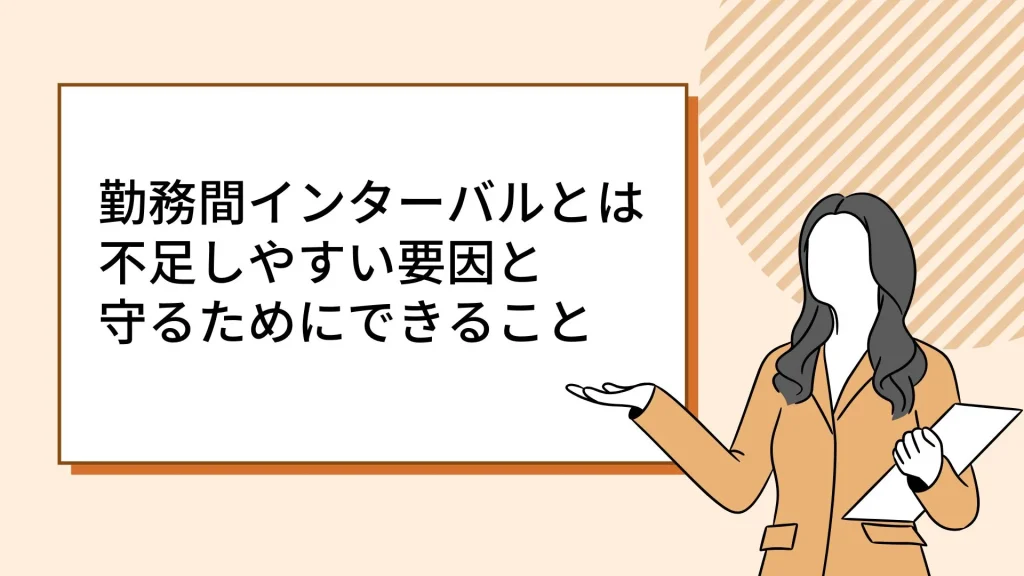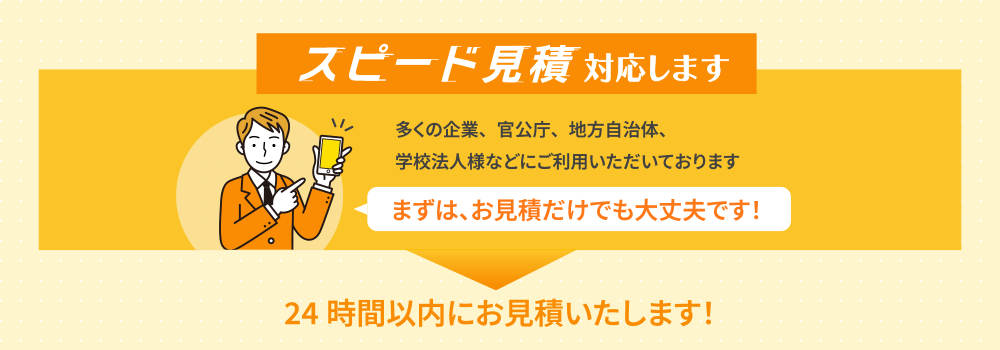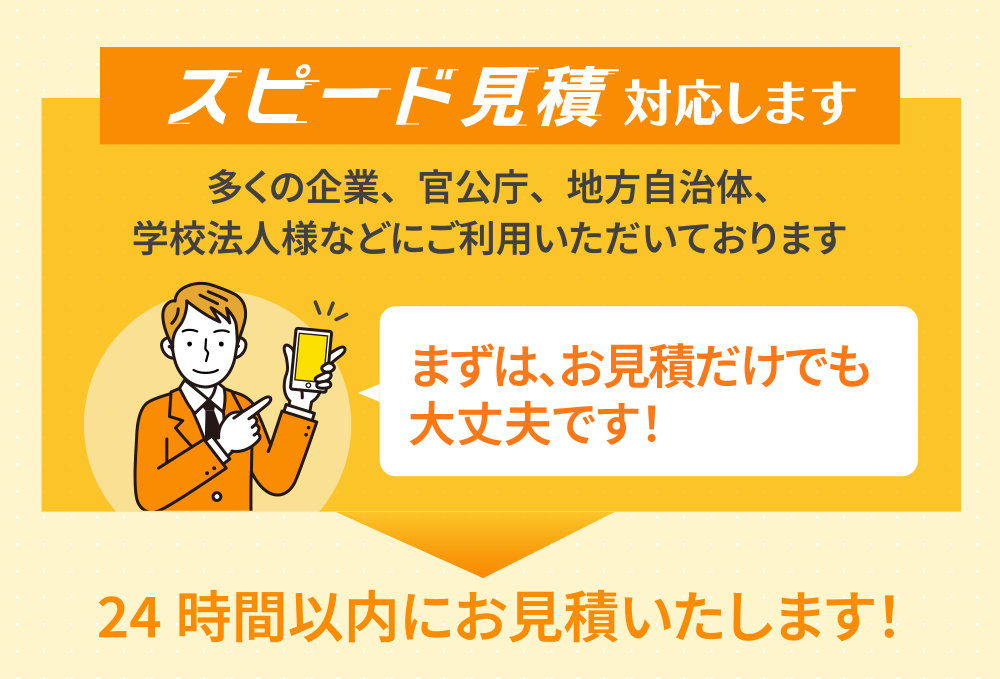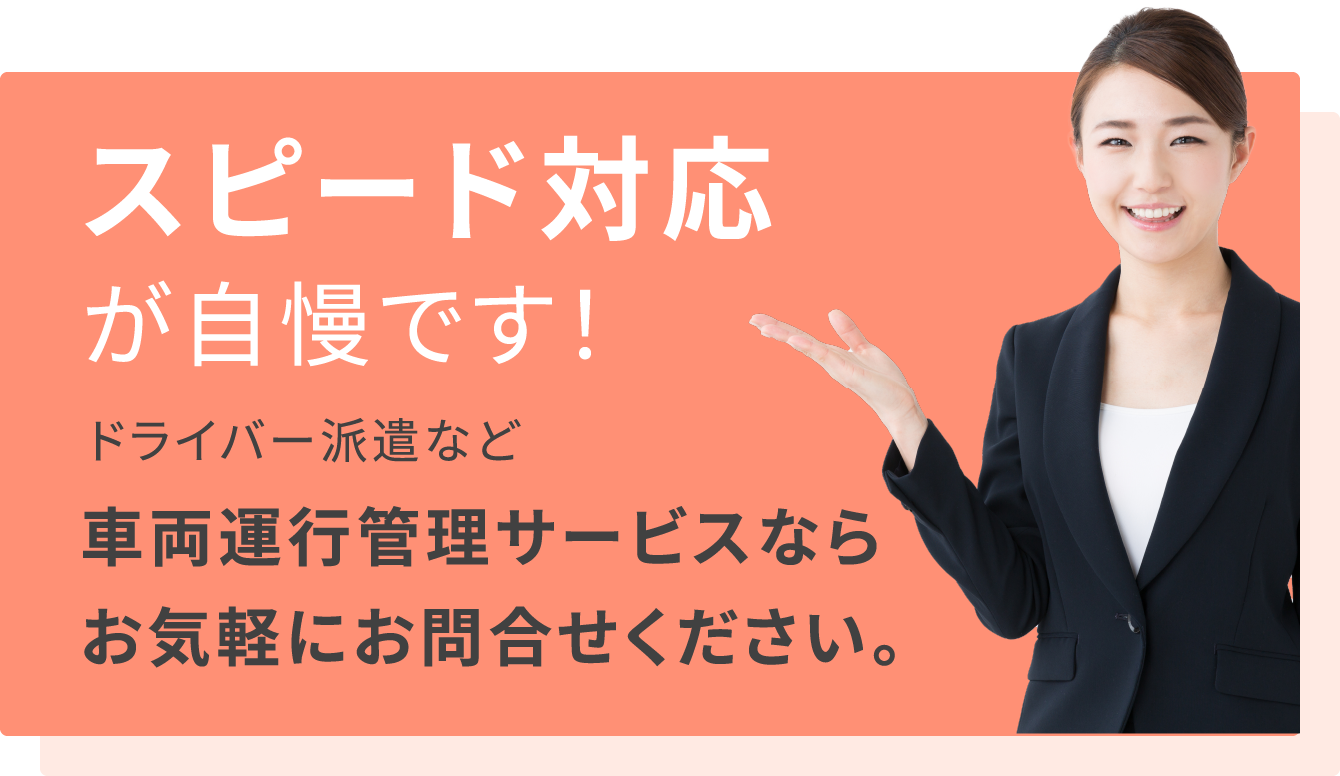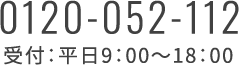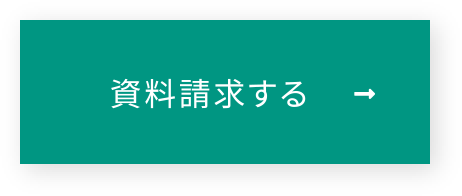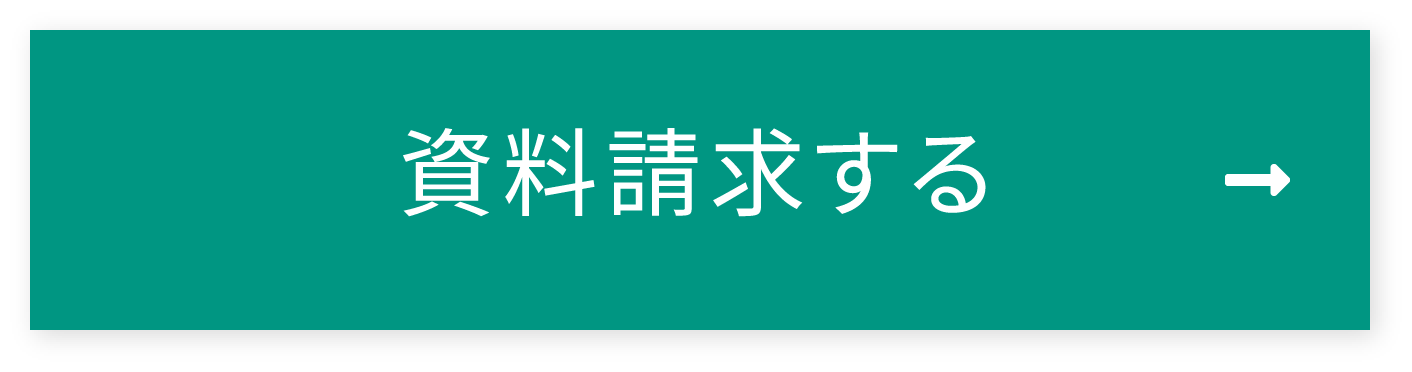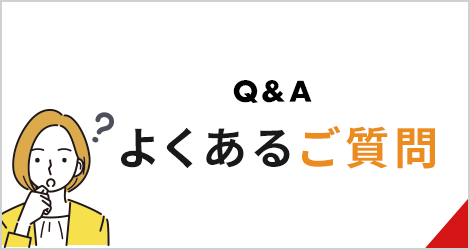2025.03.16
カテゴリ:法務/労務管理/規制
タグ:
昔の普通免許で運転できる車の条件とは?制度の変遷や他の免許との違い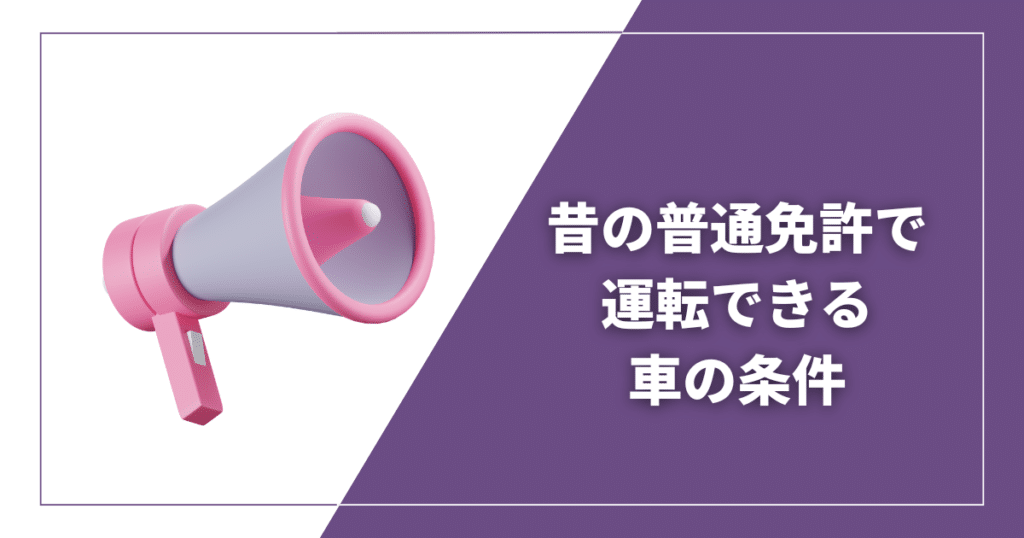
自分の免許で運転可能な車両が分からず困った経験はありませんか?実は、普通免許で運転できる車の範囲は、免許取得の時期によって異なります。制度の変更により、以前は普通免許で運転できた車でも、現在では中型免許や準中型免許が必要となる場合があります。
この記事では、普通免許の制度がどのように変わってきたのか、その背景やどの車両が運転できるのかを詳しく解説します。また、自分の免許で運転可能な車を確認する方法や、、注意すべきポイントについても紹介します。
この記事を読むことで、自分の免許の有効範囲を正しく理解し、誤った運転でトラブルにならないように対策できるようになります。免許で運転できる車に不安がある方は、不安がある方はぜひ最後まで読んでみてください。
昔の普通免許とは?制度の変遷と区分変更の背景
昔の普通免許とはどのようなものなのか、まずは制度の変遷や制度が変わった背景について詳しく解説します。
昔の普通免許と現在の普通免許の違い
昔の普通免許は、現在の普通免許よりも運転できる車両の範囲が広かったのが特徴です。現在では中型免許や準中型免許が必要な車両も、取得時期によっては普通免許で運転できることがあります。
普通免許を取得した時期によって、運転可能な車両の条件は以下のように異なります。
|
取得時期 |
運転できる車両の条件 |
|
2007年6月1日以前 |
乗車定員:10人以下 |
|
2007年6月2日〜2017年3月11日 |
乗車定員:10人以下 |
|
2017年3月12日以降 |
乗車定員:10人以下 |
乗車定員が10人以下であることは変わりませんが、車両総重量と最大積載量は法改正ごとに小さくなっています。
自分が保有する免許で、どのような車両であれば運転できるのか、正しく把握しておきましょう。
普通免許の区分変更の背景
普通免許の区分が変更された背景には、交通安全の向上と免許制度の適正化があります。
2007年の改正前は、普通免許で運転できる車両の範囲が広すぎて、十分な経験がないドライバーが大きな車両を運転し、事故を引き起こすケースが多くありました。そのため、より適正な免許区分を設けることで、ドライバーのスキルに応じた車両を運転できるようにしたのです。
この変更により、普通免許で運転できる車両の範囲は狭くなりましたが、その分、大きな車両による事故の減少に繋がっています。
昔の普通免許と中型免許・準中型免許との違い
普通免許で運転できる車両の範囲が変更された際、中型免許や準中型免許といった新しい免許区分が導入されました。この改正により、運転可能な車両の範囲がさらに細分化されました。
中型免許・準中型免許で運転できる車両の条件は次の通りです。
|
中型自動車免許 |
乗車定員:11人以上29人以下 |
|
準中型免許 |
乗車定員:10人以下 |
以前、普通免許で運転できた車両は、準中型免許の範囲に近いものでしたが、制度改正により制限が厳しくなりました。
そのため、現在トラックの運転が必要な職業では、追加で免許を取得しなければならないケースが増えています。
免許更新で変わることと注意点
昔の普通免許を持っている人は、免許を更新しても運転できる車両の範囲に変更はありません。ただし、免許証の表記や制度変更には注意が必要です。
例えば、2007年以前に普通免許を取得した人の免許証には「中型(8t限定)」と表記されます。
「中型」と書かれてはいるものの、これは現在の中型免許とは異なり、「最大8トンまで運転可能な旧普通免許」を示しています。この違いを把握していないと、「中型トラックなら全て運転できる」」と誤解するケースもあるでしょう。
免許更新時には、自分の免許がどの車両に適用されるのかをしっかり確認し、誤った運転をしないよう気をつけることが重要です。
昔の普通免許を持つ人が知っておくべき事
昔の普通免許を持っている方は、運転に関して以下の点を知っておきましょう。それぞれ、詳しく解説します。
- 昔の普通免許で運転できる車の確認方法
- 制限を超える車を運転した場合のリスク
- 業務での運転における注意点
昔の普通免許で運転できる車の確認方法
昔の普通免許で運転できる車両を確認するためには、免許証に記載された情報や道路交通法に基づく規定をしっかり理解することが必要です。
2007年以前に普通免許を取得した場合「中型車は中型車(8t)に限る」、2007年6月2日〜2017年3月11日の間に免許を取得した場合には「準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許証に記載されます。
運転可能な車両を正確に把握するためには、免許証の表記を確認するとともに、国土交通省や警察庁の公式サイトで免許制度を確認しましょう。
制限を超える車両を運転した場合のリスク
自分が持っている免許の範囲を超える車両を運転すると、無免許運転と見なされ重大な罰則を受ける可能性があります。無免許運転は行政処分の対象となり、25点の違反点数が加算されるため、免許の取消や長期間の免許停止となるケースも少なくありません。
さらに、事故を起こした場合、保険会社が「免許の範囲外の運転」と判断すると、補償が受けられない可能性もあります。
誤って免許の範囲外の車両を運転した場合でも「間違えた」では済まされません。
法律上のリスクだけでなく事故時の責任や保険の適用にも影響を及ぼすため、事前にしっかり確認し、適切な免許を取得しましょう。
業務での運転における注意点
昔の普通免許を持っている方が業務で車を運転する際には、ドライバーだけでなく企業側も、業務用車両が免許の範囲内かを事前に確認しておかなければなりません。免許の範囲を超えた車両を運転した場合、企業側も責任を問われる可能性があります。
企業が従業員に運転業務を任せる際には、ドライバーの免許証の種類と業務用車両のスペックが合致しているかを確認する義務があります。特に物流業界や建設業界では、重量や積載量の異なる複数の車両を扱う企業も多いため、念入りに注意しなければなりません。場合によっては、追加で免許の取得を促すことも考慮すべきです。
業務で車の運転が必要になる場合には、ドライバーだけでなく企業側も責任を持ち、従業員が適切な免許で運転しているか管理する必要があります。
自分の免許で運転できる車を確認しよう
普通免許で運転可能な車両の重量や積載量は、免許を取得した時期によって異なります。
現在の普通免許とは異なる条件が適用されている場合は、免許の記載をよく確認しましょう。さらに、自分が運転できる車両の条件を把握するためには、国土交通省や警察庁の公式サイトも活用してみてください。
業務で車を利用する場合には、ドライバー自身だけでなく、企業側も免許と運転する車のスペックが合致しているか確認する必要があります。
まずは、自分の免許がどのようなものか、確認してみてください。