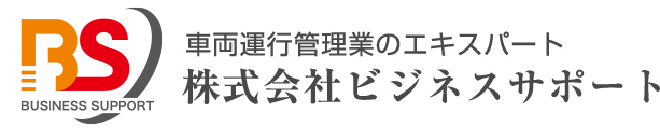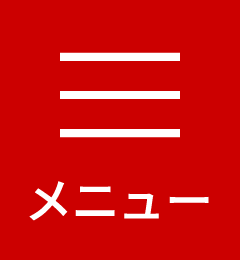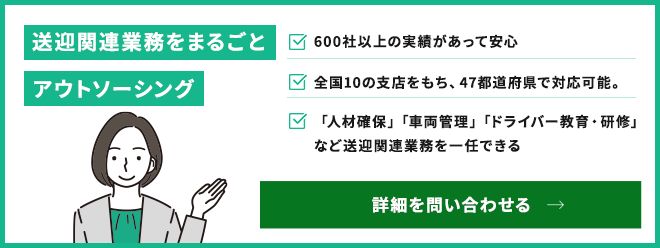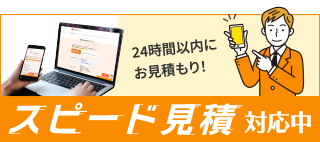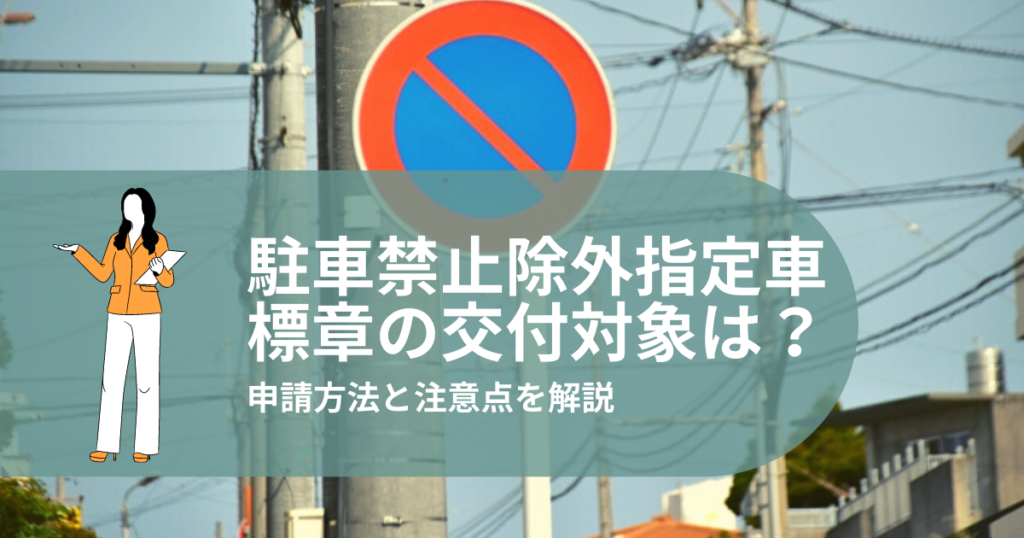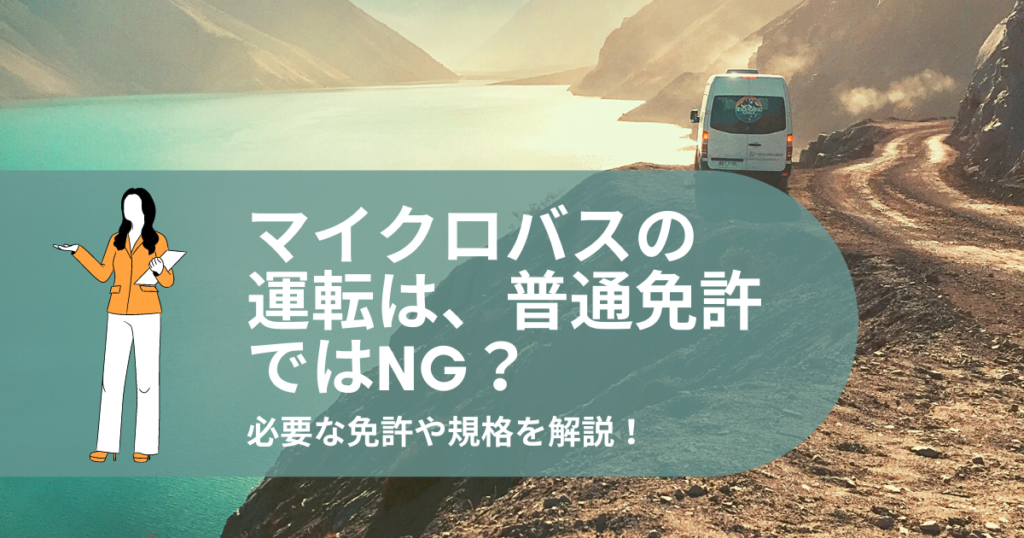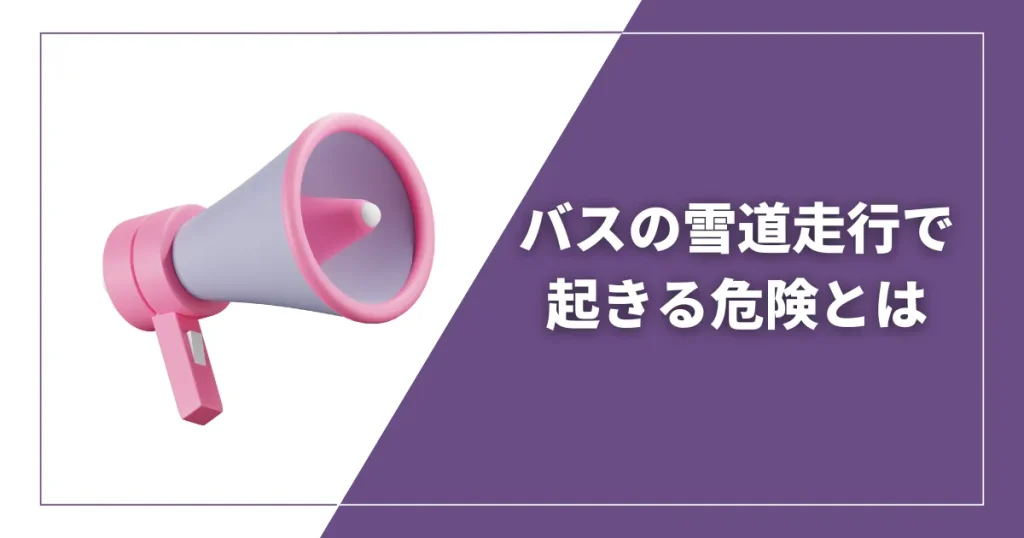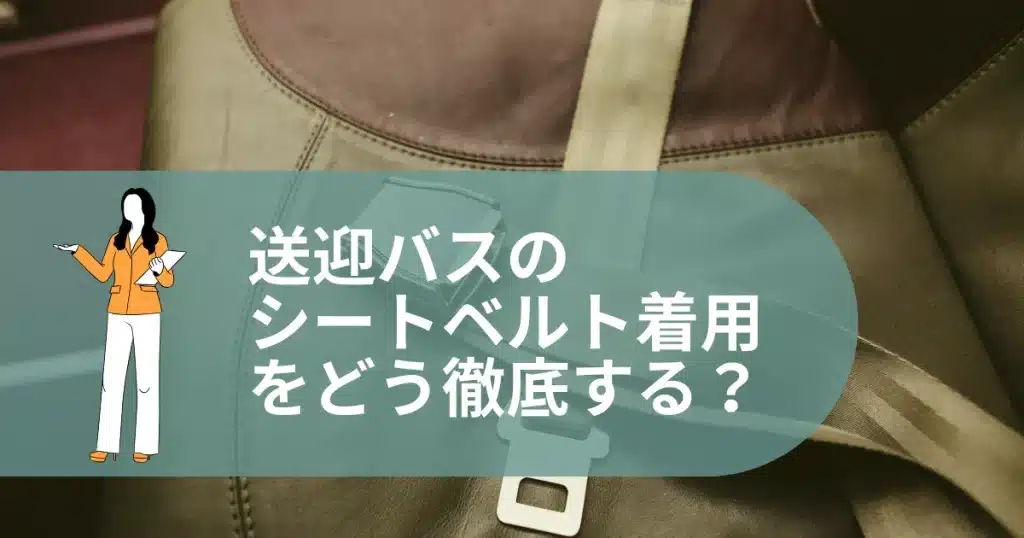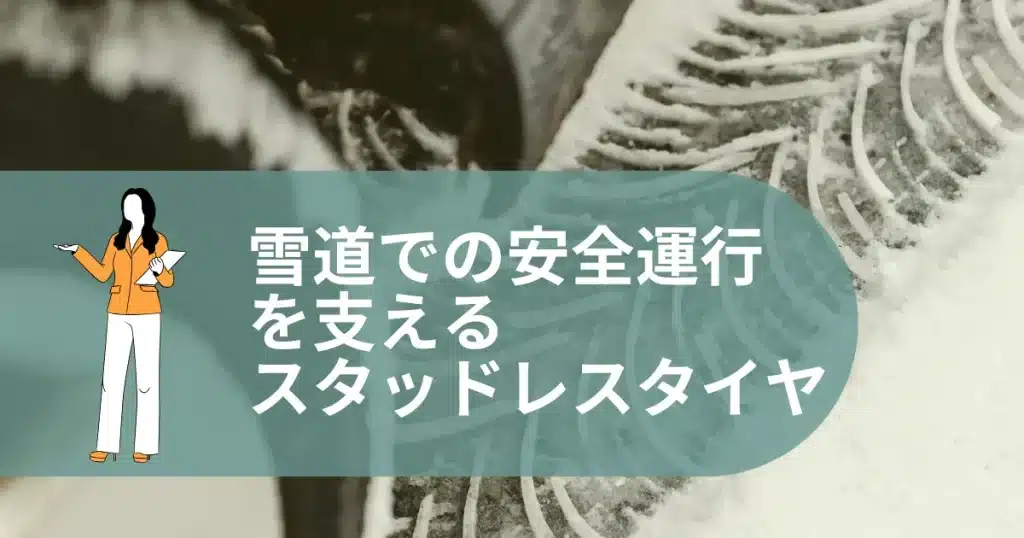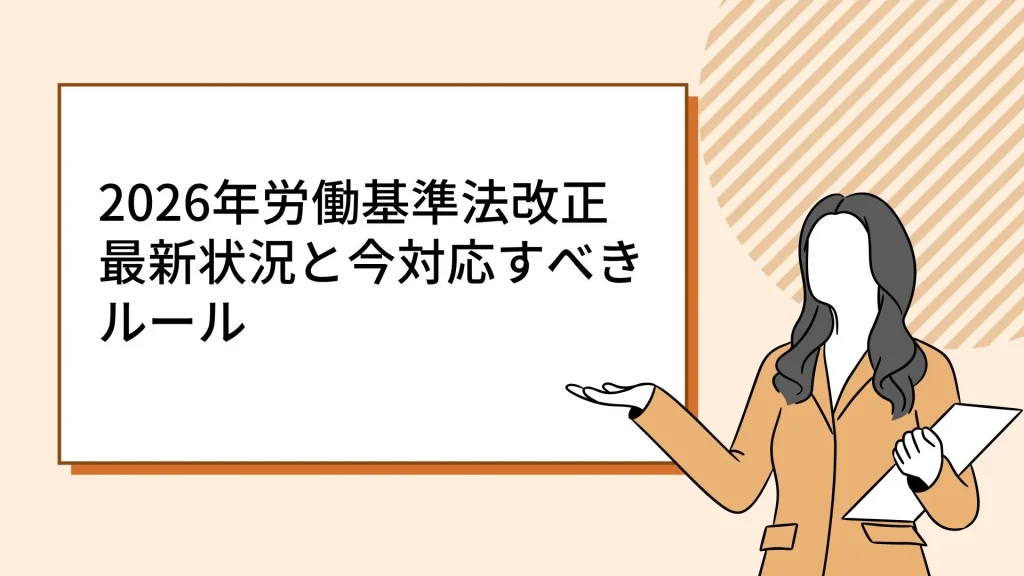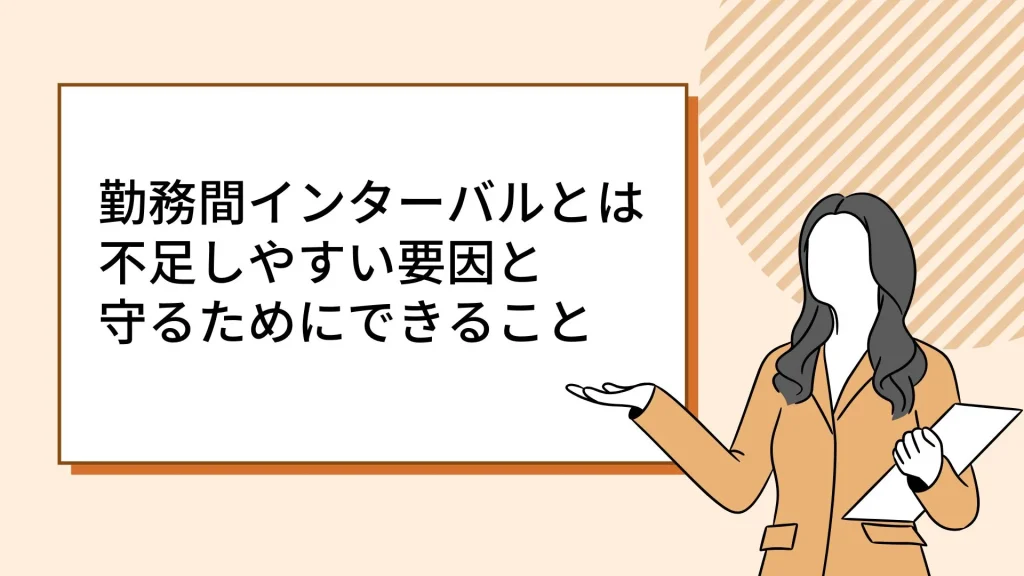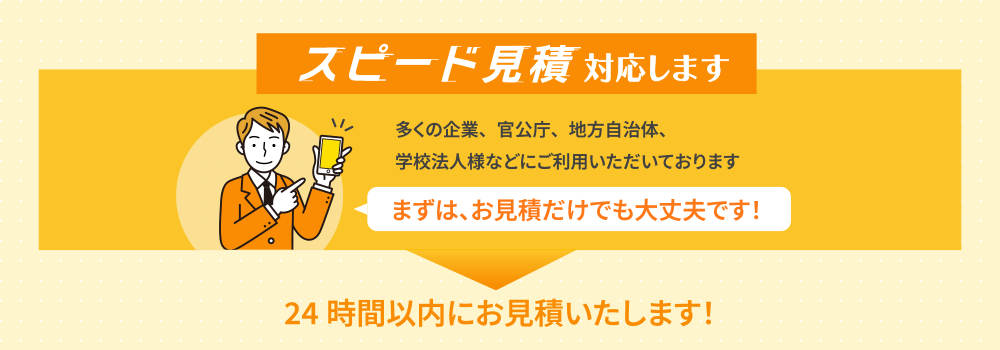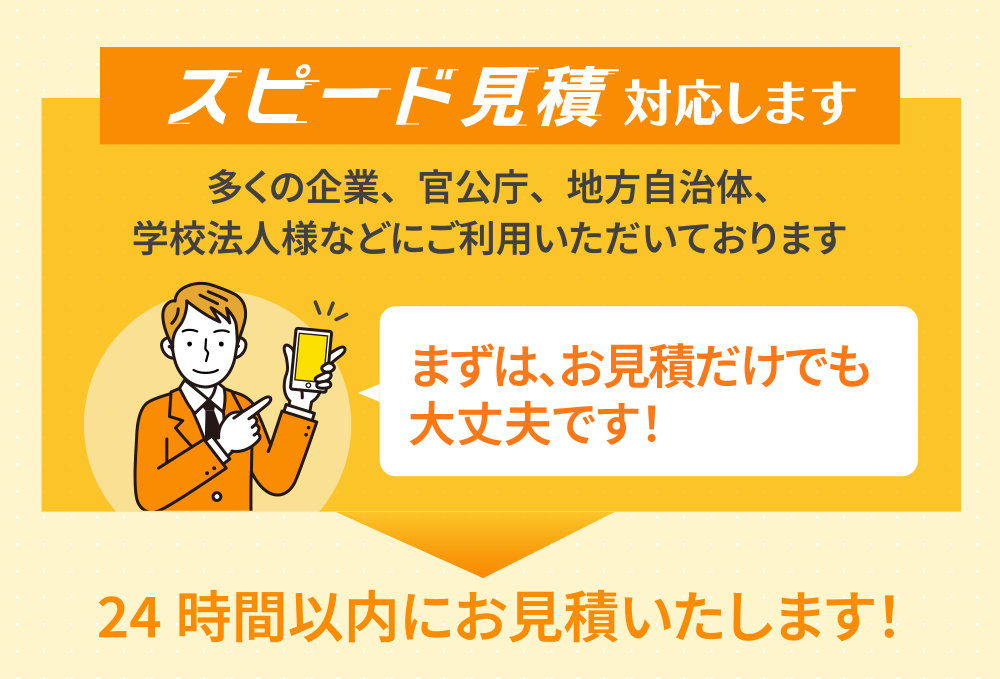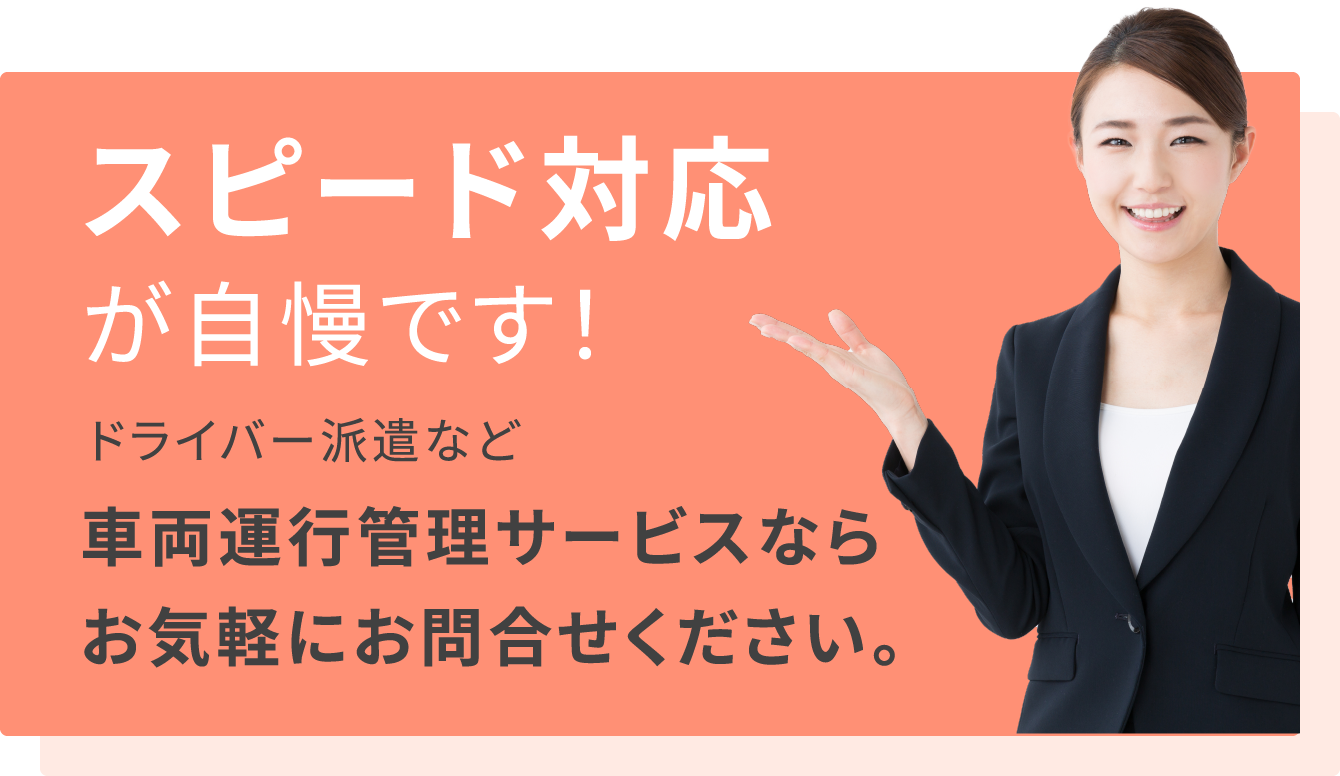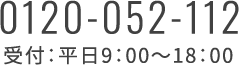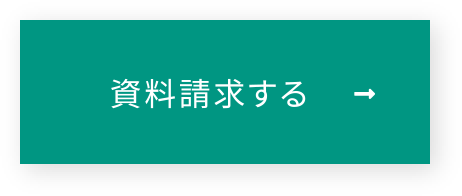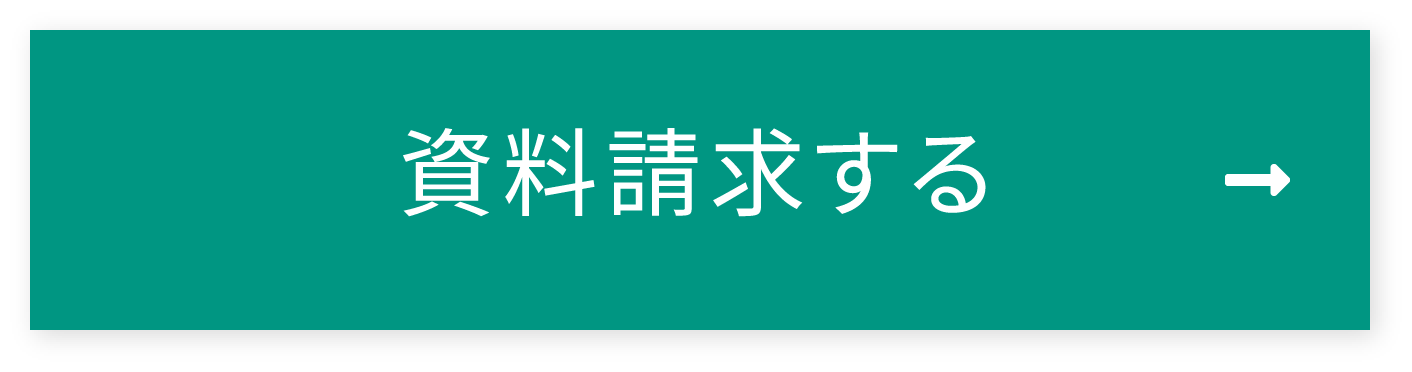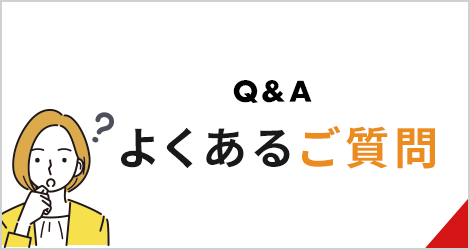2024.02.23
カテゴリ:運行管理
タグ:ノウハウ
安全運転管理者とは?運行管理者との違いや資格要件・業務内容を解説道路交通法施行規則により、規定の台数以上の車を所有する事業者は、安全運転管理者を配置しなければなりません。配置されていない場合、50万円以下の罰金が科せられます。
しかし「どんな人が安全運転管理者になれるの?」「安全運転管理者はどんな仕事をするの?」と悩まれるご担当者様も多くいます。
そこで今回は、安全運転管理者について解説します。安全運転管理者の資格要件や業務内容についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
安全運転管理者とは
安全運転管理者とは、自動車を所有する事業者が、拠点ごとに責任者を選任することで、道路交通法令の遵守や交通違反の防止を図るために定められた制度です。送迎代行業や運輸業など特定の業種だけでなく、一定台数以上の自動車を所有しているすべての事業者は、使用している車の台数に応じて安全運転管理者等を配置しなければなりません。
道路交通法施行規則では、次のような場合は安全運転管理者等の配置が定められています。
|
安全運転管理者 |
・11人以上の自動車の場合を1台所有している ・その他の自動車を5台以上所有している 上記のいずれかに該当する場合1名の配置が必要 |
|
副安全運転管理者 |
・20台以上の車両を所有する場合に1名の配置が必要 ・以降、20台ごとに1名追加で配置が必要 |
自動二輪車を所有している場合には、0.5台としてカウントされます。ただし、50cc以下の原動機付き自転車は含みません。
1つの法人で複数の事業所を持っている場合には、事業所ごとに安全運転管理者等の選任と届出が必要です。また、事業所が同じ住所であっても使用者が異なる場合には別々に選任と届出を行わなければなりません。
県警や警視庁のWebページでは事業所が「所有」する車と解説されていますが、自動車の台数のカウントには、従業員の持ち込み車両やリース車両など全ての自動車が含まれますので注意してください。安全運転管理者の配置が必要かどうかあいまいな場合には、必ず県警や警視庁に問い合わせて確認しておきましょう。
よく似た「運行管理者」との違いは?
運行管理者と安全運転管理者は、どちらも法律に基づいて安全管理を行う役割を担います。もっとも大きな違いは、運行管理者が業務用車両の「緑ナンバー」を管理するのに対して、安全運転管理者は乗用車である「白ナンバー」を管理する点です。
例えば、運送業や大型バスの運行などを行う事業所では、運行管理者が必要です。運行管理者は「貨物」と「旅客」の2種類に分かれており、貨物の場合は営業所ごとに運行管理者を配置しなければなりません。また、営業所の車両が29台以下の場合、必要な運行管理業務者は1人ですが、車両が30台追加されるごとに運行管理者を1人ずつ選任する必要があります。
運行管理者を選任している事業所の場合、必ずしも安全運転管理者を選任する必要はありません。
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者は、次のような業務を遂行します。それぞれ、詳しく解説します。
- ドライバーの状況把握
- 安全運転のための運行計画の作成
- 長距離・夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による運転者の状態確認
- アルコールチェックの実施
- 運行日誌の備え付けと記録管理
- ドライバーに対する安全運転指導
- 関係法令の遵守と最新情報の把握
ドライバーの状況把握
安全運転管理者は、ドライバーの運転適性や健康状態を定期的に把握し、適切な指導を行う必要があります。
ドライバーの体調不良や運転技能の低下は事故のリスクを高めるため、事前の状況確認が欠かせません。特に、過去に違反や事故歴があるドライバーには、より厳格な管理が求められます。例えば、運転記録証明書を活用し過去の違反歴をチェックすることで、事故のリスクが高いドライバーを特定し、適切な指導を実施できます。また、健康診断の結果をもとに長時間運転が適さないドライバーを把握し、業務内容を調整することも重要です。
ドライバーの状況把握は安全運転を維持するために欠かせない業務であり、定期的な確認と適切な対応が求められます。
安全運転のための運行計画の作成
安全運転管理者は、無理のない運行計画を策定しドライバーの負担を軽減することで、事故のリスクを抑えなければなりません。過密なスケジュールや長時間運転は疲労の蓄積を招き、注意力の低下を引き起こします。特に、深夜や悪天候時の運転は視認性が低下し事故のリスクが高まるため、適切な運行管理が求められます。
例えば、長距離輸送では運転時間が一定時間を超えないよう休憩を適切に配置し、ドライバーの疲労を軽減することが重要です。また、天候や道路状況を考慮し渋滞や悪条件を避けるルートを選定することで、より安全な運行が可能になります。さらに、ドライブレコーダーや運行管理システムを活用しリアルタイムで運行状況を把握することで、突発的なトラブルにも迅速に対応できます。
安全な運行を実現するには、計画的なスケジュールの策定が不可欠です。適切な休憩時間の確保やリスクを考慮したルート選定を徹底することでドライバーの健康と安全を守り、事故の発生を未然に防げるのです。
長距離・夜間運転時の交代要員の配置
長距離や夜間運転を行う際は、適切な交代要員を配置し、運転者の疲労を軽減しなければなりません。長時間運転による疲労は居眠り運転や判断力の低下を引き起こし、大事故につながる可能性が高まります。特に深夜の運転は視認性が低下し危険回避の判断が遅れるため、安全対策を徹底しなければなりません。
例えば、高速道路を利用する長距離輸送では、運転時間が4時間を超えないよう休憩を適切に設定し、必要に応じてドライバーを交代させることが求められます。また、夜間運転では、事前に仮眠を取る場所を決め交代がスムーズに行える環境を整えることで、安全性の工場が可能です。さらに、運行管理システムを活用しリアルタイムで運転状況を把握することで、疲労の蓄積を早期に検知し適切な対応が取れます。
交代要員の適切な配置は長距離・夜間運転におけるリスクを大幅に低減させるため、安全運転管理者が徹底しなければならない重要な管理項目です。
異常気象時等の安全確保の措置
異常気象時には、ドライバーの安全を最優先に考え適切な安全確保の措置を講じなければなりません。
大雨、台風、大雪などの異常気象時は、視界不良や路面の滑りやすさが原因で事故のリスクが大幅に高まります。強風による車両の横転や冠水によるスリップ事故など天候による危険が増大するため、適切な運行管理が求められます。
例えば台風が接近している場合は、事前に天候情報を確認し運行の延期や別ルートへの変更を判断する必要があるでしょう。また、大雪が予想される際にはスタッドレスタイヤの装着やチェーンの携行を義務付けることで、スリップ事故のリスクを低減できます。さらに、道路の通行止め情報をリアルタイムで把握し、迅速な判断ができる体制を整えることも重要です。
異常気象時の対応を迅速かつ適切に行うことで、事故を未然に防ぐだけでなくドライバーの安全を確保し、企業の責任を果たすことにもつながります。
点呼等による運転者の状態確認
安全運転管理者は出発前や帰着時に運転者の状態を確認し、運転に適した状態であることを確実に把握しなければなりません。
運転者の疲労や健康状態の変化を見落とすと、事故のリスクが大幅に高まります。特に、長時間運転や過労は判断力の低下を招き重大事故につながる要因となるため、点呼による確認が不可欠です。
例えばトラック運送業界では、点呼時に「顔色」「声のトーン」「目の充血」などをチェックし、運転者が体調不良でないかを確認することが義務付けられています。また、睡眠不足や体調不良の兆候が見られた場合は運転を中止させる判断や適切な休憩を指示することで、事故のリスクを軽減可能です。さらに、アルコールチェックを実施することで、飲酒運転の未然防止にもつながります。
点呼を通じて運転者の健康状態や疲労度を適切に把握することは、安全運行を確保するために欠かせない業務です。安全運転管理者は、運転者の状態を正確に見極め、的確な指示を行うことで、事故を未然に防ぐ役割を果たさなければなりません。
アルコールチェックの実施
安全運転管理者は運転者の酒気帯び運転を防止するため、アルコールチェックを確実に実施しその結果を記録・保存しなければなりません。
アルコールチェックを怠ると飲酒運転による事故のリスクが高まり、企業の管理責任が厳しく問われます。特に、2023年の道路交通法改正により事業所におけるアルコールチェックの義務が強化され、適切な管理体制の構築が求められています。違反した場合は罰則の対象となるだけでなく、企業の信頼低下にも直結します。
適切なタイミングと手順で運転者の呼気を測定するとともに、結果を保存しておくことが重要です。さらに、万が一アルコール反応が検出された場合の対応手順を明確にし、違反者への指導や再発防止策の徹底が求められます。
アルコールチェックは、事故防止と法令遵守の観点から欠かせない業務です。企業リスクを回避し社会的信用を維持するためにも、確実に実施しなければなりません。
運行日誌の備え付けと記録管理
安全運転管理者は運転者の業務記録を適切に管理するため、運行日誌を作成し、正確に記録・保存しなければなりません。
運行日誌を適切に管理することで運転者の業務状況を正確に把握し、事故の防止や監査対応が可能になります。過労運転の防止や法令遵守の観点からも重要であり、適切な記録が残っていない場合、企業の管理体制が不十分と見なされるリスクもあるのです。
運行日誌には「運転開始時間」「休憩時間」「走行距離」「燃料補給履歴」などの詳細情報を記録することで、企業が適切な運行管理を実施している証拠を残すことができます。また、デジタル運行記録システムを導入することでリアルタイムの運行状況を把握し、記録の正確性を向上させることも可能です。これにより、監査時の指摘を防ぐだけでなく、業務の効率化にもつながります。
運行日誌の管理は、安全運転管理者の重要な業務の一つです。正確な記録を残すことで法令遵守を徹底し、企業の信頼性を高め、安全で持続可能な運行体制を構築しなければなりません。
ドライバーに対する安全運転指導
安全運転管理者はドライバーに対して定期的な安全運転指導を実施し、事故を未然に防ぐための教育を徹底しなければなりません。
交通事故の多くは、運転者の不注意や交通ルールの違反によって発生します。特に、漫然運転や速度超過、脇見運転は重大事故につながるリスクが高いため、定期的な安全教育を行い運転者の意識を高めることが重要です。企業として適切な指導を行わなかった場合、安全管理体制が不十分とみなされ、社会的な信頼を損なう可能性もあります。
例えば、ドライブレコーダーの映像を活用し、実際に発生した事故やヒヤリハット事例を分析する研修を実施することで、ドライバー自身が具体的なリスクを認識できます。また、運転シミュレーターを用いた危険予測トレーニングを取り入れることで、危険回避能力を向上させることが可能です。さらに、安全運転講習や外部講師による研修を定期的に開催し、最新の交通ルールや安全運転技術を学ぶ機会を設けることも有効です。
定期的な安全運転指導は、事故の未然防止と企業の社会的責任を果たすために欠かせません。継続的な教育と実践を通じて安全意識を高め、ドライバーが安心して運転できる環境の整備が求められます。
関係法令の遵守と最新情報の把握
安全運転管理者は道路交通法や関連法令の最新情報を常に把握し、適切な対応を講じなければなりません。
近年の法改正により、企業の管理体制が厳しく問われる場面が増えています。最新の法律に対応できない場合、企業のコンプライアンス違反が指摘されるだけでなく、事故発生時の責任がより重く問われる可能性があります。法令を正しく理解し、迅速に対応できる体制を整えなければなりません。
例えば、2023年の道路交通法改正では、アルコールチェックの義務化が強化され、すべての事業所で酒気帯び確認と記録保存が必須となりました。これに伴い、多くの企業がアルコール検知器の導入やチェック体制の見直しを行いました。また、電動キックボードの規制緩和により、新たな運転ルールが適用され、社用車以外の移動手段に関する社内ルールを再検討する企業も増えています。さらに、今後の法改正では、安全運転管理者の役割や責任が拡大する可能性もあり、最新情報の把握が欠かせません。
関係法令の遵守と最新情報の把握は、企業のリスク管理とコンプライアンス維持において極めて重要です。法改正に適応し、適切な管理体制を整えることで、安全な運行環境を確保し、企業の社会的責任を果たさなければなりません。
安全運転管理者を選任しなかった場合の罰則と企業リスク
安全運転管理者を選任しなかった場合、企業には次のような罰則やリスクが生じます。それぞれ、詳しく解説します。
- 罰金と行政処分
- 監査や指導の強化
- 交通事故発生時の企業責任が増大
- 社会的信用の低下
- 従業員に対する安全確保の責任を果たしていないとみなされる可能性
- アルコールチェック義務違反
罰金と行政処分
安全運転管理者を選任しなかった場合、企業は道路交通法違反となり、罰則の対象となるだけでなく事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。道路交通法では、一定の条件を満たす事業所に対し安全運転管理者の選任が義務付けられています。違反した場合、最大50万円の罰金が科される可能性があるのです。さらに、悪質な違反が続いた場合、事業停止命令や業務改善命令が下されるケースもあります。これにより、取引先からの信用を失い、事業継続が困難になるリスクも考えられるでしょう。
また、万が一選任義務を怠った事業所で重大事故が発生した場合、管理責任が問われ企業の経営にも深刻な影響を及ぼしかねません。法的リスクを回避し企業の信頼を守るためにも、安全運転管理者を確実に選任し、適切な管理を行うことが重要です。
監査や指導の強化
安全運転管理者が不在、または適切に業務を遂行していない場合、企業は監査や指導の対象となり厳しい行政措置を受けるリスクがあります。
企業の安全管理が不十分と判断されると公安委員会や労働基準監督署による監査が実施され、業務改善命令や罰則が科される可能性が高まります。特に、安全運転管理に関する法令違反が指摘された場合、企業のコンプライアンス体制が問われ取引先や社会からの信用を大きく損なう恐れもあるでしょう。
例えば、運行記録の不備やアルコールチェックの未実施が発覚すると、是正指導が入るだけでなく状況によっては罰則が適用されるケースもあります。さらに、過去に同様の違反があった場合や、企業として適切な対策を講じていないと判断された場合、行政処分が強化される可能性も否定できません。
適切な安全管理を徹底し監査に備えることは、企業の社会的責任を果たすうえで不可欠です。法令遵守の意識を高め万全な管理体制を整えることで、リスクを最小限に抑え、安全な運行環境を維持しなければなりません。
交通事故発生時の企業責任が増大
安全運転管理者が不在の場合、企業は交通事故発生時の責任をより重く問われ、法的・経済的なリスクを抱えることになります。
適切な安全管理が行われていない場合、企業の「使用者責任」が問われ、損害賠償の請求を受けるリスクが大幅に高まります。特に、企業が安全対策を怠っていたと判断された場合、被害者側から厳しい責任追及を受ける可能性があるでしょう。
例えば、業務中に従業員が重大な交通事故を起こした場合、安全運転管理者が適切な指導や管理を行っていれば「必要な安全対策を講じていた」として企業の責任が一部軽減される可能性があります。しかし、安全運転管理者が不在で運転者に対する教育や指導が十分に行われていなかった場合、企業の管理責任が問われ、過失が大きいと判断される可能性が高まります。その結果、高額な損害賠償を請求されるだけでなく、企業の法的リスクが拡大し経営に深刻な影響を及ぼしかねません。
企業のリスクを最小限に抑え安全な運行環境を確保するためにも、安全運転管理者の設置は不可欠です。
社会的信用の低下
安全運転管理が適切に行われていない場合、企業の社会的信用が低下し取引先や顧客からの信頼を大きく損なう可能性があります。
特に重大事故を引き起こした場合、その影響は企業のブランド価値の低下にとどまらず、契約の打ち切りや売上減少といった経営上の損失につながります。さらに、安全管理体制が不十分であると判断されると、新規取引の獲得が難しくなり事業の成長にも悪影響を及ぼすでしょう。一度失われた信用を回復するには、多大な時間とコストがかかるため、未然にリスクを防ぐことが不可欠です。
社会的信用を維持し企業のブランド価値を守るためにも、安全運転管理は徹底しなければなりません。
従業員に対する安全確保の責任を果たしていないとみなされる可能性
安全運転管理者を選任せず、適切な安全管理が行われていない場合、企業は「従業員の安全確保義務を果たしていない」と判断され重大な法的責任を問われる可能性があります。企業には労働安全衛生法に基づく「安全配慮義務」があり、従業員の健康と安全を確保する責任があります。安全運転管理者を選任せず、必要な管理体制を整えていない場合、この義務を果たしていないと見なされ行政処分や損害賠償請求の対象となるリスクが高まるのです。特に、安全管理の不備が原因で事故が発生した場合、企業の過失が厳しく追及される可能性があります。
企業が従業員の安全を守ることは、法的義務であると同時に、社会的責任でもあります。安全運転管理者の選任と適切な管理体制の構築は、従業員の命を守るために欠かせません。
アルコールチェック義務違反
アルコールチェックを実施しない、または記録を適切に管理しない場合、企業は法的責任を問われるだけでなく、社会的信用の低下や経営リスクを抱えることになります。道路交通法の改正により事業所におけるアルコールチェックの義務が強化され、違反した場合には罰則が科されるだけでなく、企業の管理体制の不備が厳しく追及される可能性があります。
特に、アルコールチェックを怠ったことで飲酒運転が発生し事故につながった場合、企業の安全管理責任が問われ、重大な法的措置が取られる可能性もあるのです。アルコールチェックの徹底は、企業のコンプライアンスを守るためだけでなく、従業員や社会の安全を確保するために不可欠です。適切な管理を徹底し、チェック結果を確実に記録・保存することで、法的リスクを回避し、安全な事業運営を維持しなければなりません。
安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者等になるためには、次のような資格要件が定められています。
|
安全運転管理者 |
副安全運転管理者 |
|
・20歳以上(副安全運転管理者が必要な事業所の場合は30歳以上) |
・20歳以上 |
|
<欠格事項> 上記の要件に該当していても、次のような人は安全運転管理者等にはなれません。 ・事務所に常勤していない人 |
|
欠格事項に該当する「特定の違反」は、県警・警視庁のWebページなどで確認できます。以下に、一部を例として紹介します。
- 交通事故の救護措置義務違反
- 酒酔い・酒気帯び運転またはその下命容認行為
- 過労運転の下命容認行為
- 放置駐車違反の下命容認行為
- 自動車の使用制限命令違反
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者の業務内容としては、大きく「運転者の管理」と「運行業務の管理」の2種類に分けられます。それぞれ、具体的に次のような業務を行います。
|
運転者の管理 |
・安全運転の指示 ・交通安全教育 ・運転者の状況把握 ・運転者の適正などの把握 |
|
運行業務の管理 |
・運転日誌の記録 ・運行計画の作成 ・交代要員の配置 ・異常気象時等の安全確保の措置 |
安全運転管理者は、安全運転教育を行うとともに、点呼などで毎日運転者の状況を確認し、飲酒や過労など正常な運転ができない状態に陥っていないか確認しなければなりません。また、法令を遵守して業務を遂行できるような、運行計画の作成や交代要員の配置も安全運転管理者の仕事です。令和4年の4月と10月には、上記に加えそれぞれ次のような業務が義務化されます。
|
令和4年4月1日から義務化 |
運転前後の運転者の状態を目視で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること |
|
令和4年10月1日から義務化 |
運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと アルコール検知器を常時有効に保持すること |
安全運転管理者などの届出方法
安全運転管理者の選任・解任の際や、届出事項に変更がある場合には、自動車を使用する事業所を管轄する警察署へ所定の日数以内に事業主や所属長など、使用者責任を負う人による届出が必要です。自治体によって手続きの詳細は異なりますが、ここでは愛知県の例を紹介します。
届出書類
届出の際に必要な書類は次の通りです。
|
書類の種類 |
必要な数 |
備考 |
|
安全運転管理者等に関する届出書 |
2部(1部コピー可) |
|
|
履歴書 |
1部 |
|
|
自動車の運転管理経歴書 |
1部 |
副安全運転管理者で、運転管理経歴を有しない場合は不要 |
|
運転記録証明書 |
1部 |
運転免許を保有していれば提出が必要 過去3年間または5年間 |
|
戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し |
いずれか1部 |
運転免許証の写しは裏面記載の有無にかかわらず両面提出が必要 白黒可 |
運転記録証明書を取得するためには、自動車安全運転センターへの申し込みが必要です。申請から発行まで1〜2週間程度かかる場合もあるため、事前に取得を済ませておきましょう。
届出先
届出先は、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口です。選任した日から15日以内に届出を行ってください。受付時間は平日午前8時45分から午後5時30分までです。
安全運転管理者等に選任される本人でなくても届出はできますが、郵送での届出は受け付けていないため注意してください。
安全運転管理者等に対する講習
安全運転管理者や副安全運転管理者は、年に1回公安委員会が行う法定の講習を受けなければなりません。講習では、次のような内容を学びます。
- 道路交通に関する知識
- 自動車の安全な運転に必要な知識
- 運転者に対する安全運転に必要な知識や技能
- 最新の道路交通法や交通事故情勢
法定講習を受けなければ、安全運転管理者等として業務を続けることはできませんので必ず受講しましょう。講習の通知は、講習が行われる約1〜2ヶ月前に届きます。指定された日に受講できない場合には別の日に受講することも可能なので、通知書で対応を確認するか、管轄の警察署に問い合わせてください。
法定講習の受講費は、安全運転管理者は4,500円、副安全運転管理者は3,000円です。受講費の支払い方法は自治体によって異なるため、通知書を確認してください。
事業車の使用には安全運転管理者等が必要
事業に車を使う場合、台数に応じて安全運転管理者や副安全運転管理者を配置する必要があります。安全運転管理者の業務は主に運転者の管理と運行業務の管理です。安全運転管理者になるためには資格要件を満たしている必要があり、年に1回は講習を受けなければなりません。
手続きの詳細は自治体ごとに異なるので、県警・警視庁のWebページを確認してください。
参考:安全運転管理者等の届出手続き|愛知県警察
安全運転管理者等法定講習|警視庁
送迎バスに手が回らず、「なんとなく」で運用してしまっている方へ
「他の業務に追われ、属人的に運用している」
「長年外注しているが、契約内容を見直したい」
このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、送迎ルートの作成、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。
想定送迎人数もしくは車両台数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。
記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。